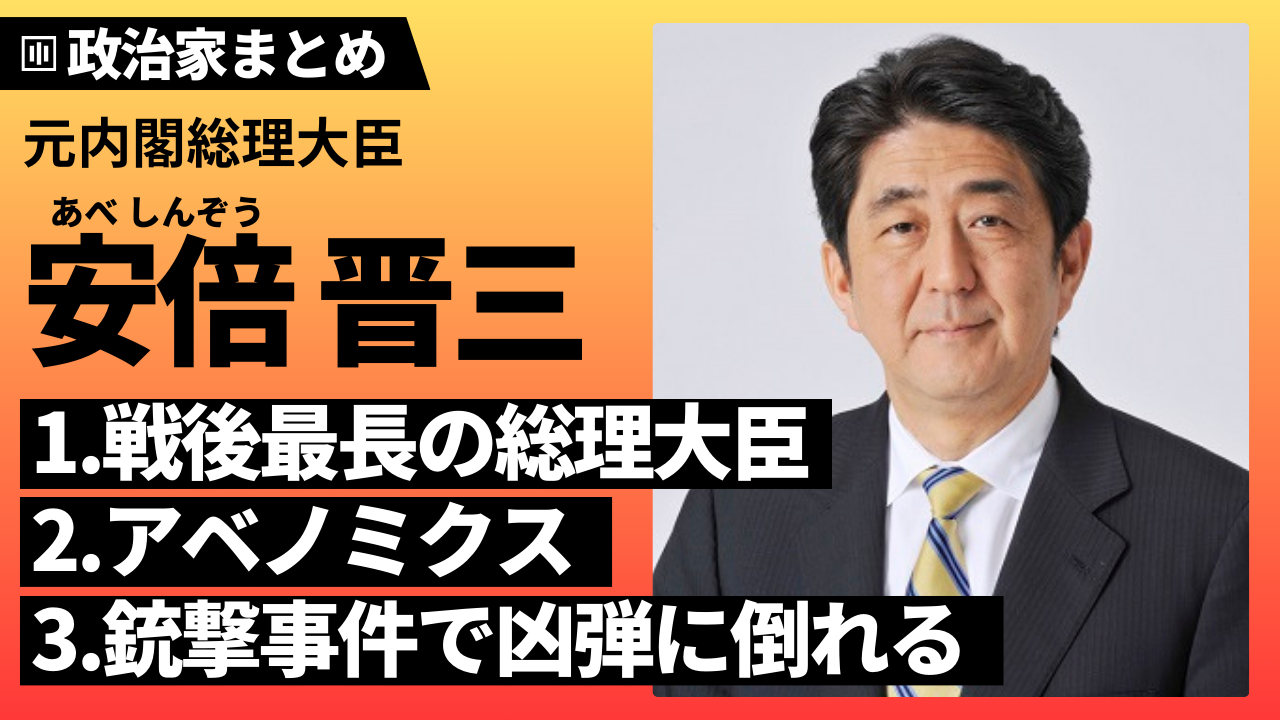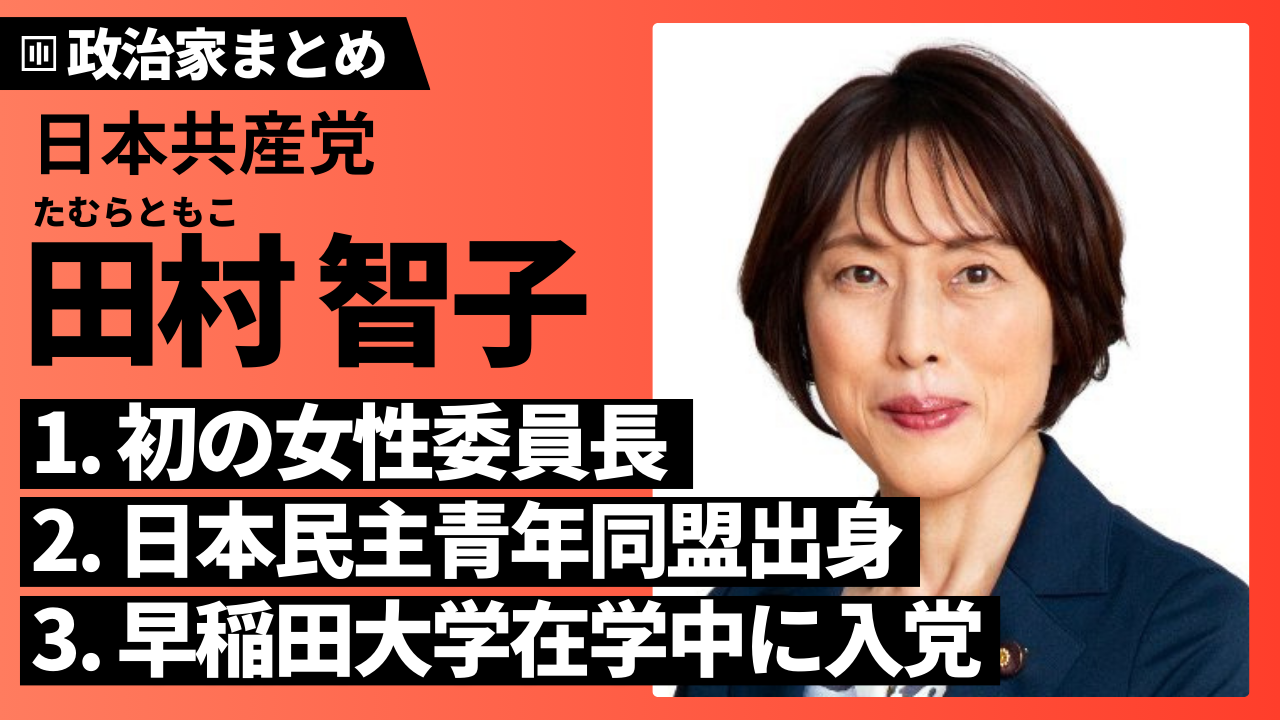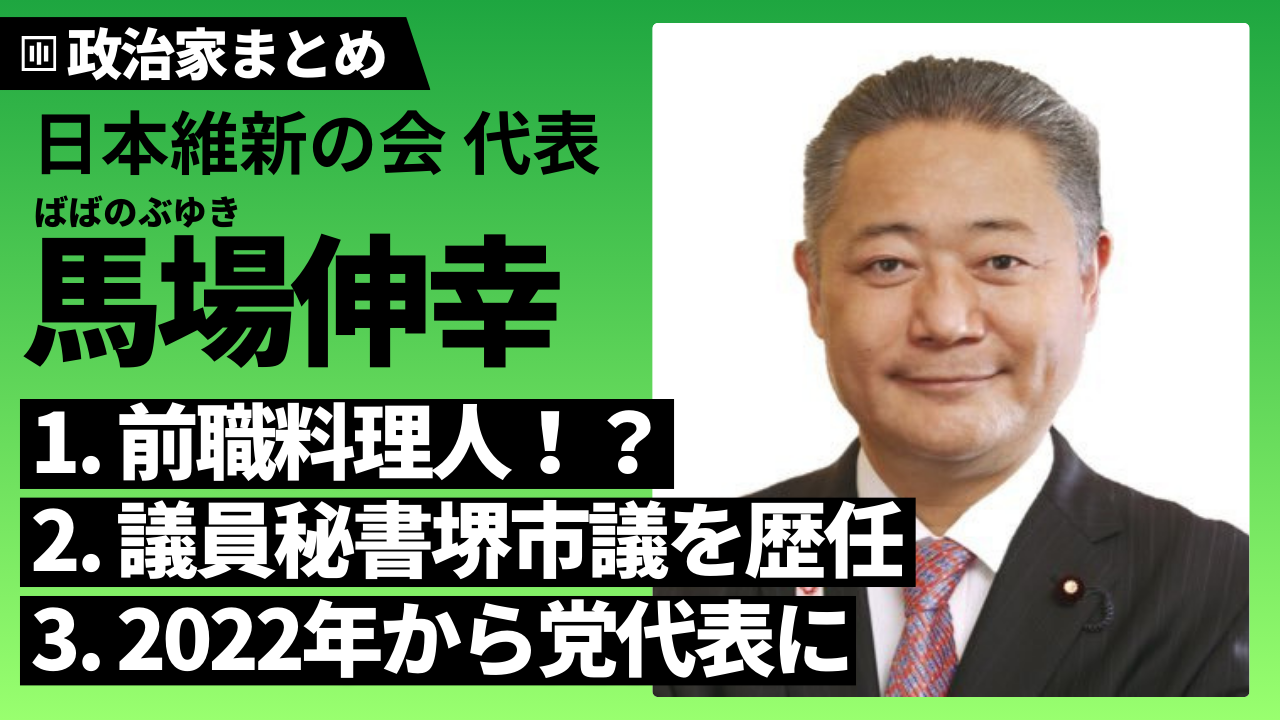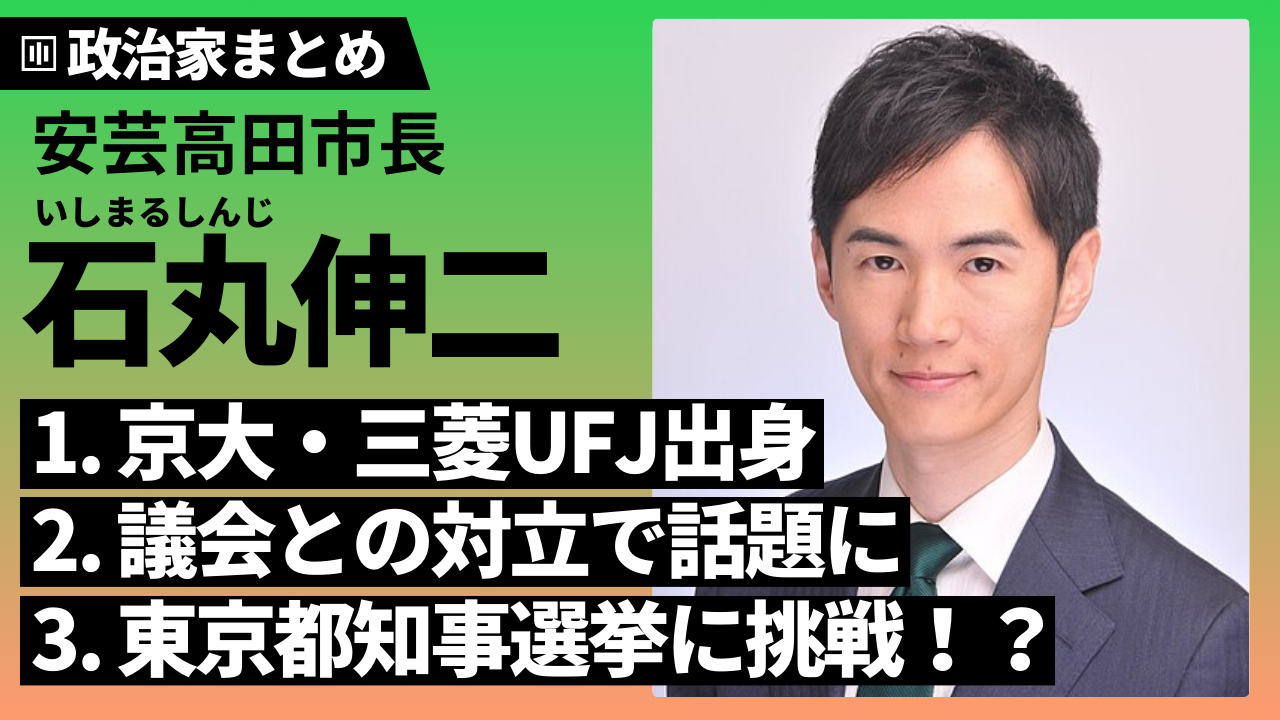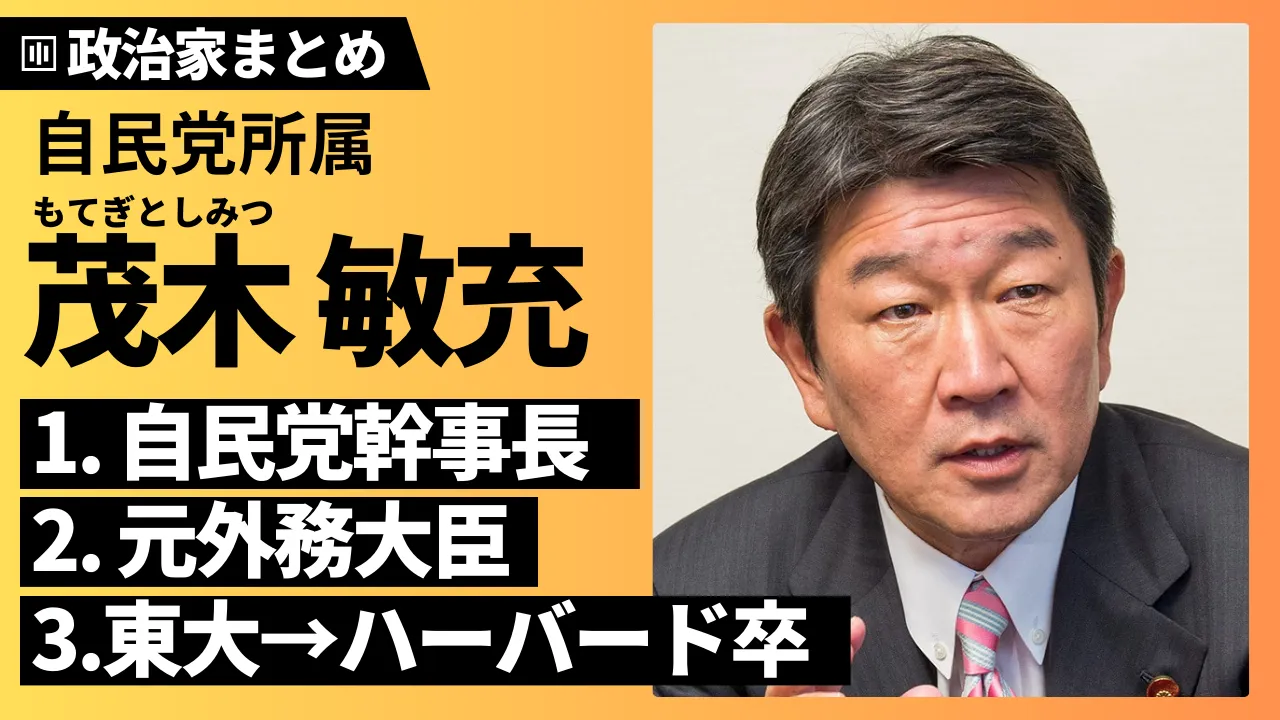【津田梅子】何をした人?新5000円札の顔!生い立ちや功績を解説
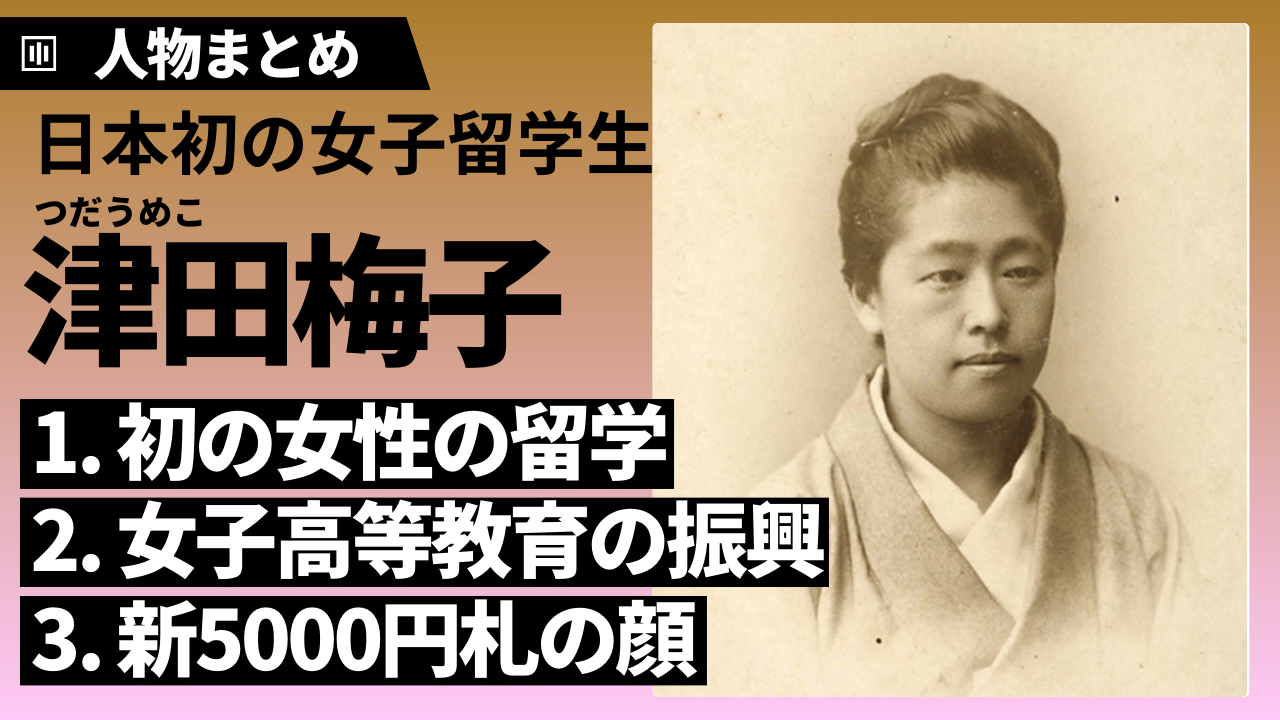
津田梅子とは?留学・女子教育など
2024年7月から発行される新5千円札の人物に選ばれた津田梅子。名前を知る人は多いと思いますが、あまり深堀されることの少ない人物でもあります。今回はそんな津田梅子について、功績や経歴、また彼女が参加した岩倉使節団や新札に関する情報まで、幅広く解説していきます。
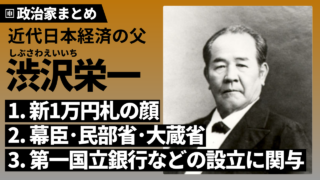
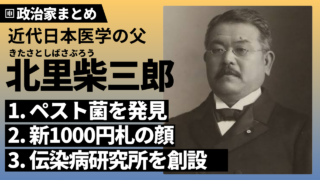
津田梅子は何をした人?
津田梅子は、明治から大正にかけて活躍した女子教育家です。日本初の女子留学生の1人でもあり、女子教育における先駆者であるとも評されます。女子英学塾(現津田塾大学)の創設者でもあります。また、欧米の学術雑誌に名前を載せた最初の日本人女性でもあります。
- 1864年:東京府の士族、津田仙と初子の次女として産まれる
- 1867年:津田仙が江戸幕府の通訳として、福沢諭吉、尺振八とともに渡米
- 1868年:明治新政府誕生
- 1871年:津田仙が梅子を岩倉使節団の随行留学生に応募
- 同年:岩倉使節団に随行し渡米(当時8歳)
- 1881年:開拓使より帰還命令がでるも、留学の延長を申請
- 1882年:10年以上に及ぶ留学から帰国
- 1883年:伊藤博文に雇われる
- 1885年:華族女学校の英語教員に就任
- 1888年:再び留学し、ブリンマー大学に入学
- 1891年:カエルの発生に関して顕著な研究成果をあげる
- 同年:指導者モーガン教授と共著で論文を執筆
- 1892年:再び帰国
- 1898年:女子高等師範学校の教授を兼任
- 1900年:女子英学塾を東京に開校
- 1908年:女子英学塾の生徒数が150名に到達
- 1917年:体調を崩し入院
- 1919年:塾長の職を停止
- 1928年:瑞宝章を授与
- 1929年:脳出血のため死去
梅子は頻繁に留学の時にお世話になったランマン夫妻と手紙のやり取りを重ねており、日本での就職に苦労しているときに、「アメリカに戻ったらどうか」という旨の手紙を受け取ったこともありました。
しかし梅子はこの手紙に対し、「私は開拓使から費用を援助してもらって留学したのですから、その御恩を返さなければなりません」と、この提案を断っています。
津田梅子の功績
ここからは、津田梅子の功績をいくつかご紹介します。
日本の女性の中で最初に留学に行く
第2代内閣総理大臣の黒田清隆が実現させた、開拓使による女子留学生のアメリカ派遣事業に、津田仙は娘の梅子を応募させました。梅子は無事に渡米に成功し。9ヶ月後に家族にあてて書いた「A little girl’s stories」と題する英文の絵日記は、現在でも津田塾大学の梅子資料室に保管されています。
官費女子留学生の待遇は「日本政府が旅費、学費、生活費を全面的に負担」「奨学金として毎年800ドルを支給」という破格のものでしたが、「10年間留学したことにより、婚期を逃してしまう」と危惧されたため、この募集に応じたのは5人の士族の娘のみでした。
女子高等教育のための教育機関を解説
1899年の「高等女学令・私立学校令」による法整備などで女子教育への機運が高まりました。梅子はこれを見て「自らの学校を開こう」と決意。アメリカの仲間たちの支援を受け、学校開設のための資金を入手することに成功します。
梅子は「華族女学校教授兼女子高等師範学校教授」という安定した立場を捨て、「女子英学塾」の設立願を東京府に提出します。1900年に梅子は現在の千代田区のある借家に開校。身分差別のない平等な教育を行いました。開校時の生徒はわずか10人でしたが、その8年後には生徒数が150人に達しています。
生物学の研究も積極的に行う
あまり知られていない梅子の功績として、生物学に対する顕著な貢献が挙げられます。梅子はカエルの卵に関する研究を熱心に行っており、ローズ学長による、ブリンマー大学理事会への1891年度の報告書には「ミス・ツダの蛙の卵の軸の定位に関する研究は、その優秀性のゆえに、特に言及しておかねばならない。」と特記されています。
この研究成果は、指導教官であるモーガン博士により、梅子とモーガン博士を共同執筆者とする論文「The Orientation of the Frog’s Egg」にまとめられ、イギリスの学術雑誌「Quarterly Journal of Microscopic Science, vol. 35.」に掲載されました。
梅子は日本人女性として初めて、欧米の学術雑誌に論文が掲載されたのです。
津田梅子が参加した「岩倉使節団」とは?
梅子が随行した「岩倉使節団」とは何なのでしょうか。岩倉使節団とは、1871年から1873年にかけて、世界12ヵ国に派遣された使節団の事です。岩倉具視を特命全権大使として、46人の使節、18人の随行員、43人の留学生などで構成されていました。表向きの目的は諸外国との友好関係の構築や文物の調査ですが、実は裏の目的も携えていました。それは不平等条約の改正のための交渉です。
近代的な法制度が整っていないことや、キリスト教禁教政策などを理由にこの試みは失敗しましたが、各国の元首に謁見し、明治政府の国家建設に大きな影響を与えたことから、日本の歴史上でも遣唐使に匹敵する重要性をもつ使節であると言われています。
新5,000円札はいつから発行されるのか?
2024年7月3日に、新たにお札が改刷されます。今回取り上げた津田梅子は、新5千円札の肖像画に採用されました。新1万円札については渋沢栄一が、新千円札については北里柴三郎が採用されました。
まとめ
日本における女子教育の基礎を築き上げ、日米間の懸け橋となった津田梅子。新札に関する話題の時に必ず出てくる人物ですので、この機会に覚えておきましょう。もし新5千円札を目にしたら、彼女に想いを馳せてみるのもいいかもしれません。
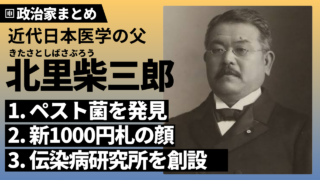
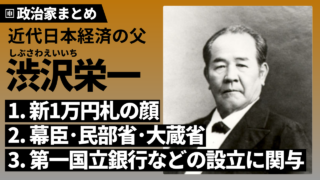
参考になるサイト・資料
- 山崎孝子|「津田梅子」|吉川弘文館
- 古川安|「津田梅子:科学への道、大学の夢|東京大学出版会
- 大庭みな子|「津田梅子」|朝日新聞出版
- 吉川利一|「津田梅子」|津田塾同窓会
- 亀田帛子|「津田梅子:一人の名教師の軌跡」|双文社出版
- 米欧亜回覧の会|「岩倉使節団とは」|http://www.iwakura-mission.gr.jp/shisetudan
- 国立印刷局|「2024年7月3日 お札が変わります」|https://www.npb.go.jp/ja/n_banknote/index.html