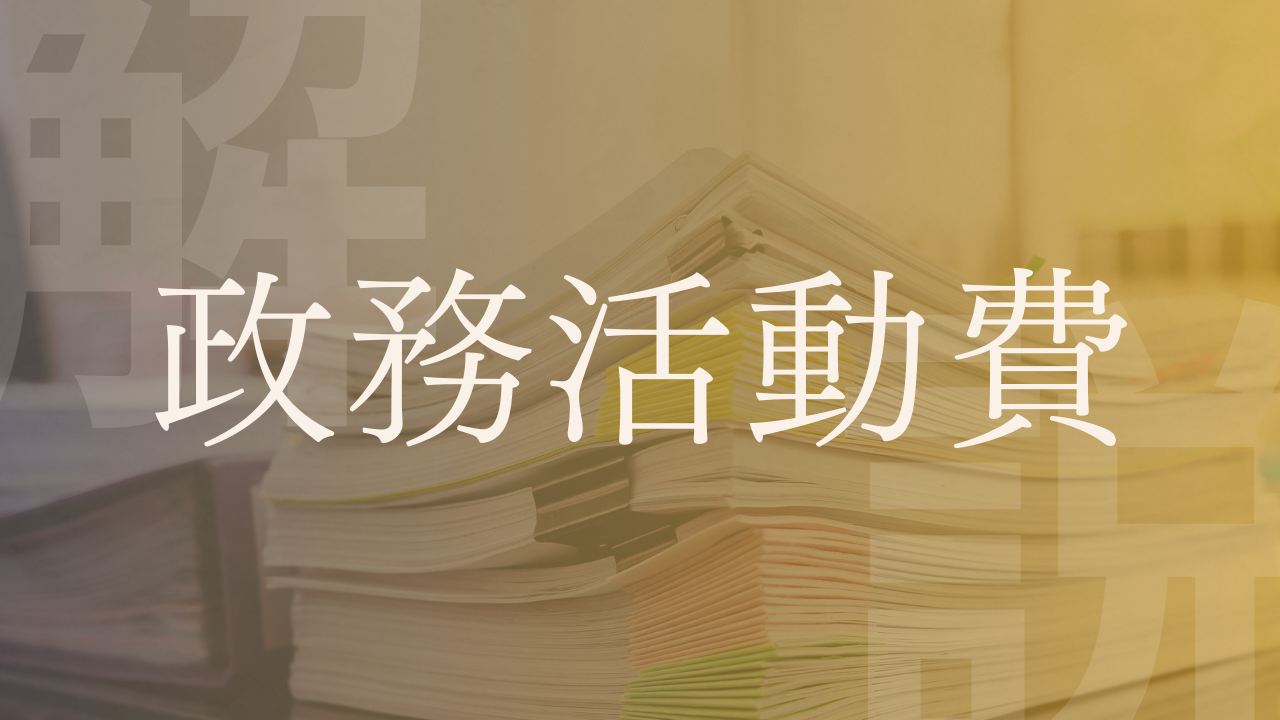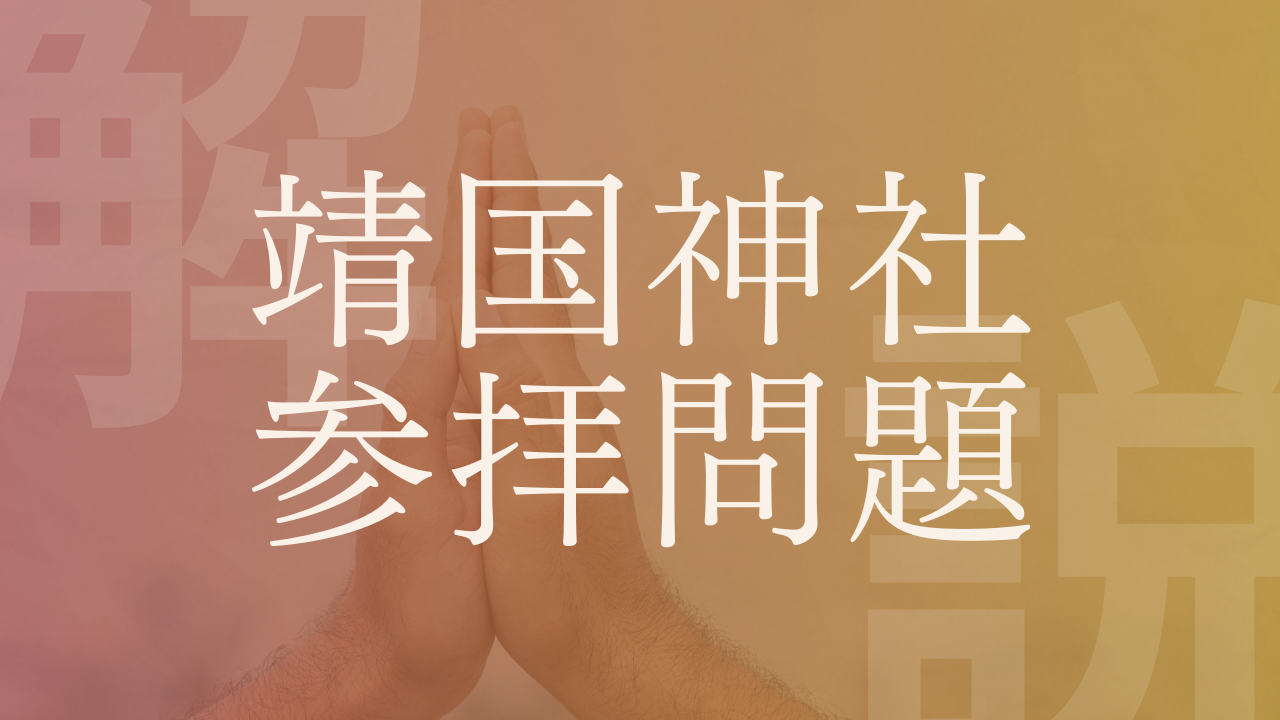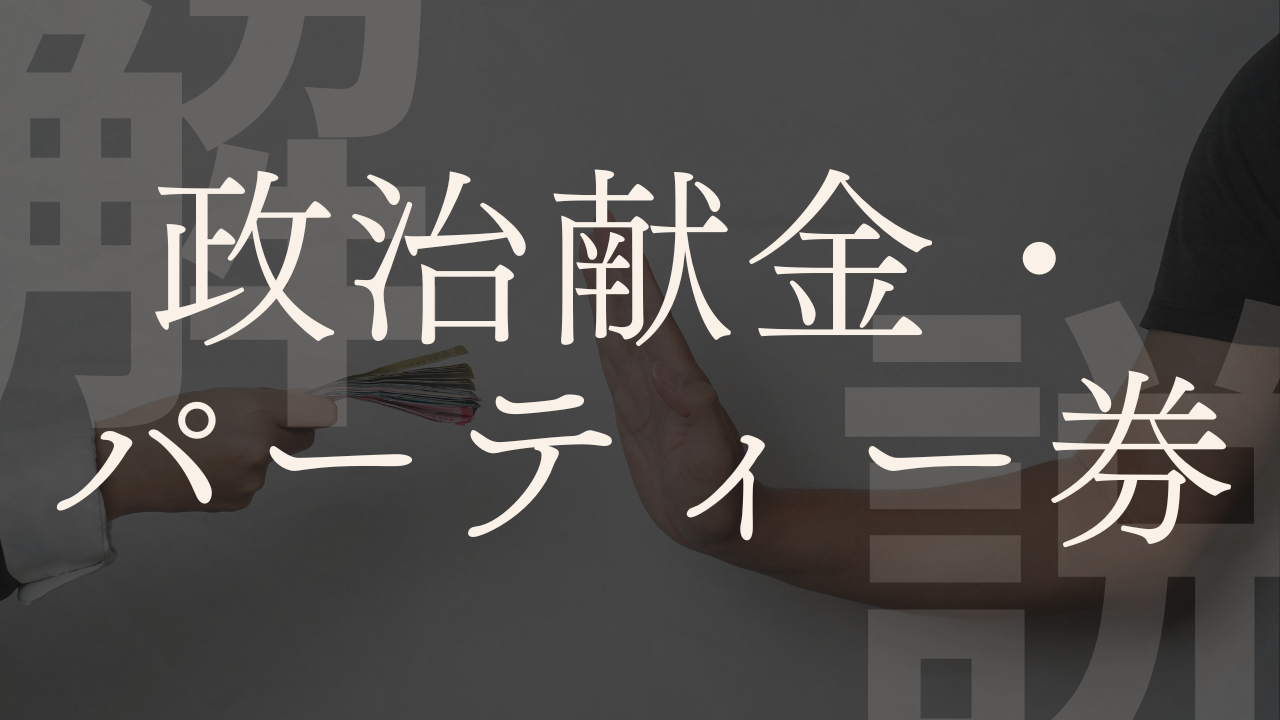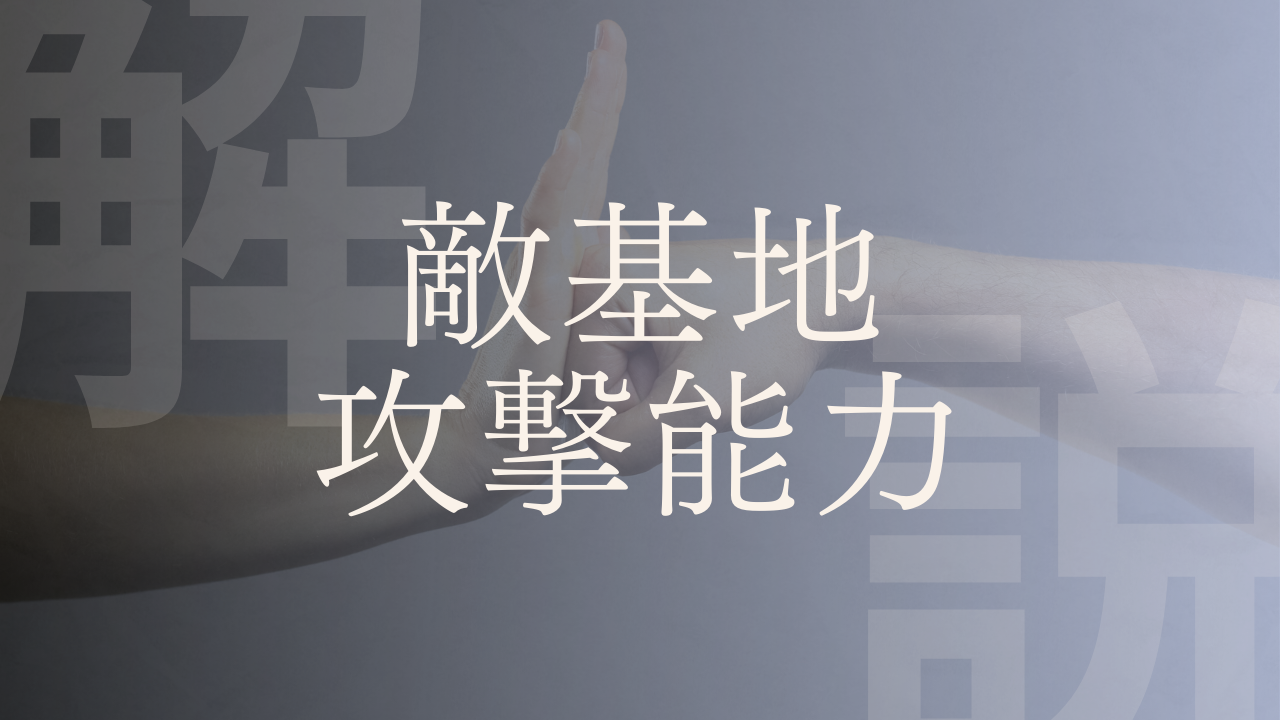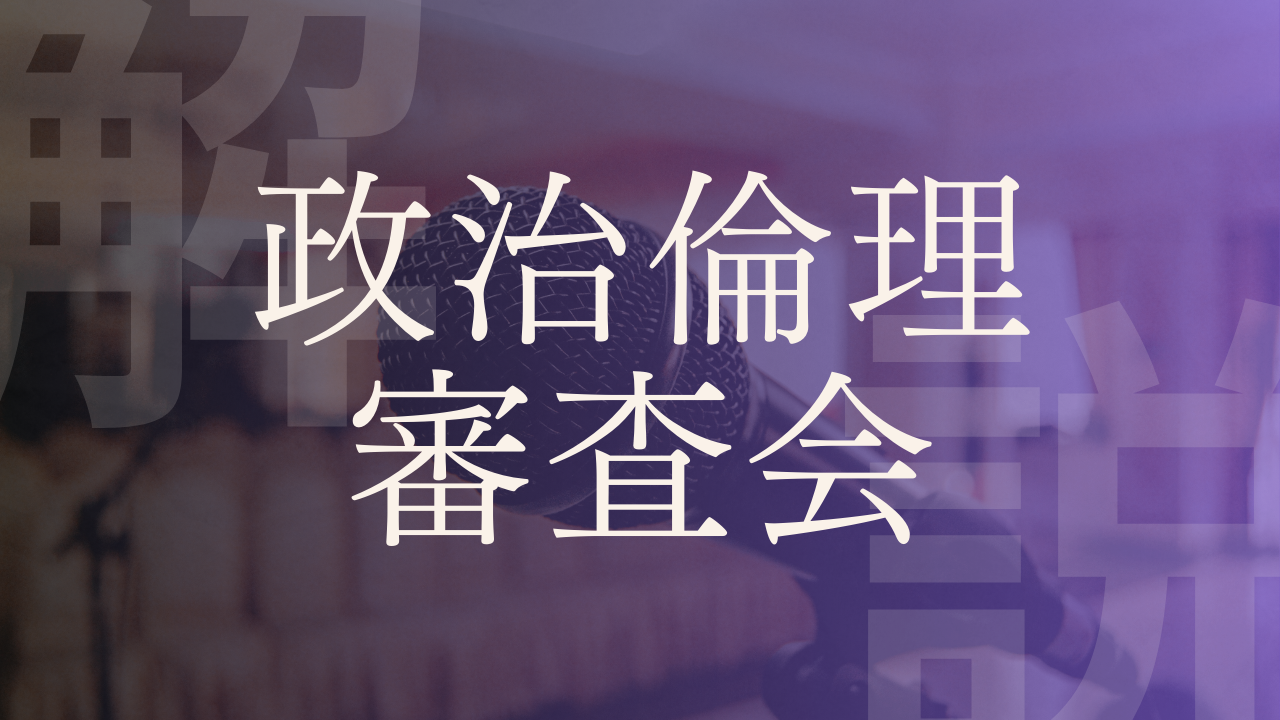【大阪都構想】目的・メリット・デメリットや住民投票の結果を解説!

政令指定都市から特別区へ。維新の会の改革は正しかったのか。
2度の住民投票を経て否決された大阪都構想。統治機構改革の旗印のもとに推し進められたその議論は、果たして正しかったのでしょうか。そして、どのような影響を与えたのか、大阪のことだから関係ないと感じる前に、まずは都構想の内容を知って考えてみましょう。
大阪都構想とは
大阪都構想とは、大阪市において特別区制度への移行を目指す構想のことです。現在の大阪市は、政令指定都市と位置づけられていますが、東京都のような特別区制度に移行することによって、行政運営上のメリットがあるとする考えに基づいています。
政令指定都市とは?
政令指定都市とは、地方自治法で「政令で指定する人口50万人以上の市」とされており、「指定都市」「政令市」「指定市」とも呼ばれています。
「大都市に関する特例」という規定により、一般の市では都道府県が担うような都市計画や健康・福祉に関する事務などの権限を特例的に市が担っています。
現在は、札幌市(北海道)、仙台市(宮城県)、さいたま市(埼玉県)、千葉市(千葉県)、川崎市(神奈川県)、横浜市(神奈川県)、相模原市(神奈川県)、新潟市(新潟県)、静岡市(静岡県)、浜松市(静岡県)、名古屋市(愛知県)、京都市(京都府)、大阪市(大阪府)、堺市(大阪府)、神戸市(兵庫県)、岡山市(岡山県)、広島市(広島県)、北九州市(福岡県)、福岡市(福岡県)、熊本市(熊本県)の20の市が政令指定都市に指定されております。全人口の2割ほどが政令指定都市に居住しています。
都道府県と政令指定都市の権限が被っていて2つの議会・2人の首長の意思決定が必要となり、都市計画等の広域事業が円滑に進まないといった指摘もあります。
そういったことから大阪都構想の議論が出てきました。
特別区とは?
現在は東京都のみで採用されている制度で、1947年に成立した地方自治法によって、「都の区は、これを特別区という。」と定められたことに由来しています。東京都内には、特別区が23区あります。
政令指定都市の中にも「区」がありますが、これは行政区とされ、特別区とは区別されています。特別区の場合は、東京都◯◯区と称されますが、行政区の場合は、◯◯県(府)◯◯市◯◯区と称され、特別区には選挙で選ばれた区長と議会があり自治体の機能を持っていますが、行政区の場合には選挙で選ばれた区長と議会はなく住民の利便性のために設けられた区画といった位置づけになります。
大阪都構想議論の加熱と1度目の住民投票
20世紀頃から、大阪市の権限を強める特別市を目指す動きや、大阪市を特別区に移行する案などがあり、議論があったものの、いずれも具体化することなくこれらの構想は消滅していました。
その中で、注目度が高まり、実現の具体性を帯びてきたのは、2008年に橋下徹大阪府知事が就任してからでした。橋下知事(当時)は、大阪維新の会を立ち上げ、大阪府全体を「大阪都」とし、大阪市・堺市の政令指定都市を解消する行政構想を発表しました。
当時の案では、大阪市を8区に、堺市を3区に、豊中、吹田、守口、八尾、松原、大東、門真、摂津、東大阪の9市をそれぞれ区にし、特別区として20区を新たに設置するとされていました。
2011年11月には、平松邦夫大阪市長(当時)の任期満了に伴う大阪市長選挙と、市長選挙に出馬を表明した橋下知事(当時)の辞職に伴う大阪府知事選挙が同時に行われました。府知事選・市長選が同時に行われるダブル選挙となりました。
結果は、大阪市長選挙では府知事から鞍替えした橋下徹が、大阪府知事選挙では府議会議員だった松井一郎が当選し、府知事・大阪市長ともに大阪都構想実現を目指す体制となります。
2012年(当時民主党政権・野田第2次改造内閣)には国政においても法整備が進み、大阪都構想への機運が急速に高まりました。2014年の出直し大阪市長選挙を経て、議論が進む中で、大阪市を5つの特別区に再編する案でまとまりました。
この案では、城東区・東成区・生野区・旭区・鶴見区を東区、北区・都島区・淀川区・東淀川区・福島区を北区、住之江区(南港東以西)・港区・此花区・大正区・西淀川区を湾岸区、西成区・中央区・西区・天王寺区・浪速区を中央区、住之江区(平林南・平林北以東)・阿倍野区・平野区・住吉区・東住吉区を南区の5つの特別区に再編するとされました。
2015年には、大阪府議会・大阪市議会で大阪維新の会・公明党(公明党は、住民投票の実施は了承、構想自体には反対の立場)の賛成により、住民投票を行うことが可決され、住民投票が5月17日投開票で行われました。
住民投票の結果、
- 反対:705,585票
- 賛成:694,844票
となり、いわゆる大阪都構想は否決されました。この結果を受けて、橋下徹大阪市長は任期満了を持って政界引退します。
2度目の住民投票へ
1度は廃案となったものの、1回目の住民投票の際の自民党らによる対案であった大阪戦略調整会議(通称:大阪会議)の破綻を踏まえ、松井一郎大阪府知事と橋下市長の後継者である吉村洋文大阪市長を中心に都構想議論が再燃します。
5区案から4区案に変更され、住民投票実現のための吉村市長が府知事に、松井知事が大阪市長に立候補する出直しクロス選挙を経て、2回目の住民投票が現実味を帯びます。
4区案では、東淀川区・淀川区・西淀川区・此花区・港区を淀川区に、北区・福島区・都島区・旭区・城東区・鶴見区・東成区を北区に、中央区・西区・浪速区・西成区・大正区・住吉区・住之江区を中央区に、天王寺区・阿倍野区・生野区・東住吉区・平野区を天王寺区へ再編するとしていました。
大阪府議会・大阪市議会では、大阪維新の会・公明党・自民党の一部の賛成により、2回目の住民投票が行われることが決まりました。
2度目の結果は、また否決されます。
- 反対:692,996票
- 支持:675829票
大阪都構想の意義・効果
副首都推進局が出している特別区制度(いわゆる大阪都構想)の意義・効果では、以下の三つが主に挙げられています。
二重行政の解消
大阪府・大阪市の連携不足によって、両方で同じような業務を行っていることを整理し直して、効率化が図れるとされています。
広域行政一元化
広域行政を大阪府に一元化することで、意思決定を1人の首長、ひとつの議会で行うことができるようになり、スムーズな意思決定をすることが出来るようになるとしています。
住民サービスの拡充
大きすぎた大阪市の範囲を4つの基礎自治体(特別区)に分けることによって、それぞれの首長とそれぞれの議会が地域事情に合わせた住民サービスを行うことができるようになるとしています。
大阪都構想の反対意見
ここからは大阪都構想の主な反対意見についてとりあげていきます。
特別区となる事によって、大阪市域内の権限・財源が損なわれる
政令指定都市としての権限・財源を損ない、大阪府へと財源と権限が移譲されることによって、市域内の利益が損なわれるといった意見もあります。
特別区制度への移行コストがかかる
再編にかかる費用や人的コストがデメリットとして指摘されています。また、基礎自治体の役所が1つから4つに増えることによって、人件費が増加したりといった見方もあります。
都構想実現せずとも、二重行政の解消がされている
10年以上にわたり、橋下市長・松井知事、吉村市長・松井知事、松井市長・吉村知事といった形で同じ政党出身の知事・市長の体制が続いたことにより、制度的な改変をせずとも、二重行政の解消が行えたという意見もあります。そのため、制度的な変更を必要としないと考えた住民もいました。
説明が不十分
制度説明がしっかりとされておらず、よく分からないから反対といった声もありました。
まとめ
大阪府・市の大胆な再編案である大阪都構想は、賛成・反対問わず多くの地域住民の関心を寄せました。住民投票といった手続きを経て、市民の政治への関心は高まったといえます。そんな大阪都構想を知ることで、なぜここまで大阪での政治の関心度が高いのかを知ることが出来るでしょう。
参考になるサイト
- 指定都市市長会|指定都市とは|https://www.siteitosi.jp/about/designated.html
- 特別区協議会|特別区とは|https://www.tokyo-23city.or.jp/chosa/tokubetsuku/whats.html
- 日本経済新聞|大阪都構想の住民投票告示 5月17日投開票|https://www.nikkei.com/article/DGXLASHC25H8Q_X20C15A4000000/
- 大阪市|平成27年5月17日 執行 大阪市における特別区の設置についての投票における投票状況 確定|https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu240/sokuhoukekka/tohyo_data_10_h27.html
- 大阪市|令和2年11月1日 執行 大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票における投票状況 確定|https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu240/sokuhoukekka/tohyo_data_10_r21101.html
- Business Journal|東京23区、「区」の廃止表明で「市」への脱却目指す…東京都、財源と権限を収奪し弊害|https://biz-journal.jp/2019/04/post_27564.html
- 毎日新聞|初期費最低300億円台 住民投票時から半減|https://mainichi.jp/articles/20171109/k00/00e/010/276000c
- 週プレNEWS|大阪都構想にホリエモン「反対派が多数になった理由は、維新の会が府と市の行政を握ったことが大きいと思う」|https://wpb.shueisha.co.jp/news/politics/2020/11/28/112514/