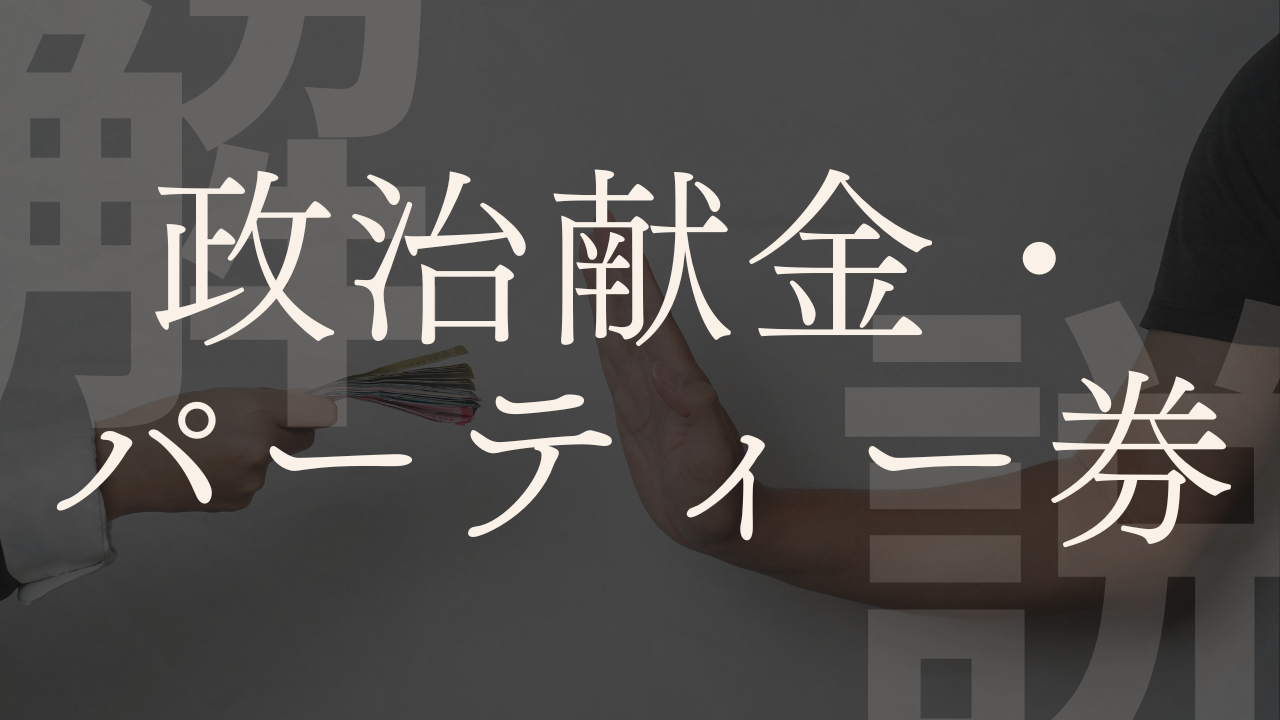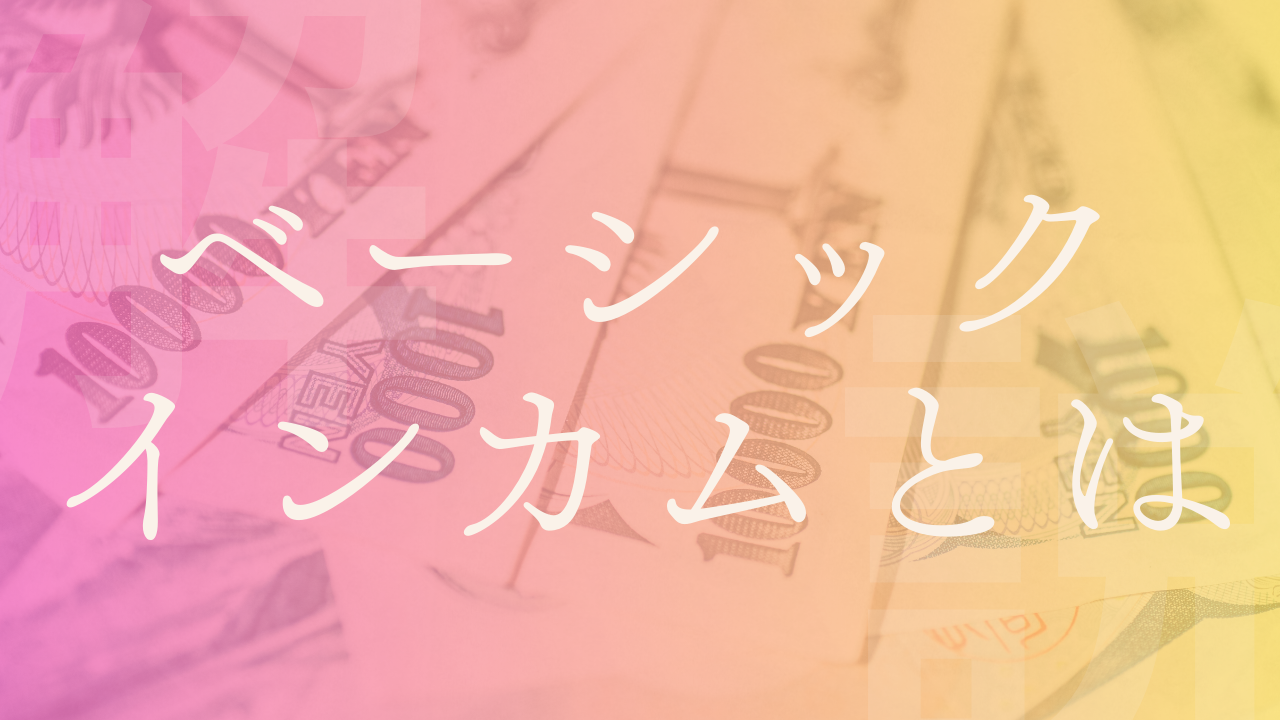【東日本大震災】津波・原発事故・多くの教訓を残した大災害

【解説】忘れてはならない東日本大震災の記憶
東日本大震災は2011年3月11日に発生した大規模な地震です。東北地方の海岸線を中心に大津波被害が襲い、さらに福島第一原子力発電所が事故を起こすなど、大きな被害をもたらしました。
関連死を含めて2万2212人の死者・行方不明者が犠牲となりました。広範囲に渡る被害を生み出した地震の概要をふりかえってみましょう。

大きな被害にあった東北地方の太平洋沿岸
東日本大震災で大きな被害を受けたのは東北地方の太平洋沿岸です。宮城県北部の栗原市では最大震度である震度7を記録しました。さらに宮城県の他の地域や岩手県、福島県、茨城県、栃木県一部地域でも震度6強〜6弱を記録し、建物の倒壊や火災などの被害をもたらしました。
大きな被害をもたらす原因となったのが、揺れの後に到達した大津波です。10メートル近い大津波が海岸線に到達し、建物や人が流されました。岩手県の海岸線は、これまでにも地震による津波被害を受けており防潮堤が建設されていましたが、その高さを超える大津波が押し寄せました。犠牲者のうち9割強の死因は、津波に流されたことによる「溺死」でした。年齢で見ると、逃げ遅れた60歳以上のお年寄りが多く含まれています。
大きな教訓を残した原発事故
東日本大震災では福島県双葉郡大熊町と双葉町にあった福島第一原子力発電所で重大な事故が発生しました。地震により外部電源が失われ、さらに用意されていた非常用のディーゼル発電を行う電源も津波によって流されてしまい、全電源が喪失する状態に陥ります。
原子力発電は、原子炉の中心の炉心にある核燃料が核分裂を起こすことで生じる熱でお湯を沸かし、機械を動かし発電を行う仕組みです。核燃料には冷却が必須なのですが、それが不可能となってしまったのです。そのため炉心の燃料が溶け出し、放射性物質が外に拡散するメルトダウン事故を起こしました。この事故は国際原子力機関(IAEA)により、1986年に旧ソ連で起こったチェルノブイリ原発爆発事故クラスに相当する、最悪レベルの7と判断されています。
原発の周辺地域では現在も高い放射線量が存在しているため、居住の制限のある「帰宅困難地域」となっています。震災後には、事故が起きた場合、大きな被害をもたらす原子力発電所に反対する社会運動も巻き起こりました。多くの教訓を残した事故だと言えます。
首都圏では帰宅困難民があふれる
東日本大震災は、東北ばかりではなく関東地方にも大きな被害をもたらしました。首都である東京でも震度5強を観測しました。鉄道が運休したため、学校や会社から帰れない多くの帰宅困難者を生み出しました。このほか、埋立地の多い千葉県浦安市では強い揺れによる液状化現象が起こり、太平洋沿いにある同県旭市でも津波被害を受け犠牲者が出ています。
さらに福島の原発事故を受け、電力供給量が足りなくなるおそれがあるとして、東京電力管内では一部時間を停電する「計画停電(輪番停電)」も行われました。
復興はどこまで進んだ? 現在も続く影響
2024年で震災から13年が経ちました。復興はどこまで進んだのでしょうか。復興庁のとりまとめた資料「復興の現状と今後の取組」によれば、高台移転による住宅造成、災害公営住宅の整備、復興道路・復興支援道路の全線開通、被災した鉄道が全線開通などの復興を成し遂げています。さらに震災の記憶や教訓を後世へ継承するための追悼の施設の建設が進められています。
一方、2023年11月時点で避難者は3万人、応急仮設住宅の入居者は602戸(958人)あります。かつてよりは少なくなったとはいえ、いまだに避難や仮設住宅の入居を余儀なくされている人もいることは忘れてはいけません。
福島第一原子力発電所も廃炉へ向けて作業が進められていますが、ALPS(多核種除去設備)処理水の処分方法として海洋放出が行われ、賛否を巻き起こしています。
まとめ
東日本大震災は2011年3月11日に東北地方を中心に東日本一帯に大きな被害をもたらした大地震です。2万人以上の犠牲者・行方不明者を出しました。
福島第一原子力発電所の事故とあわせて、災害に対してどのような対策を取ってゆくべきか、大きな教訓と課題を残しました。復興は進んでいますが、いまだに避難や仮設住宅への入居を余儀なくされている人もいます。



参考になるサイト
- 内閣府防災情報のページ「東日本大震災」https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h23/63/special_01.html
- 社会実情データ図録「東日本大震災と阪神・淡路大サイン祭の男女別年齢別死者数」https://honkawa2.sakura.ne.jp/4363f.html
- 復興庁「FAQ 福島の安全性について」https://fukushima-updates.reconstruction.go.jp/faq/fk_040.html
- 復興庁「復興の現状と今後の取組」https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/202312_genjoutorikumi.pdf