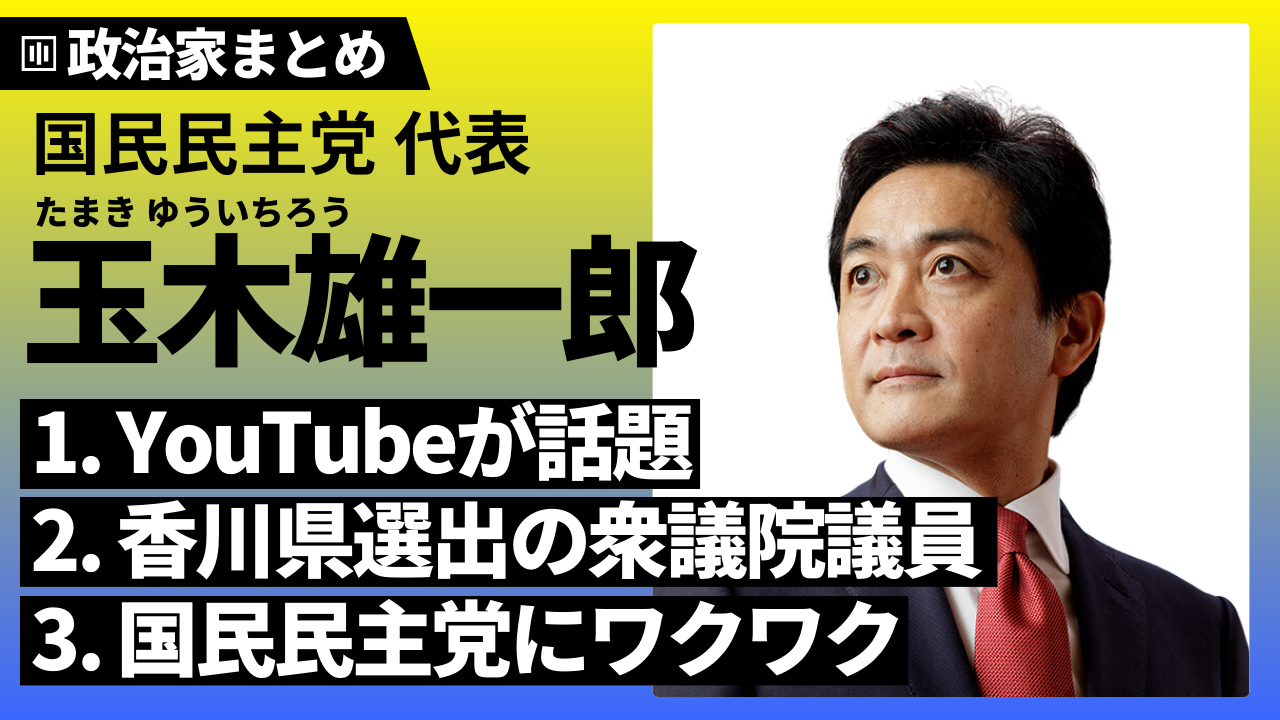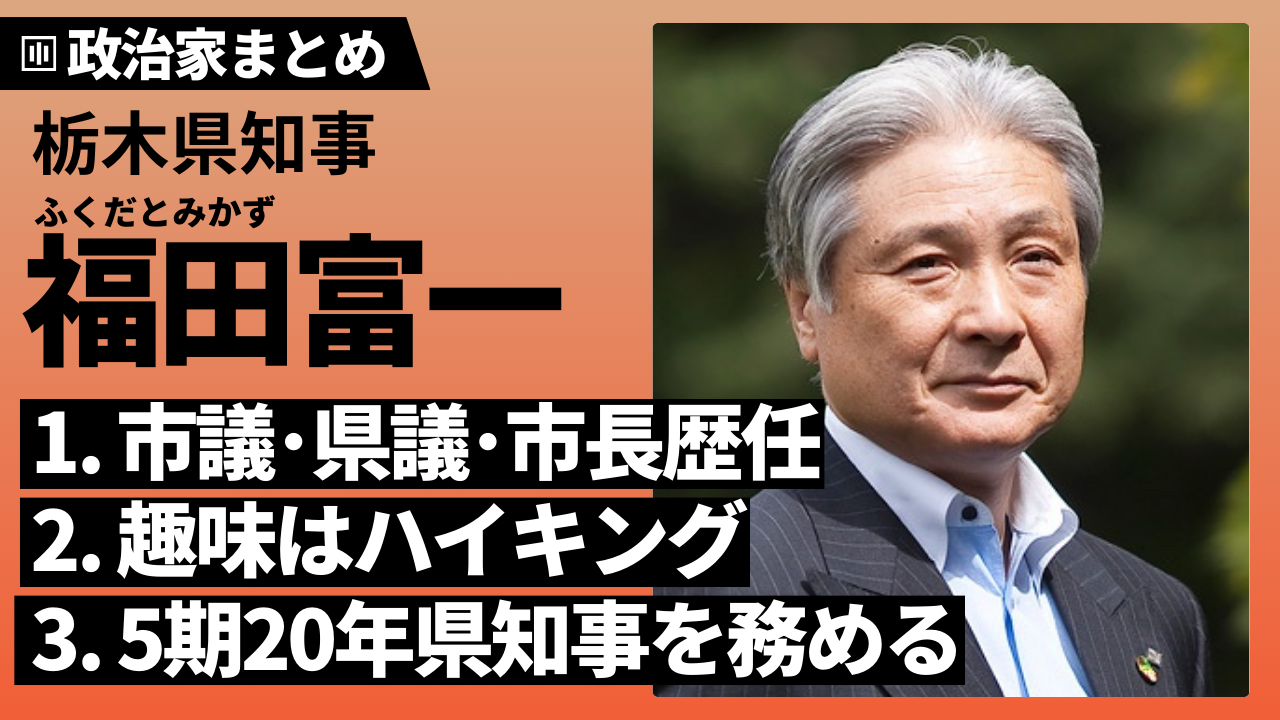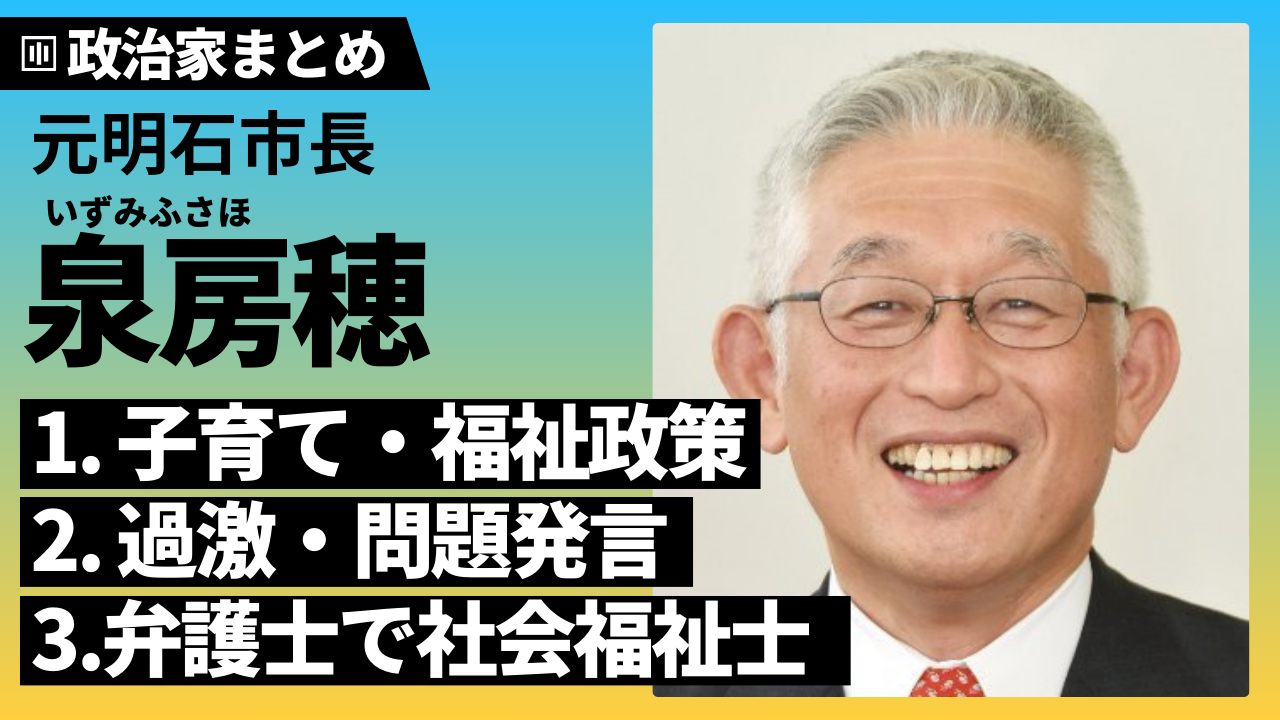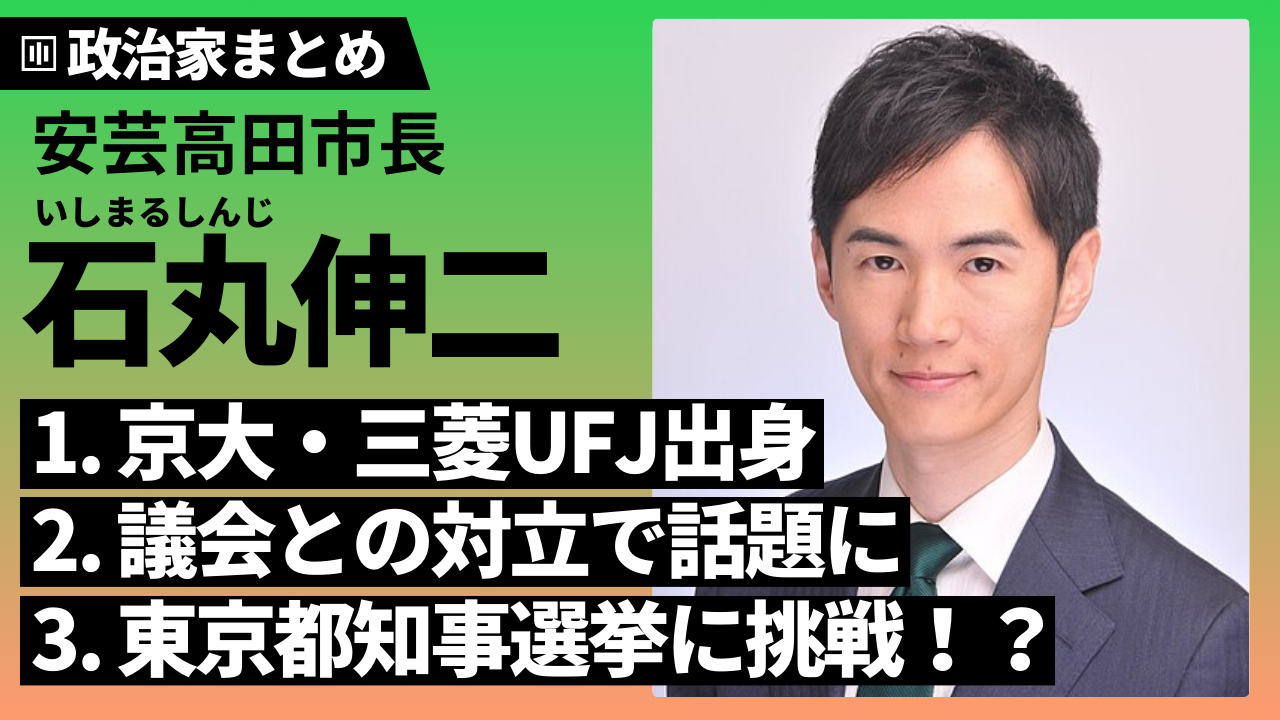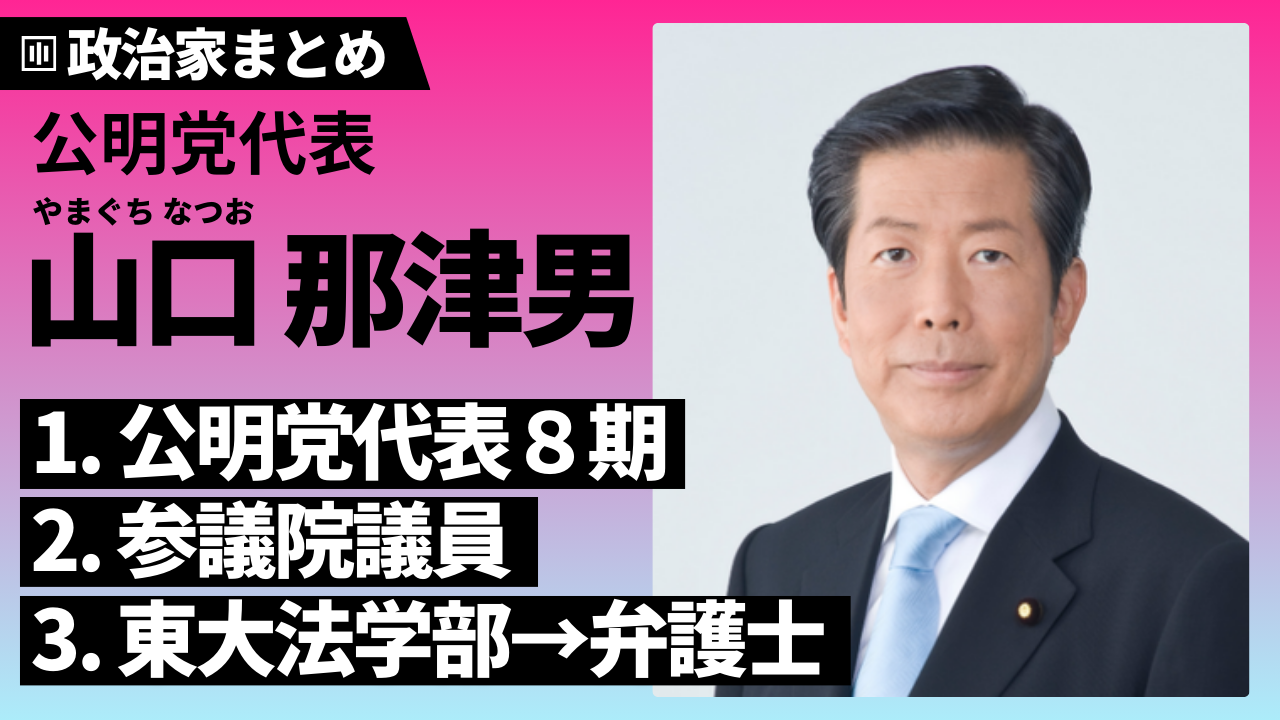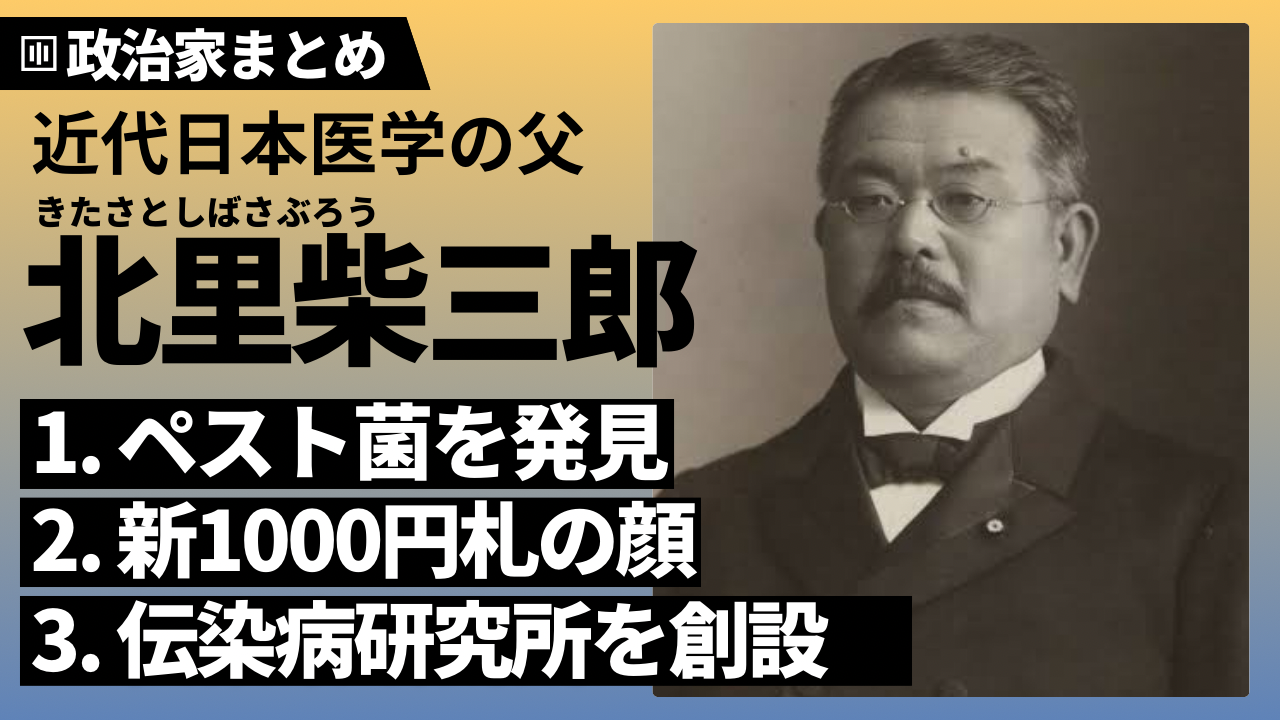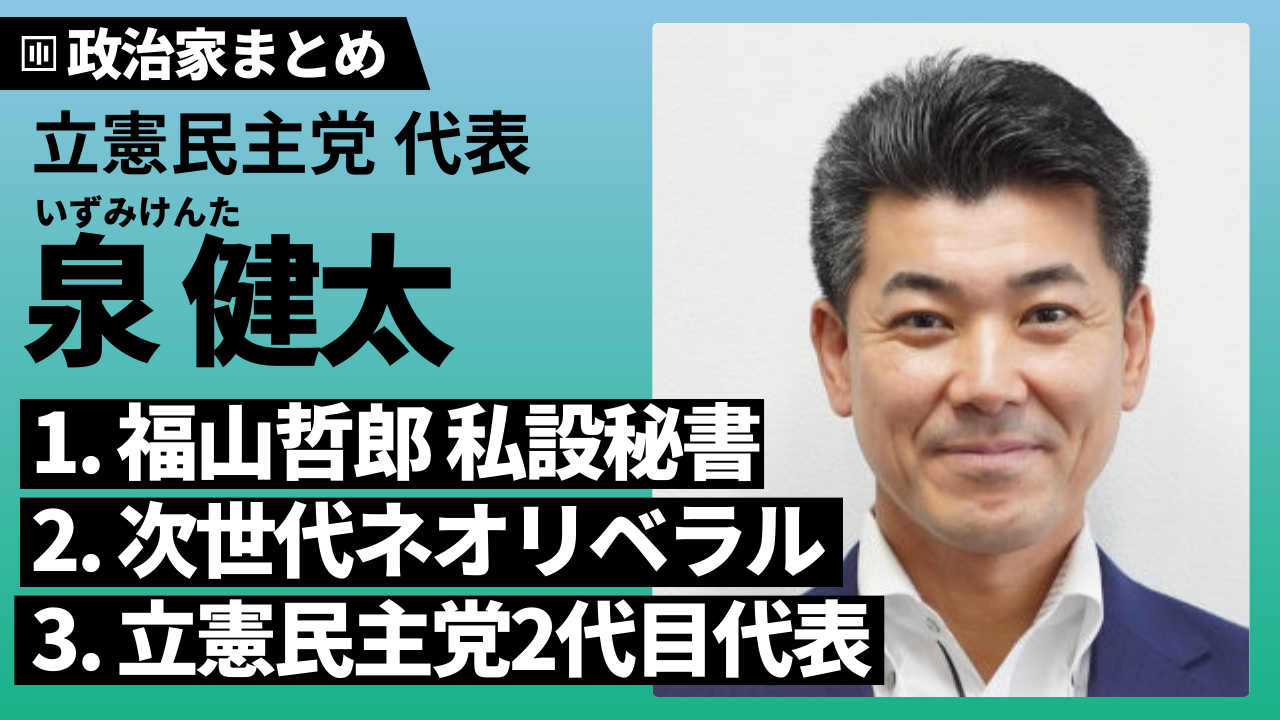【与党・石破政権】自由民主党とは?長年政権を担ってきた政党を知ろう

戦後最強の政党!?「自由民主党」徹底解剖
日本において、1955年以降ほとんどの時期で政権を担当してきた自由民主党(以下自民党)。この間、ほとんどの総理大臣が自民党所属でした。日本の政治に多くの影響を与えている自民党のことを知る事は政治を知ることにおいて必要不可欠といえるでしょう。今回はそんな自民党の特徴や歴史的背景についてまとめていきます。
自民党・概要
- 総裁:石破茂
- 副総裁:菅義偉
- 幹事長:森山裕
- 設立:1955年
- 略称・通称:「自民」、「自民党」、1字表記の場合は「自」
- 国会議員数:309人(衆議院:195人、参議院:114人、2025年4月現在 参照:自民党)
- 党員数:約103万人(2024年 現在 参照:NHK)
設立背景
第二次世界大戦後の混乱期において、政党の乱立や政治の分裂が続き、保守派の政治家を中心に政治の安定や再建を図ることが目指されました。そこで、自由党と日本民主党が合流し、自由民主党が結成されました。
4年間左派と右派に分裂していた社会党が再統一したことに危機感を覚えた財界の圧力もあり、吉田茂と鳩山一郎の抗争は終わり、保守合同が実現しました。
政権与党として
自民党は結党当初から政権与党として存在し、以降1993年に衆議院議員選挙で過半数を割るまでの38年間ほとんどの時期で単独で政権を担当することになります。(例外として、自民党から分裂した新自由クラブと1983年に連立政権を形成しています。)政権与党の自民党と野党第一党の社会党が国会で対立する政治体制を55年体制と呼びます。
1992年(平成4年)に起きた東京佐川急便事件により、国民の政治不信が増大し、自民党単独の長期連続政権による金権体質がたびたび指摘されるようになりました。1993年の衆議院総選挙において自民党が過半数を割り、自民党を離党した日本新党、新党さきがけ、細川護煕率いる日本新党が躍進し、日本新党党首の細川護煕を首相とする非自民・非共産連立政権が樹立します。
連立政権は、細川政権、新生党の羽田孜政権と続きましたが、いずれも長続きせず、連立政権内での足並みの乱れが顕著になっていきます。そこで自民党は、社会党の村山富市委員長を首相に推す奇策で、1994年(平成6年)社会党、さきがけとの連立政権(自社さ政権)として与党に復帰しました。
旧非自民連立政権側は新進党に集約されていましたが、自民党側の積極的な引き抜きにより、1997年(平成9年)に過半数の議席数を回復し、年末には新進党が解党し、1998年(平成10年)には社会党、さきがけとの連立を解消して自民党単独政権へと戻りました。
1999年には小沢一郎率いる自由党との自自連立、公明党を含めた自自公連立内閣を形成、2000年には自由党が政権を離脱し、自由党から分裂した保守党との自公保連立政権を組みながら、政権を維持していきます。この頃から、現在にも続く公明党との協力関係がはじまります。2003年には、自民党が保守党を吸収し、自公連立政権となります。
2009年の衆議院議員選挙では、鳩山由紀夫代表率いる民主党が圧勝し、社会民主党と日本新党との連立政権である鳩山由紀夫内閣が成立しました。鳩山総理に続き、菅直人内閣、野田佳彦内閣が成立しましたが、政策実現への課題や震災及び原発事故の影響もあり、政権の支持率や信頼度が落ち、自民党は2012年に再び政権をとることになりました。
以降、現在にいたるまで自民党は公明党と連立を組みながら、政権与党として安倍晋三内閣、菅義偉内閣、岸田文雄内閣、石破茂内閣と続いています。
党内派閥の影響
2023年末からの政治資金問題により、注目が集まった自民党内の派閥は、どのようなものなのでしょうか。自民党は永らく党執行部の権限が弱く、ベテラン政治家が派閥を結成して、その派閥同士の駆け引きによって政治が行われることが常態化していました。これは一つの選挙区の中で複数人当選者がいる中選挙区制度が採用されていた影響が大きいです。同じ選挙区の同僚議員は、同じ党でありながら当選を競い合うライバルの関係にいました。立候補者は党本部の支援を独占することができず、大物政治家の派閥に所属することによって、選挙で派閥からの支援を受けるようになりました。
中選挙区制から、小選挙区比例代表並立制に移行したことにより、候補者選定等において党本部の存在が高まりました。その中で総裁の座を争うための集団という意味が薄れながらも、現在までポスト獲得や選挙において互助組織の側面を持ちつつ、影響力を持ち続けています。
派閥政治は自民党内に多様性をもたらし、自民党は幾多の政治変動にも対応出来る支持基盤を持った政党として長年政権を維持しています。一方で、資金の不足しがちな若手議員や中堅議員が、党執行部の意向よりも派閥の領袖の意向に左右されることも多く、長老政治、密室政治、金権政治の温床となるという指摘もあります。
自民党の主張
自由民主党の政策には、派閥や各個人において幅があるものの、自由主義経済を土台とする資本主義体制の維持、自由主義国との協調や日米友好、憲法改正等を目指しています。
ほとんどの総理大臣が自民党所属なので、細かい政策に関しては、その時代の政権が何をしたかに着目していくことが重要といえます。
主な政治家
麻生太郎
安倍晋三
岸田文雄
まとめ
自由民主党は、戦後ほとんどの期間を与党として政権を担ってきました。
自由民主党の歴史を知ることで、現状の政治について理解が深まると思います。
今後、どのような政治家が自由民主党から誕生して、どのように政局を動かしていくのか、注目していきましょう。