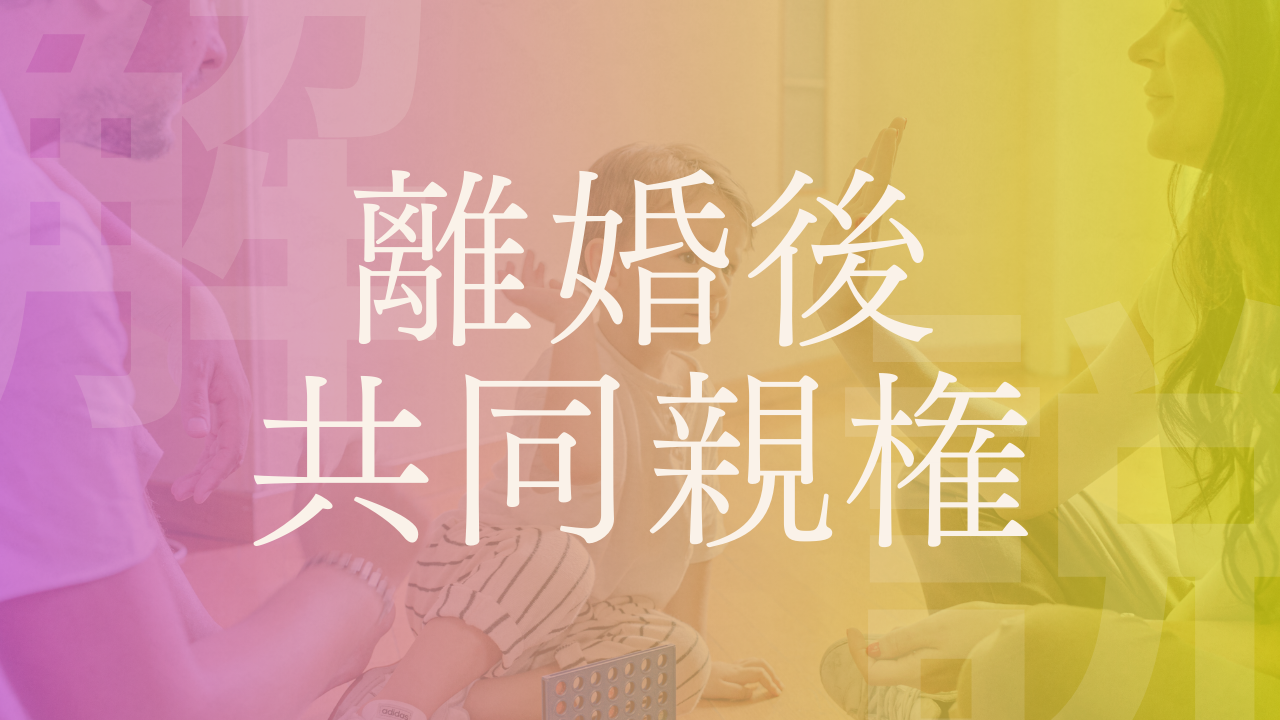【特定外来生物】導入経路や被害・対策は?ジャンボタニシの実例についても解説!

特定外来生物とは?マングース・タイワンリスなどへの対策は?
特定外来生物は言葉くらいは聞いたことがある人が多いでしょう。実際に、どういった生物が特定外来物となるのか。どのように指定されるのか。あらためて考えてみましょう。
特定外来生物とは?
特定外来生物の範囲は多岐にわたります。まずはその種類や法的根拠を確認してゆきましょう。
特定外来生物の定義
特定外来生物とは、環境省の定義によれば「外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるもの」とされています。種類としては哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類、甲殻類、クモ・サソリ類、軟体動物等、植物と多岐にわたります。新たに特定外来物に追加されるものもあれば、除外されるものもあり、入れ替わりがあります。
法的根拠
特定外来物は外来生物法によって規制がなされています。外来生物法の目的は「特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資すること」と定められています。特定外来物に指定されたものは「飼育、栽培、保管、運搬、輸入」といった広い領域に渡って規制がなされます。さらに特定外来物は生きているものに限られています。個体ばかりでなく、卵、種子、器官なども含まれます。生きていないもの、たとえば昆虫標本などは該当しません。
目的
外来生物法が導入された目的は、特定外来物は繁殖が想定されるためです。特定外来物が繁殖してしまうと、もともと日本にあった自然の生態系を壊してしまうおそれがあります。さらに人の生命や身体へ危害、影響が生ずる可能性もあります。さらに特定外来物は農林水産業へも大きな被害を生じさせる可能性があります。生態系への影響、人の身体・生命への影響、農林水産業への影響を想定し、その被害を防止する目的が特定外来法です。
意図的導入と非意図的導入
特定外来種には意図的導入と非意図的導入があります。この違いを説明します。
意図的導入
意図的導入とは、その生物をある目的を持って導入するケースです。毛皮の利用のために家畜として輸入されたヌートリアや、ウシガエルのエサとして輸入されたアメリカザリガニ、試験動物として輸入された魚のブルーギルなどが該当します。植物でも、観賞用のほかの目的で輸入されたセイタカアワダチソウ、食用、飼料として輸入されたセイヨウタンポポなどが該当します。
非意図的導入
非意図的導入は、明確な目的がなかったものの日本へ入り込んでしまったものを指します。海外との船舶との往来にあたり船に住み着いていたドブネズミが日本に上陸して定着してしまった例などがあります。このほか動物の中にいる寄生虫なども特定外来生物の非意図的導入に該当します。
もたらす被害とその実例
特定外来生物は実際にどのような被害をもたらしているのでしょうか。
ジャンボタニシの被害例
よく知られているものとしてジャンボタニシの例があります。ジャンボタニシは正式名称をスクミリンゴガイと言います。ジャンボタニシはお米を作るための稲作に影響を与えます。田植え直後から2~3週間後までの柔らかい稲の苗を食べてしまうため、大きな被害をもたらします。ピンク色の卵が特徴的であり、産卵頻度は3~4日に1度、約10日で孵化するため高い繁殖力を持っています。
重症化するケースもあるセアカゴケグモ
日本各地で繁殖が確認されているセアカゴケグモは毒グモです。おとなしい性格であるものの、素手で掴もうとする場合、噛まれるケースがあります。強い毒性を持つため、痛み発汗発熱などの全身の症状が出る場合や、噛まれた箇所の皮膚の壊死が起こる可能性もあるので注意が必要です。
現行行われている対策
特定外来生物の対策は、繁殖のスピードに駆除が追いついておらず、いわゆる「いたちごっこ」の状態が続いているのが現状です。主な対策を取り上げます。
沖縄、奄美で行われているマングース駆除
沖縄と奄美地方ではマングースの繁殖が深刻な問題となっています。マングースは1910年にハブ駆除などを目的として、現在のバラングラディシュから輸入されました。当初の目的であるハブの天敵とはならずに、奄美の現地に生息する希少種であるアマミノクロウサギやアマミイシカワガエルを捕食するようになってしまいました。沖縄でもオキナワキノボリトカゲやハナサキガエルなどが被害に遭っています。そのため、ワナなどを用いて完全駆除を目指しています。
神奈川県などでのタイワンリス増殖
タイワンリスはもともとペットとして輸入されたものが、放棄、逸出し野生化し大きな被害をもたらしています。農作物が荒らされるほか、材木の樹木をかじるなどの被害が出ています。これまでは神奈川県、静岡県など6県での定着が確認されており、近年は分布域を広げています。神奈川県の三浦半島では寺社の建物が被害に遭っているほか、電線がかじられるなど人間の生活にも影響をおよぼす被害が出ています。神奈川県鎌倉市では捕獲器の貸出が行われていますが、より踏み込んだ対策である個体の捕獲に対する報奨金制度の制定なども検討されています。
まとめ
特定外来生物は、日本の外から流入した生物のうち、生態系への影響、人間の生命・身体への影響、農林水産業へ影響があり、法律で規制された生物を指します。ペットや食料などの用途で輸入された意図的導入と、船の荷物などに付いてきた非意図的導入があります。駆除などの対策が行われていますが、繁殖力が強い生物も多く、対策が追いついていないのが現状です。
参考になるサイト
- 環境省|特定外来生物|https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html
- 環境省|日本の外来種対策|https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/outline.html
- 環境省|特定外来生物とは何か?|https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/manyuaru/old_manual/manual_tokutei_gairai_old/data1.pdf
- 小田原市|スクリミンゴガイ(ジャンボタニシ)の対策について|https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/industry/agricult/for-producer/p23460.html
- 東京都|気をつけて! 危険な外来生物|https://gairaisyu.metro.tokyo.lg.jp/species/damage.html
- 環境省|奄美保護センター|https://kyushu.env.go.jp/okinawa/awcc/mongoose.html
- 環境省|特定外来生物の解説|https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/L-ho-07.html