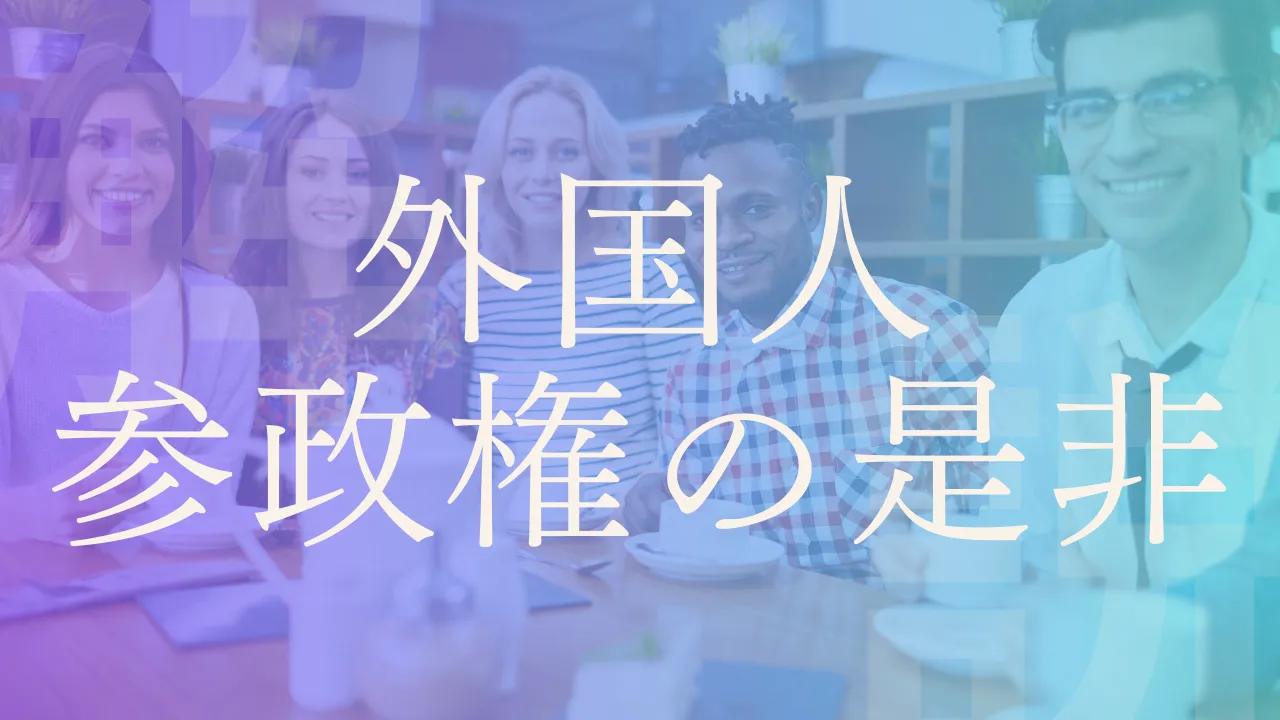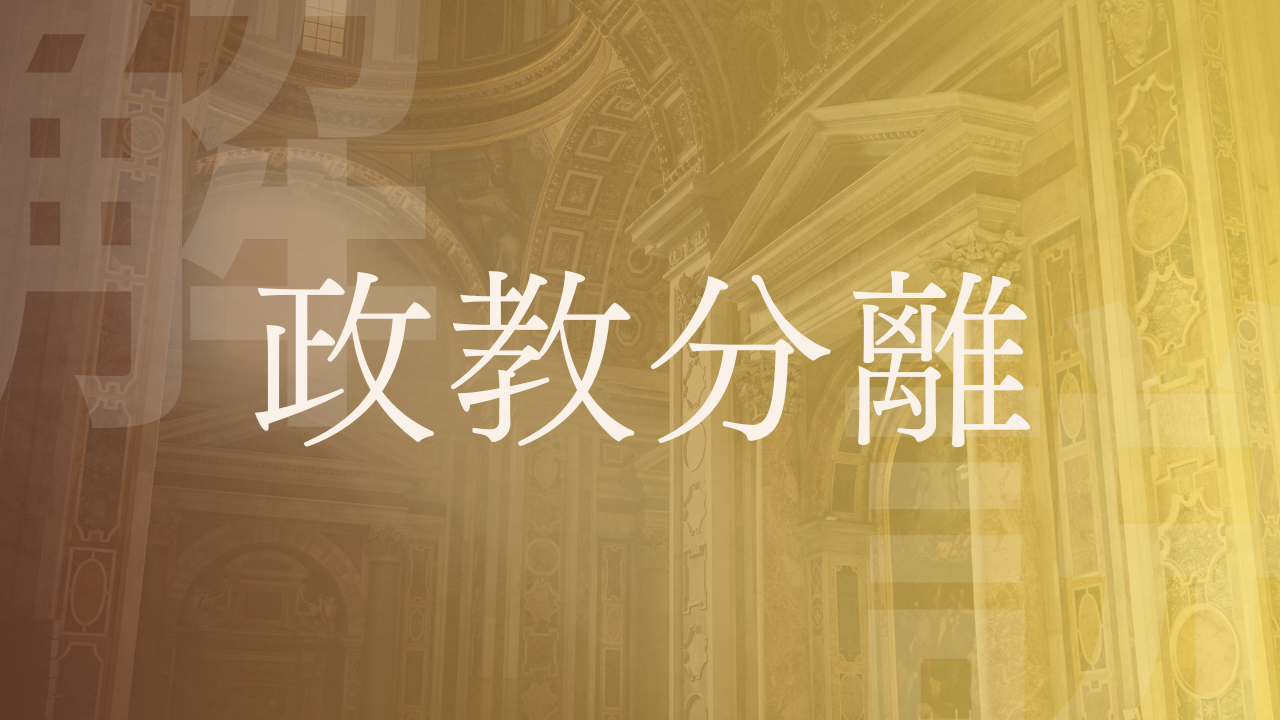日本にはどんな省庁があるの?公務員の役割についても!官公庁一覧・組織図

【官公庁・省庁まとめ】行政の仕組み・中央省庁を徹底解剖!
日本には、多くの官公庁があります。しかし、そのすべてを詳しく知る人はあまりいないのではないでしょうか。
この記事では、そんな各省庁の役割や働きを一覧にし、組織図も掲載しています。この機会に、しっかり覚えておきましょう。
官公庁とは?
そもそも、官公庁とは何なのでしょうか。
官公庁とは、国や地方公共団体の役所のことです。官公庁のうち、1つの府と13の省庁が中央省庁に属しており、その内訳は内閣府・デジタル庁・復興庁・総務省・法務省・外務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省です。
これらの省庁に勤める人は国家公務員一般職と呼ばれ、大使、大臣、裁判官、自衛官などは特別職と呼ばれます。
それぞれ適用される法律も異なります。
中央省庁の組織図・一覧と役割
では、そんな中央省庁の組織はどのような構造になっているのでしょうか。
内閣・中央省庁の組織図

NHK for Scchool|行政機関|https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?dasid=D000531039000000 を参考に政経百科 編集部で画像作成
中央省庁の種類と一覧
それでは、それぞれの省庁の働きはどのようなものなのでしょうか。解説していきます。
内閣府
内閣府は、内閣や総理大臣の主導による国家運営を目指して、総理大臣の補佐・支援の強化を実現するため2001年に設置された内閣の機関です。
ほかの省庁より1段高い立場から、国政上の重要な政策について企画立案、調整などを行っています。
内閣府の内部に存在する重要な部局として、皇室の方々のお世話や日本の伝統文化の保存などを行う宮内庁があげられます。
デジタル庁
デジタル庁では、これから日本が目指すデジタル社会の実現と、そのために必要な考え方や取り組みを示しています。
煩雑な行政上の手続きをオンライン化し、利便性を向上させるほか、民間手続きも含めてオンライン化・ワンストップ化を進めています。
復興庁
復興庁は、20111年3月11日に発生した東日本大震災に伴って設置された省庁です。いち早く復興を成し遂げられるよう、被災地に寄り添いつつ復興事業を進める組織として設置されました。
復興に関する政策の計画や実施、地方公共団体への一元的な窓口支援などを行っています。
総務省
総務省は、行政運営の改善、地方行財政、選挙、消防、防災、情報通信、郵便など、国家の運営を行う上で基本となるシステムを管理し、国民生活の基盤を担う機能を有しています。
行政に関する情報公開や地方分権改革、地域の活性化や国家の治安維持なども行っています。
法務省
法務省は、検察、刑の執行、恩赦、戸籍、人権、出入国管理など法律に関する業務を行っています。
他にも政府や国家の破壊をたくらむ団体の規制や司法書士、土地家屋調査士に関することも管轄しています。
外務省
外務省は、日本の外交を担当する省庁です。外交政策や条約の締結、通商、外国にいる日本人の保護などを行います。外交使節の交換なども行っています。
1869年(明治2年)に設置された歴史ある省庁で、現在に至るまで日本の国益を守り続けています。
文部科学省
文部科学省は、学術の振興やスポーツ政策、文化に関する政策を担当しています。日本の学校に関する業務を取り扱っているため、初等中等教育局や高等教育局を有しています。
他にも、科学技術や研究のサポートなども行っています。
厚生労働省
厚生労働省は、国民生活の発展を目指すため、社会福祉、社会保障、公衆衛生、健康増進などに関する業務を取り扱っています。
少子高齢化対策や職業の安定、労働環境の整備なども行っています。

経済産業省
経済産業省は国内産業の振興、国際間の取引の安全強化及び促進、新たな産業の創出の促進、中小企業、地域経済の支援、資源、材料、製品、情報などの安全強化を行っています。
かつては「通商産業省」という名前でしたが、2001年に科学技術庁の原子力安全部門を加えて、経済産業省と名前を変えました。
農林水産省
農林水産省は、日本の食糧の安定供給や農林水産業の発展、森林保全、水産資源の管理などを行っています。
また、外国から持ち込まれた物を検査する検疫所を有しています。設置された当初は「農林省」という名前でしたが、排他的経済水域の設定などにより水産資源の重要性が高まったことを受け、1978年に農林水産省に改称しました。
国土交通省
国土交通省は、国土の開発や保全、そのための資本の整備や交通に関する政策の推進、気象業務の発展や海上交通の安全などを担う省庁です。
2001年に北海道開発省、国土庁、運輸省、建設省を統合して設置されました。これにより、より良い行政サービスの展開や総合的な国土交通政策を展開して行くことが出来るようになったのです。
環境省
環境省は、廃棄物対策、公害の規制、自然環境や野生動物の保護などを一元的に行っています。他にも地球温暖化の抑止やオゾン層保護、海洋汚染防止など、国際的な環境問題の解決にも取り組んでいます。
防衛省
防衛省は、自衛隊を組織し、日本の主権と自由を守ることを使命としています。皆さんがこの記事を読んでいる間にも、彼らは国民の生命、財産、自由、領土、領海、領空を防衛しています。
他にも、国内外で発生した大規模災害や国際間の平和活動などにも尽力しています。
地方自治体の仕組み
では、中央省庁とは別に存在している、地方自治体について見ていきましょう。
国と都道府県(広域自治体)と市区町村(基礎自治体)の役割の違い
両者の最大の違いは、取り扱い範囲の広さにあります。広域自治体は市町村で完結しない業務や高度な専門性を有する業務を取り扱うのに対して、基礎自治体は住民生活や地域に密着した業務を行っています。
都道府県・広域自治体の主な役割
広域自治体は、その名の通り広域にわたる社会資本の整備や危機管理、産業政策、環境対策やそのほかの高度な専門性を有する業務を取り扱っています。
市区町村・基礎自治体の主な役割
一方基礎自治体は、地域に密着した対人サービスなどの行政分野を総合的に担っています。
公務員の仕事と役割
大学生の中には、一定数公務員への就職を目指す人も多いと思います。では、そもそも公務員とは何なのでしょうか。解説していきます。
公務員とは?
公務員とは、国や地方自治体に勤務している人を指します。職種はさまざまで、一般職員や裁判官、自衛官、公立学校の教員、消防士、警察官など多岐にわたります。
公務員にはどんな人たちがいるの?
では、公務員にはどんな人たちがいるのでしょうか。紹介していきます。
総合職
国家公務員を構成する職種の1つです。政策の企画立案を主な仕事とし、中央省庁に勤務することが多いのが特徴です。
一般職
総合職が企画立案した政策を問題なく実行するための事務処理を主に行います。
行政職
行政職は役所の窓口業務や公共施設の整備、管理、災害対策などを行っています。
技術職
技術職は、行政職よりも専門的な技能が求められます。公立学校の教員や警察官はここに含まれます。
特別職
常勤・非常勤を問わず、国家公務員法及び地方公務員法の適用を受けない公務員は特別職に分類できます。
総理大臣や大使、自衛官などがこれに分類されます。
まとめ
公務員は多様な職種が存在しており、それぞれ日本の繁栄と国力を支えています。皆さんの中にも、公務員となってその一助となる人がいるかもしれません。
参考になるサイト
- マイナビ2025|官公庁・公社・団体業界|https://job.mynavi.jp/conts/2025/completeguide/gyoukai/governmentofficepug/governmentofficepu_g.html
- 内閣府|内閣府組織概要図|https://www8.cao.go.jp/jinji/saiyo/pamphlet20212.pdf
- デジタル庁|政策|https://www.digital.go.jp/policies
- 復興庁|復興庁の役割|https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat12/yakuwari.html
- 外務省|外務省はどんなことをしているのですか?|https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/q_a/tokoro.html
- 文部科学省|文部科学省ってどんなところ?|https://www.mext.go.jp/kids/intro/about/index.html
- 農林水産省|農林水産省のミッション|https://www.maff.go.jp/hokkaido/soumu/jinji/attach/pdf/0603-1.pdf
- 国土交通省|国土交通省の役割|https://www.mlit.go.jp:8088/about/index.html
- 環境省|環境省のご案内|https://www.env.go.jp/annai/
- 防衛省|防衛省について|https://www.mod.go.jp/j/profile/