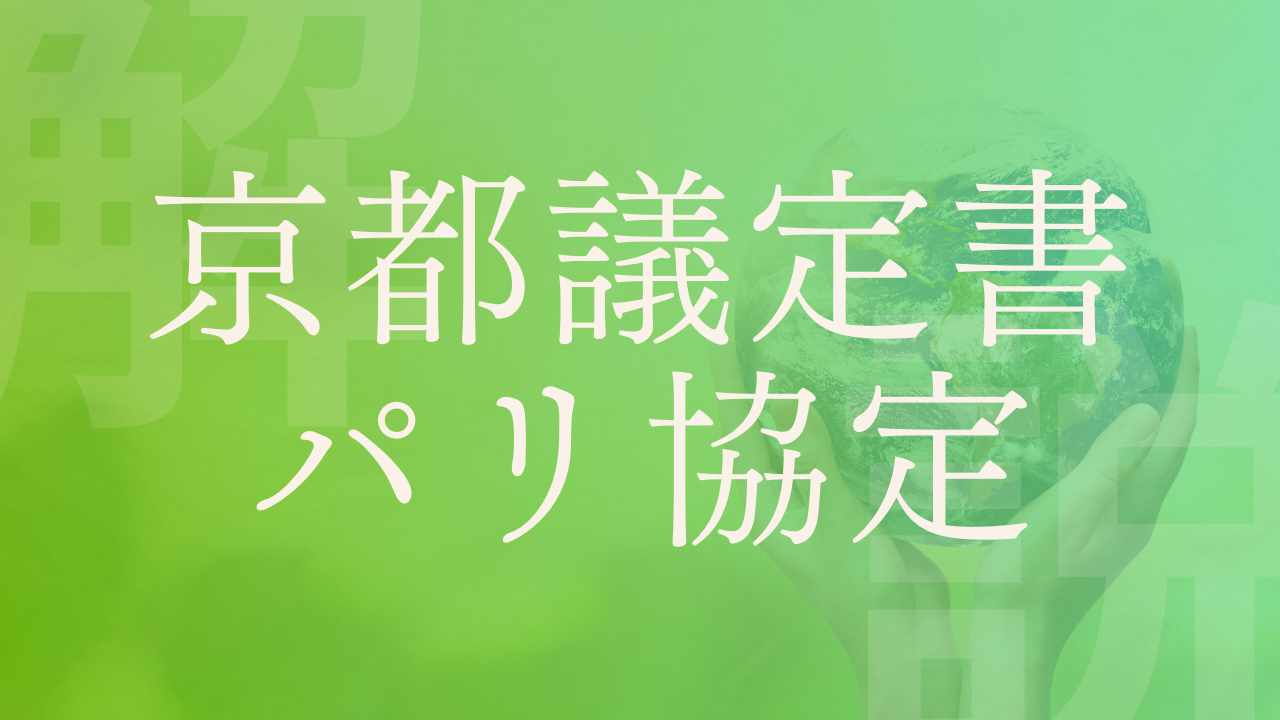【ユニバーサルデザイン】いつからある?商品例、7原則、バリアフリーとの違いは?
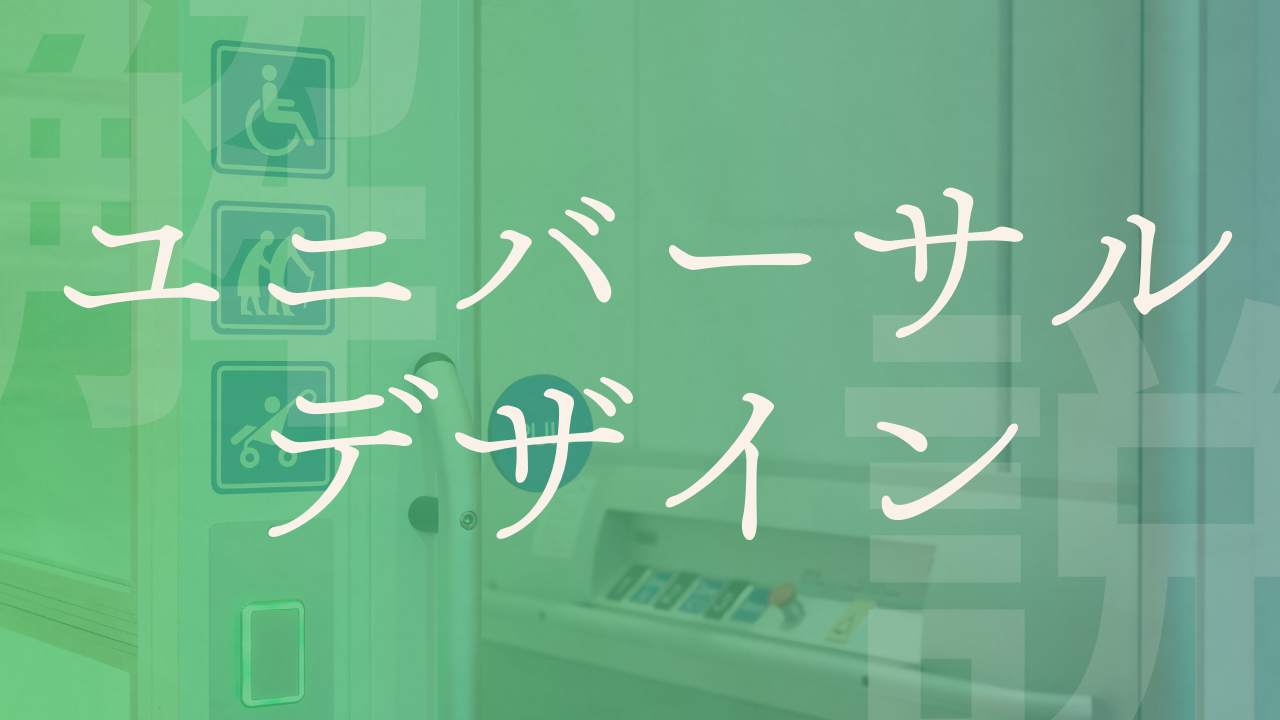
ユニバーサルデザインとは?わかりやすく解説!
ユニバーサルデザインは多くの人に優しいデザイン。そんなふわっとしたイメージをお持ちではないでしょうか?「学校で習ったものの、あまり覚えていない。」「ユニバーサルデザインとバリアフリーって何が違うの」と疑問がわきます。
この記事では、ユニバーサルデザインの概要、7つの原則、具体例からユニバーサルデザインへの理解を深めることができます。
ユニバーサルデザインとは?
ユニバーサルとは「全員の」「万人の」という意味です。そのため、「ユニバーサルデザイン」は日本語に言いかえると「みんなのためのデザイン」「誰もが使いやすいデザイン」と言えるでしょう。
ユニバーサルデザインは、年齢、性別、文化、身体的特徴にかかわらず、誰もが使いやすいデザインをするといった発想です。現代ではグローバリゼーションが進み、多様化が重視されるようになりました。
そのため、ユニバーサルデザインで誰もが過ごしやすい社会、街、モノ、仕組み、サービスを提供することは現代に求められる発想なのです。
ユニバーサルデザインが生まれた経緯
1960年代アメリカでは障がいを持つ人が増えました。正しくは障がいが認知されるようになったと言えるかもしれません。
そんな中、1963年にデンマークで「ノーマライゼーション(みんなが普通に生活していく)」という考え方が生まれ、広まっていきました。
その後、1980年代にアメリカのロナルド・メイスさんが「ユニバーサルデザイン」という考え方を提唱しました。ロナルド・メイスさんは自身も車いすを使用する障がい者でした。
そのため、障がい者の方が当たり前の生活を当たり前に。そして、差別を受けないようにするため「ユニバーサルデザイン」という考え方を提唱したのです。
日本では1995年ごろからユニバーサルデザインという言葉が知られるようになりました。
バリアフリーとの違い
ユニバーサルデザインとバリアフリーは主に3つの違いがあります。
対象とする人の違い
バリアフリーは生活弱者(障がい者、高齢者)を対象に捉えています。一方でユニバーサルデザインは生活弱者だけでなく、性別、年齢、文化の違いも含めて対象に捉えています。
障がいに対する考え方の違い
バリアフリーでは、障がいを日常生活に支障をきたすほどのものと捉え、健常者にとって使いやすいデザインを作るという発想はありません。一方で、ユニバーサルデザインは障がいを広く捉え、一時的なケガや幼少期の不自由さなども障がいと捉えます。
そして、広く障がいという概念を捉え、全ての人が使いやすいデザインを作ることを目指します。
モノに対する考え方の違い
バリアフリーでは製品としてのコストや需要などをあまり考えません。あくまでも、障がいをどう取り除くかに要点がおかれています。
一方で、ユニバーサルデザインは製品のコストと需要を考えます。誰もが使いやすいデザインであることはもちろん、製品が経済的に魅力的なものかを検討するのです。
バリアフリーとユニバーサルデザインは「誰もが使いやすい社会を作る」という基本的な考え方が共通しています。しかし、人、障がい、モノに対する捉え方が違うのです。
バリアフリーでは、日常生活に支障がでるほどの障がいを抱えている人の障がいを取り除くことに重きを置いています。一方でユニバーサルデザインは「全世界の人が共通して使いやすいデザインをつくる」という考え方なのです。
バリアフリーとユニバーサルデザインの違いを正しく理解することで、製品が作られた理由と意図が分かるようになります。
ユニバーサルデザインの7つの原則
ユニバーサルデザインには7つの原則があります。
- 誰にでも公平に利用できること
- 使う上で自由度が高いこと
- 使い方が簡単ですぐ分かること
- 必要な情報がすぐ分かること
- ミスや危険につながらないデザインであること
- 無理な姿勢をとることがなく、少ない力で楽に使用できること
- アクセスしやすいスペースと大きさを確保すること
上記の7つの原則に従ってユニバーサルデザインは作られるのです。
ユニバーサルデザインの身近な例
ユニバーサルデザインは何気なく日常で目にしています。しかし、意識していないと気づかないことも多いでしょう。
いくつか身近な例をご紹介します。
ユニバーサルデザインで設計された環境
ユニバーサルデザインで設計された環境には下記のようなものがあります。
- 街の中の段差解消
- ピクトグラムを使った表示
- 電車内の優先スペース
- 幅の広い歩道
ユニバーサルデザインはモノだけに使われる考え方ではないのです。
ユニバーサルデザインで作られたモノ
ユニバーサルデザインで作られたモノは下記のようなものがあります。
- 自動ドア
- 多機能トイレ
- シャンプーとリンスを見分ける突起
- 料金投入口の大きい自動販売機
- センサー式蛇口
- 音響・時間表示信号機
- 階段の手すり
- ノンステップバス
- 点字ブロック
ユニバーサルデザインで作られたモノは健常者にとっても便利だと感じることができます。音響・時間表示信号機は目や耳に障がいがある人はもちろん、健常者にとっても安全に信号機をわたる時に役に立ちます。
まとめ
今回は「ユニバーサルデザイン」について解説しました。ユニバーサルデザインは「誰もが使いやすい環境、モノを作る」という考え方です。ユニバーサルデザインは家の中から街まで多くの場所で採用されています。
だれかが便利でも、だれかが不便と感じていることがあるかもしれません。しかし、生活や業務でもユニバーサルデザインの考え方を使えば、みんなが過ごしやすい環境に変えていくことができます。
参考になるサイト
- Panasonic Group|UDを知ってみよう!「ユニバーサルデザインができるまでを知ろう」|https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/pks/ud/ud01_02.html
- UD資料館 JITSUKEN|ユニバーサルデザインの誕生|https://www.ud-web.info/born
- 神戸市|ユニバーサルデザインとは?|https://www.city.kobe.lg.jp/a97737/shise/kekaku/universal/promote/what_ud.html
- U/Bぷら|バリアフリーとユニバーサルデザインの違い|https://ud-shizuoka.jp/ubpla/bfud_chigai.html
- TOPPAN CREATIVE|ユニバーサルデザインとバリアフリーの違いは?具体例を交えて解説|https://solution.toppan.co.jp/creative/contents/dentatsuclinic_column08.html
- 会津若松市|ユニバーサルデザイン7つの原則|https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2008101400048/
- 郡山市|身の回りにあるユニバーサルデザイン|https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/33/4934.html