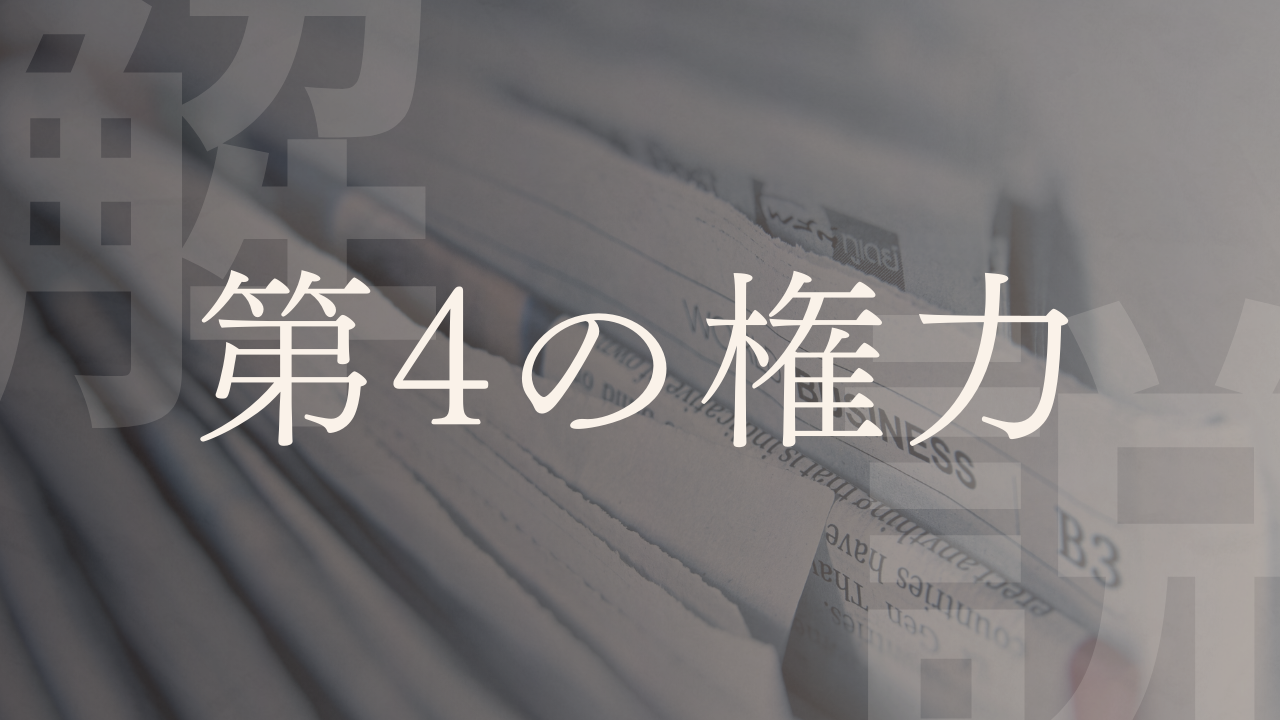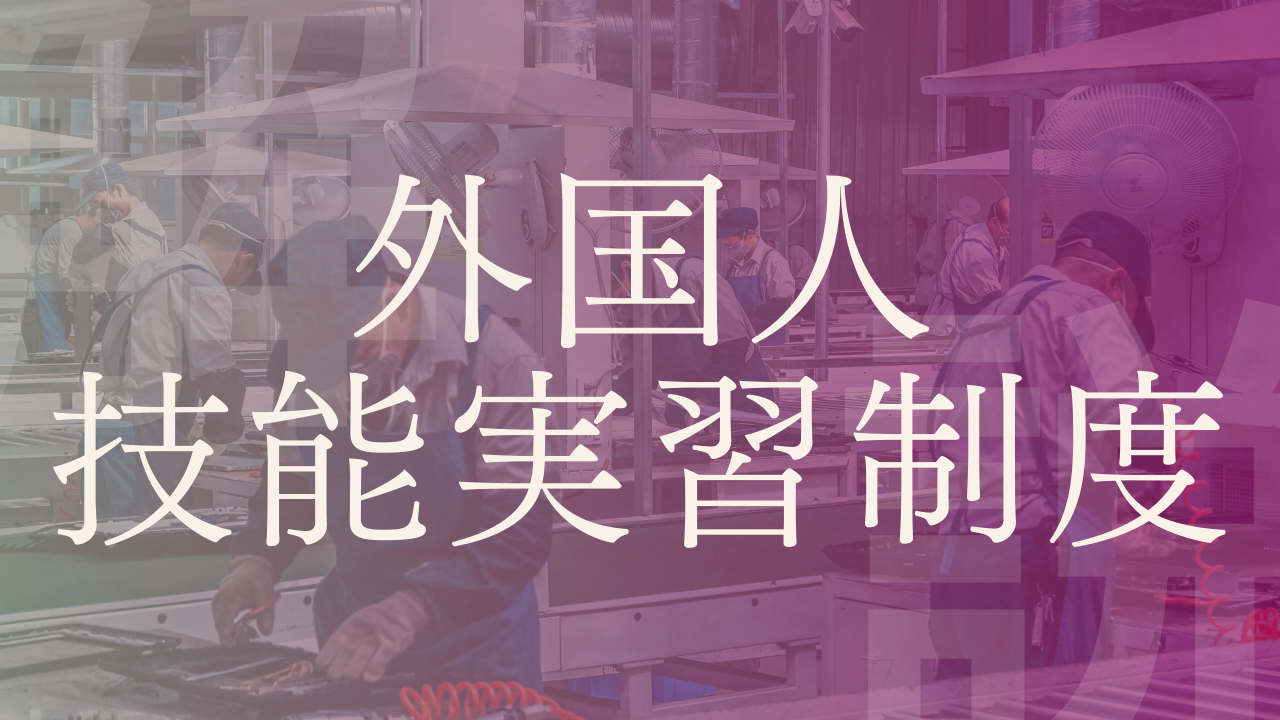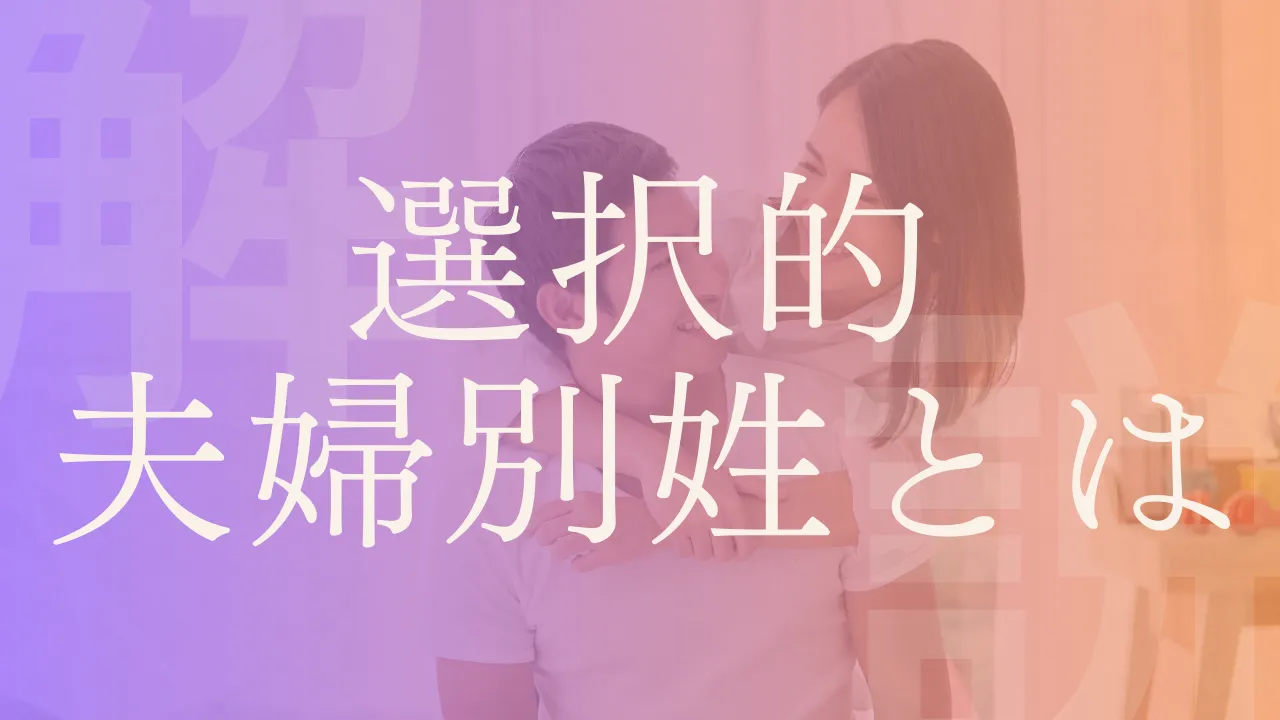【LGBTQ+】必要な配慮や企業の取り組み、理解増進法について解説!

【多様性】ジェンダー問題・性的マイノリティと日本社会のあり方を考える
みなさんは、自分の性別についてどう考えているでしょうか。自分のなりたい性や周囲から期待される性と、他人から自分に割り当てられる性のイメージに、ずれを感じたことがある人はいるでしょうか。それは生物学的な性別とはどう違うのでしょうか。最近は「ジェンダー」や「LGBTQ+」という言葉を見かける人も増えていると思います。この記事では、ジェンダーとは何か、LGBTQ+とはどんな概念なのか、わかりやすく解説します。
ジェンダー・LGBTQ+とは?
ジェンダーとLGBTQ+は、お互いに関わりの深い概念ではありますが、意味するものの方向性は大きく違います。ジェンダーが社会的性を表す一方で、LGBTQ+とは性的マイノリティの総称として用いられる言葉だからです。
ジェンダーとは:社会的性と生物学的性
ジェンダーが社会的性と呼ばれるのに対し、セックスは生物学的性を表すといわれています。生物学的性というのは、動物でいえばオスとメスが区別されるように、主に身体のつくりで判断される男性/女性の区別をいいます。一方で、社会的性というのは、社会の慣習や固定観念からイメージされる性別を指します。たとえば、女性は子育てをするもの、男性は運動が得意、などという女性像・男性像は、生物学的性に根拠があるわけではなく社会的に構築されたイメージであり、セックスではなくジェンダーであるといえます。
LGBTQ+とは
LGBTQとは、レズビアン(lesbian:女性同性愛者)、ゲイ(gay:男性同性愛者)、バイセクシュアル(bisexual:両性愛者)、トランスジェンダー(transgender:性自認と生物学的性が違う人)、クイア(queer)またはクエスチョニング(questioning)のことを指します。クイアというのは、もともとは変わり者という意味の差別的な呼び方でしたが、現在ではあえて既存の枠にとらわれない性の在り方を肯定的にとらえる呼び方として使われています。また、クエスチョニングとは、自分の性の在り方がまだ決まっていない人、あるいは固定的に決めたくない人などに使われています。最近では、LGBTQの最後にプラス(+)を付けることで、ここには表しきれない様々な性の在り方まで含むことが示されていて、性的マイノリティの総称として用いられることが多いようです。
性はグラデーション
従来、性別といえば男性か女性かの二元論が、また恋愛や性的欲求の対象といえば異性が「あたりまえ」として考えられてきました。しかし、LGBTQ+という言葉が示すように、実際には性の在り方はもっと多様で、二つにはっきりと分けられるようなものではありません。
性の在り方について考える4つの視点
性の在り方を考える際、身体的性/生物学的性(Biological Sex)、性的指向(Sexual Orientation)、性自認(Sexual Identity)、性表現(Gender Expression)の4つの視点が重要であると考えられています。1つめの視点の身体的性/生物学的性とは、生まれたときに身体のつくりから判断される性で、いわゆるセックスです。ほかの3つの視点は、まとめてSOGIEと呼ばれることもあります。性的指向とは、恋愛感情や性的欲求をどのような性に対して感じるか、性自認とは、自分で自分の性別をどのようにとらえているか、性表現とは、服装や言動を通してどのような性を表現したいか、を表します。
グラデーションと呼ばれる理由
性の在り方を考える4つの視点について紹介しましたが、どのようなSOGIEをもつかは一人ひとり異なるものであり、身体的性とは関係なく、決まった組み合わせもありません。たとえば、出生時の性が女性で、男性的な性表現を好んでいるからといって、性自認が必ずしも男性であるとは限りませんし、性的指向が女性であると決めつけることもできません。性自認が女性・男性のどちらでもない人もいますし、そもそもどんな性に対しても性的指向をもたないという人もいます。性の在り方はまさに十人十色であり、男性ならば、あるいは同性愛者ならばこうだ、と線引きできるようなものではないのです。
必要な配慮や企業の取り組み
LGBTQ+という言葉が認知されてきたとはいえ、「普通」であることが求められる社会は、性的マイノリティとしてみなされる立場の人にとって生きづらいものです。性の在り方に関わらず生きやすい社会をつくるために、私たちは何ができるでしょうか。
もしカミングアウトされたら
もしセクシュアリティについて誰かからカミングアウトされた場合、大切なのはその人の意思を尊重することです。カミングアウトへの対応にテストのような「正解」はありませんが、打ち明けてくれたことを受け止める、気を付けてほしいことはあるか尋ねる、その人が自分のセクシュアリティをどこまで公開しているか確認する、など対応が考えられます。また、話してくれた人を傷つけるようなアウティング(ある人の秘密を他の人に勝手に話すこと)には十分気を付けましょう。
企業の取り組み例
企業での性的マイノリティへの対応は、ダイバーシティ&インクルージョン(多様性と包摂)の取り組みの一環として行われることも多いようです。ある企業では、男女で異なっていた服装の規定が廃止され、そのことがホームページでも公開されました。また履歴書やESで性別の記入欄を廃止したり、写真不要としたりした会社もあります。社内研修を行ったり、困ったときに相談できる環境を整えておくことも大切だといえます。
LGBT理解増進法とは?成立の経緯と内容を解説!
LGBT理解増進法とは、昨年2023年に成立した法律で、「性的指向およびジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資すること」が目的とされています。
法案成立の経緯は、2021年、東京オリンピックの開催がきっかけでした。五輪憲章で性的指向などによる差別が禁止されていることから、超党派の議員がLGBTQ理解増進法の法案をまとめましたが、自民党保守派の反対により国会での審議さえ叶いませんでした。2年後の2023年、今度はG7サミットの開催をきっかけに、再び日本の国際社会における遅れが注目され、ついに国会へ法案が提出されました。
しかし、法案が6月に成立した一方で、内容には自民党保守派の意向が強く反映されました。「差別は許されない」という文言は「不当な差別はあってはならない」に修正された、まるで「正当な差別」が存在するかのような印象を与えるものとなっています。また「全ての国民が安心して生活できるよう留意する」という規定が加えられたことで、マイノリティに対しても寛容な社会をつくることを目的としているはずが、むしろマジョリティに配慮した内容になったとする主張もあります。
いきすぎた配慮もある?議論が分かれるケースを解説!
性的マイノリティへの配慮は世界的な潮流となっていますが、取り組みによっては大きな論争を呼ぶこともあります。
その一つが男女別トイレの廃止です。たとえば、アメリカではトランスジェンダーに配慮して男女共用のトイレを設置する学校が増えています。ところが、ある高校では、トランスジェンダー女性の生徒が共用トイレではなく、自認する性に合わせたトイレを使いたいと希望し、学校が許可したところ、約150人の女子生徒は授業をボイコットし、親たちによる抗議デモまで発生しました。その一方で、スウェーデンでは男女共用のトイレが一般的で、そもそも男女別のトイレ自体がほとんど存在しません。日本でも、2023年には渋谷区に「誰もが使えるトイレ」が設置され、話題になりました。同様に、新宿区の複合施設では「ジェンダーレストイレ」が設置されましたが、次々と不安の声や抵抗感が寄せられ、わずか4か月後には男女別のトイレに改修されてしまったという事例もあります。合理的な配慮としてどこまで認めるべきかは、今後議論の余地がありそうです。
まとめ
今回は、そもそもジェンダーやLGBTQ+とは何を意味するのか、性的マイノリティに対して求められる配慮とその対応をめぐる議論にはどのようなものがあるのか、について紹介しました。LGBTQ+なんて自分は出会ったことがない、と思う人もいるかもしれませんが、実は左利きやAB型の人と同じくらいいるとも言われています。
そもそも性はグラデーションであるということを考えれば、多様な性があるのは自然なことといえます。この機会に自分の性の在り方や、自分や周囲の人がどんなジェンダー観をもっているか、ぜひ考えてみてください。
参考になるサイト
- 東京レインボープライド2024|LGBTQとは|https://tokyorainbowpride.com/lgbt/
- PILCON|LGBTQ+・多様な性のあり方|https://pilcon.org/help-line/lgbt
- 文春オンライン|職場で同僚にカミングアウトされたら? 気をつけたい3つのポイント|https://bunshun.jp/articles/-/21213
- 朝日新聞SDGs ACTION!|SOGIとは?意味やLGBTとの違い、SOGIハラへの対策を解説|https://www.asahi.com/sdgs/article/14813603#h255slcu4jnic1z0id8y1lob1exjhq3u5
- 朝日新聞SDGs ACTION!|「LGBT理解増進法」施行 当事者・支援団体からは内容に批判も 企業への影響は?|https://www.asahi.com/sdgs/article/14939487
- 産経新聞|行き過ぎ? 性的少数者へ配慮で小学校の男女別トイレ廃止 憤懣ぶちまける親の抗議デモ騒ぎに|https://www.sankei.com/article/20150920-MXOXJOEX6VJFZPHQ4WZUIJIDGI/?119893
- 朝日新聞GLOBE+|トイレは男女共用が普通のスウェーデンで見た工夫や配慮 性別の枠の「次」探る試みも|https://globe.asahi.com/article/14938999