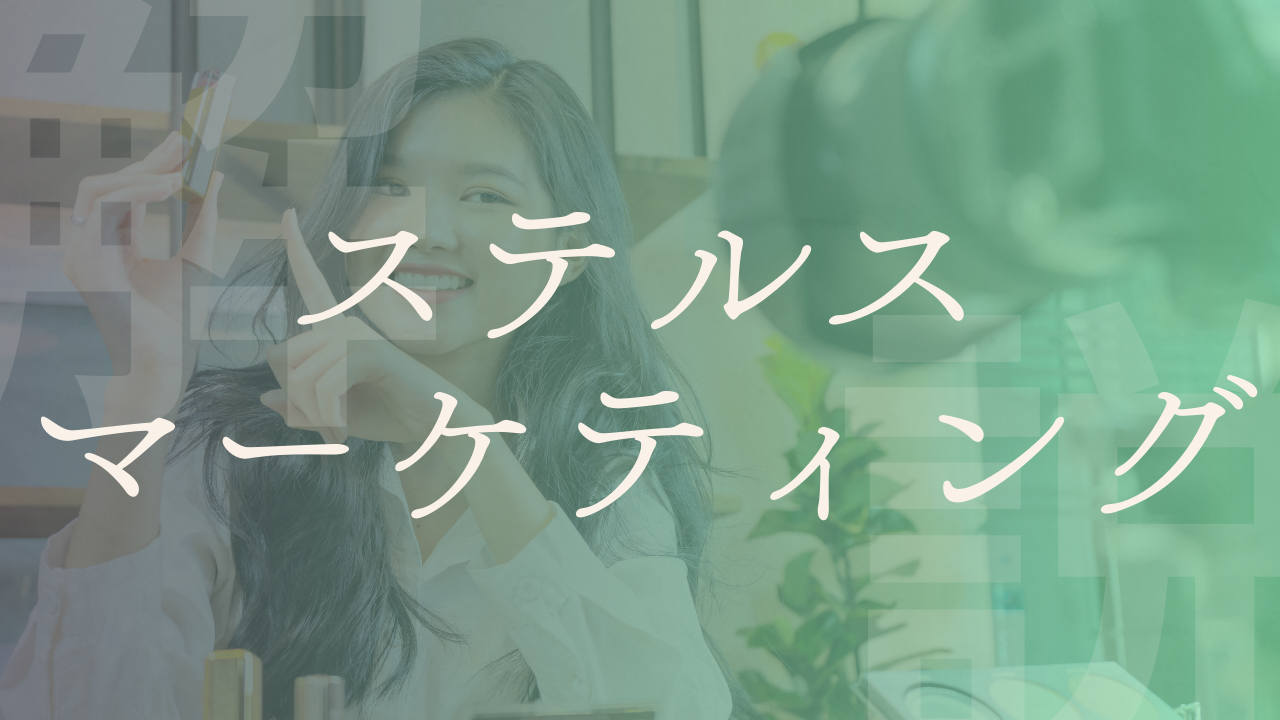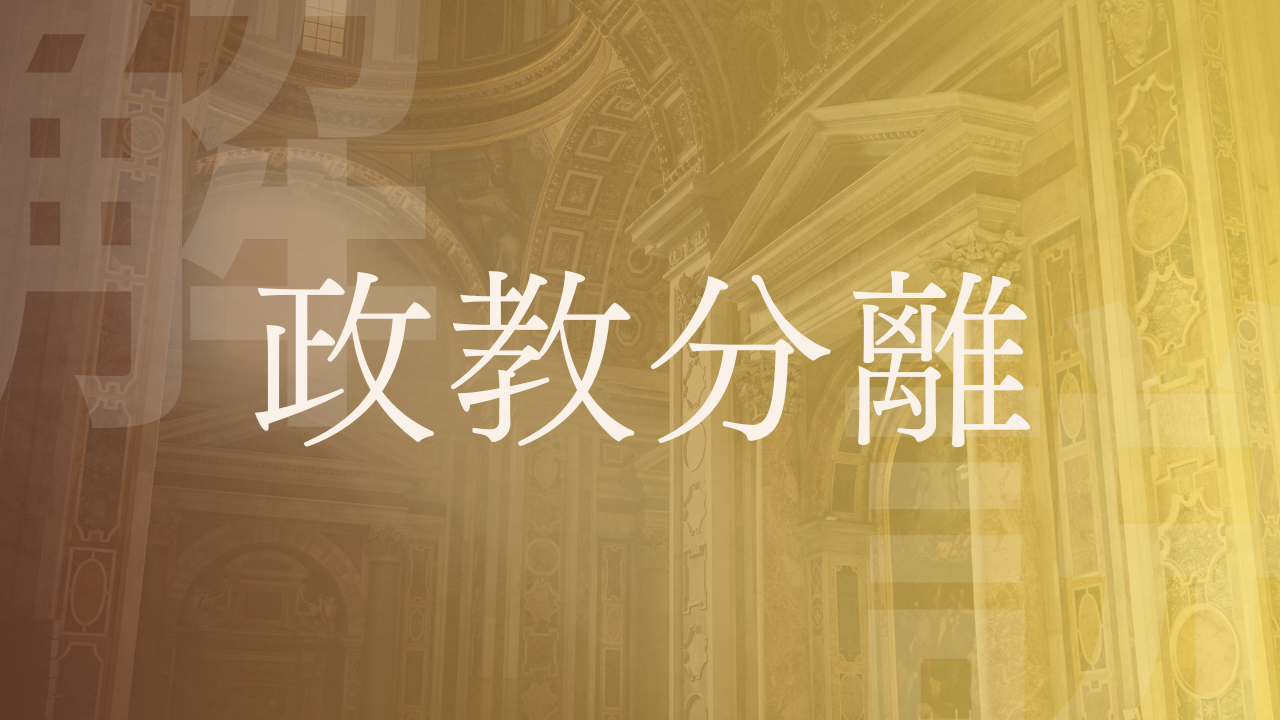【子宮頸がんワクチン】接種すべき?リスクはある?そもそも子宮頸がんとは
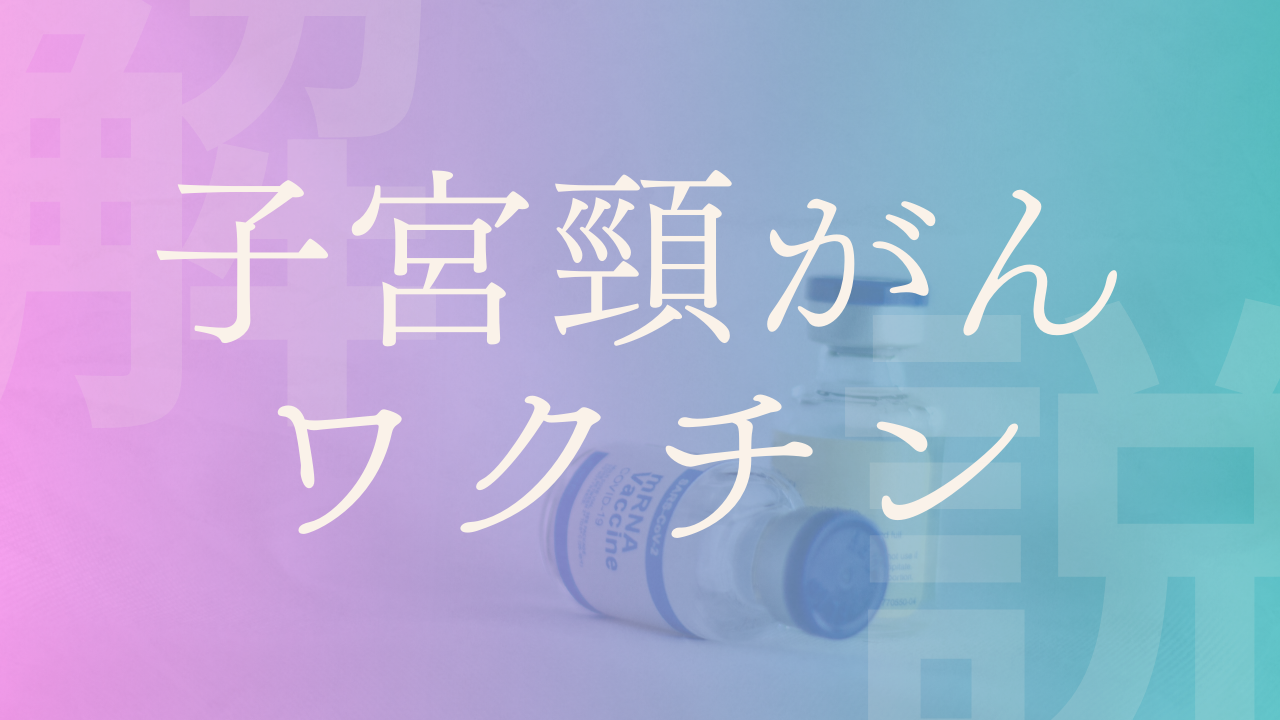
HPVワクチン・子宮頸がんワクチンとは?安全性は?正しい知識を身につけることが重要!
毎年日本人女性の約1万人がかかると言われている子宮頸がん。現在ワクチンの接種が勧められていますが、実際にワクチン接種は必要なのでしょうか。子宮頸がんワクチンについて詳しく解説していきます。
子宮頸がんとは?
そもそも子宮頸がんとはどのような病気で、どのように感染し、どのような症状が現れるのでしょうか。子宮頸がんとは具体的に何なのか見ていきましょう。
子宮頸がんとはどんな病気?
子宮頸がんとは、子宮頸部にできるがんのことです。大部分の子宮頸がんは、CIN(子宮頸部上皮内腫瘍)やAIS(上皮内腺がん)という、がんになる前の状態を経てからがんになります。
腟に近い側にできた場合には、婦人科での観察や検査がしやすいため発見されやすくなりますが、より奥の筒状の部分にできると、発見が難しいこともあります。
また、早期に発見すれば比較的治療しやすく予後の良いがんですが、進行すると治療が難しいことから、早期発見が極めて重要です。子宮頸がんは、進行すると骨盤の中のリンパ節に転移したり、子宮頸部の周りの組織に広がったり、子宮から離れた肺などの臓器に転移したりすることがあります。
感染経路や症状は?
子宮頸がんのウイルスは性的接触により子宮頸部に感染します。HPVは男性にも女性にも感染するありふれたウイルスであり、性交経験のある女性の過半数は、一生に一度は感染する可能性があるといわれています。
HPVに感染しても、90%の人においては免疫の力でウイルスが自然に排除されますが、10%の人ではHPV感染が長期間持続します。このうち自然治癒しない一部の人は異形成とよばれる前がん病変を経て、数年以上をかけて子宮頸がんに進行します。がんになる前の状態であるCINやAISの時期には症状がなく、おりものや出血、痛みもありません。
子宮頸がんが進行すると、月経中でないときや性交時の出血、においを伴う濃い茶色や膿うみのようなおりもの、水っぽいおりものや粘液がたくさん出るなどの症状がみられることがあります。がんが子宮の外に広がると、多量の出血、骨盤や下腹部、腰の痛み、尿や便に血が混じる、下肢のむくみなどの症状が出ることもあります。
子宮頸がんワクチンと検診は両方必要?
ワクチンと検診はともに子宮頸がんに有効とされている予防法ですが、両方行うことは必要なのでしょうか。
子宮頸がんワクチンの役割
子宮頸がんを予防するHPVワクチンはヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を予防するワクチンです。小学校6年〜高校1年相当の女子は、予防接種法に基づく定期接種として、公費によりHPVワクチンを接種することができます。一定の間隔をあけて、同じ種類のワクチンを合計2回または3回接種します。接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。
子宮頸がん検診の有用性
定期的な検診はがんになる前の段階やがんの初期に発見することにつながります。子宮頸がん検診は、画像診断や腫瘍マーカーなど、ほかのがん検診で行うような間接的な検査ではなく、がんができる場所の細胞を直接採取して確認する検査です。子宮頸がん検診では、子宮の入り口部分の表面を、やわらかいヘラやブラシで軽くこすって細胞を採取して調べます(細胞診)。
子宮頸がんワクチンに対しての公的支援
HPVワクチンは定期接種の対象となっているため、対象年齢の女性なら公費(原則自己負担なし)で接種することができます。
日本で対象となる年齢は、小学校6年生〜高校1年生相当です。また、過去に定期接種の機会を逃した方も、同じように公費でワクチン接種することができる制度もあります。
現在、公費で受けられるHPVワクチンは、3種類(2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9))あります。
子宮頸がんワクチンの歴史的背景
HPVワクチンは2006年に欧米で生まれ、日本では2009年10月にワクチンとして承認され、接種が開始されました。
世界保健機関(WHO)が接種を推奨しており、現在は、120か国以上で公的な予防接種が行われています(2022年12月時点)。カナダ、イギリス、オーストラリアなど、接種率が8割を超える国もあります。
日本では、2010年度から公費助成、2013年度から小学6年〜高校1年女子への定期接種積極推奨が始まり、接種率は55.5〜68.9%になりましたが、副反応が疑われたため、厚生労働省は同年6月から推奨を控えました。すると接種率が激減し、その世代のHPV感染率や子宮頸部異形成有病率が上昇しました。
その後、ワクチンの安全性再確認、有害事象対策整備、補償制度拡充を経て、2022年4月から「勧奨」およびキャッチアップ接種が再開されましたが、その接種率は十分回復していません。その回復にむけて、ワクチンの効果に関する情報の周知、および接種時の有害事象とそれらの治療体制や補償に関する情報の周知によるワクチンへの不安の払拭が重要と考えられています。
子宮頸がんワクチンは摂取すべき?
子宮頸がんワクチンは予防効果などのメリットが大きい反面、副反応などのデメリットもあります。ワクチン接種を決定する際は正しい効果とリスクについて知ることが必要になります。
摂取すべき理由
HPVの中には子宮頸がんをおこしやすい種類のものがあります。
HPVワクチンは、このうち一部の感染を防ぐことができます。
サーバリックスおよびガーダシルは、子宮頸がんをおこしやすい種類であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50〜70%を防ぎます。シルガード9は、HPV16型と18型に加え、ほかの5種類のHPVの感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80〜90%を防ぎます。また、HPVワクチンで、がんになる手前の状態(前がん病変)が減るとともに、がんそのものを予防する効果があることもわかってきています。
懸念されるリスク
筋肉注射という方法で注射します。接種を受けた部分の痛みや腫れ、赤みなどの症状が起こることがあります。ワクチンの接種を受けた後に、まれですが、重い症状(呼吸困難や蕁麻疹などのアレルギー症状や、頭痛・嘔吐・意識の低下などの神経系の症状)が起こることがあります。
また、広い範囲の痛み、手足の動かしにくさ、不随意運動といった多様な症状が報告されています。ワクチンが原因となったものかどうかわからないものをふくめて、接種後に重篤な症状として報告があったのは、ワクチンを受けた1万人あたり約3〜5人です。接種するワクチンや年齢によって、合計2回または3回接種しますが、接種した際に気になる症状が現れたら、それ以降の接種をやめることができます。
まとめ
子宮頸がんワクチンを接種することは良い効果だけでなくリスクも指摘されています。一方の立場の情報を聞くだけでなく、しっかりと正しい知識を身につけた上で判断するようにしましょう。
参考になるサイト
- 公共社団法人 日本産科婦人科学会|子宮頸がん|https://www.jsog.or.jp/citizen/5713/
- ganjoho.jp|子宮頸がんについて|https://ganjoho.jp/public/cancer/cervix_uteri/about.html
- もっと知りたい子宮頸がん予防|HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)について|https://www.shikyukeigan-yobo.jp/vaccines/
- 厚生労働省|ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~|https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html
- Keio university Health Center|子宮頸がん予防のためのヒトパピローマウイルスワクチンに関する我が国の歴史、現状、接種率向上のための提言:情報開示の重要性|https://www.hcc.keio.ac.jp/ja/research/assets/files/41-3.pdf