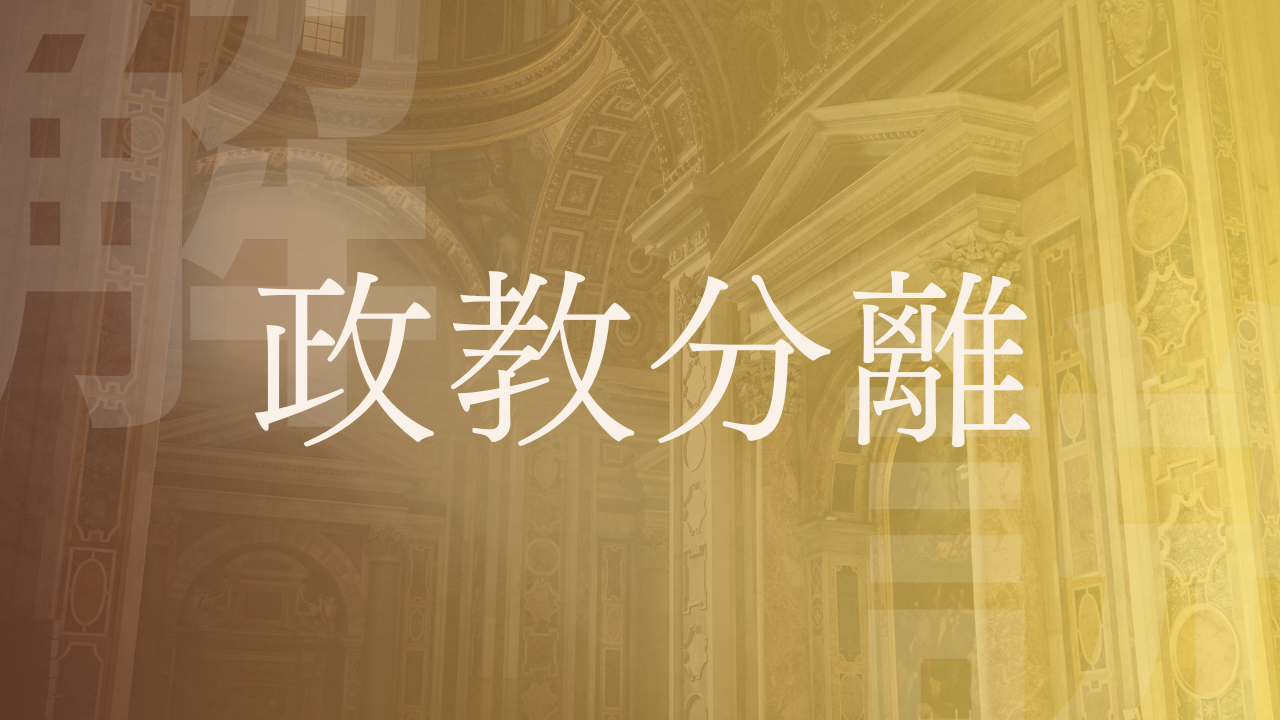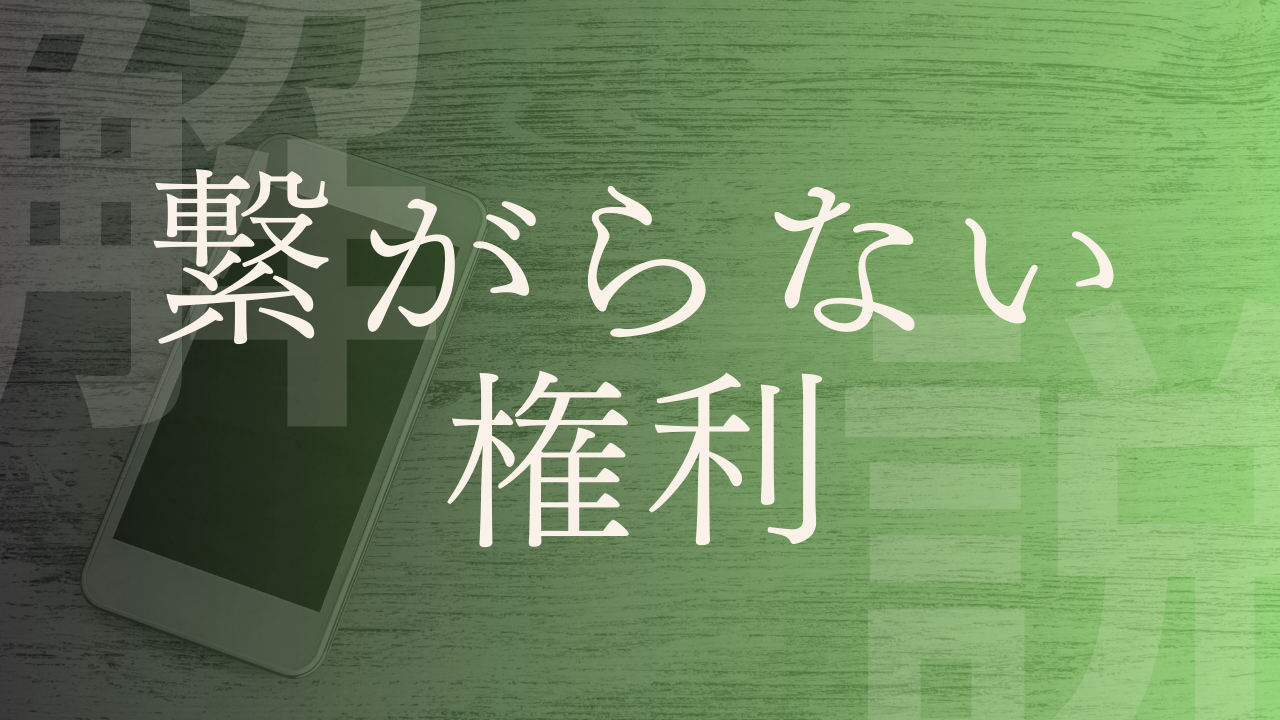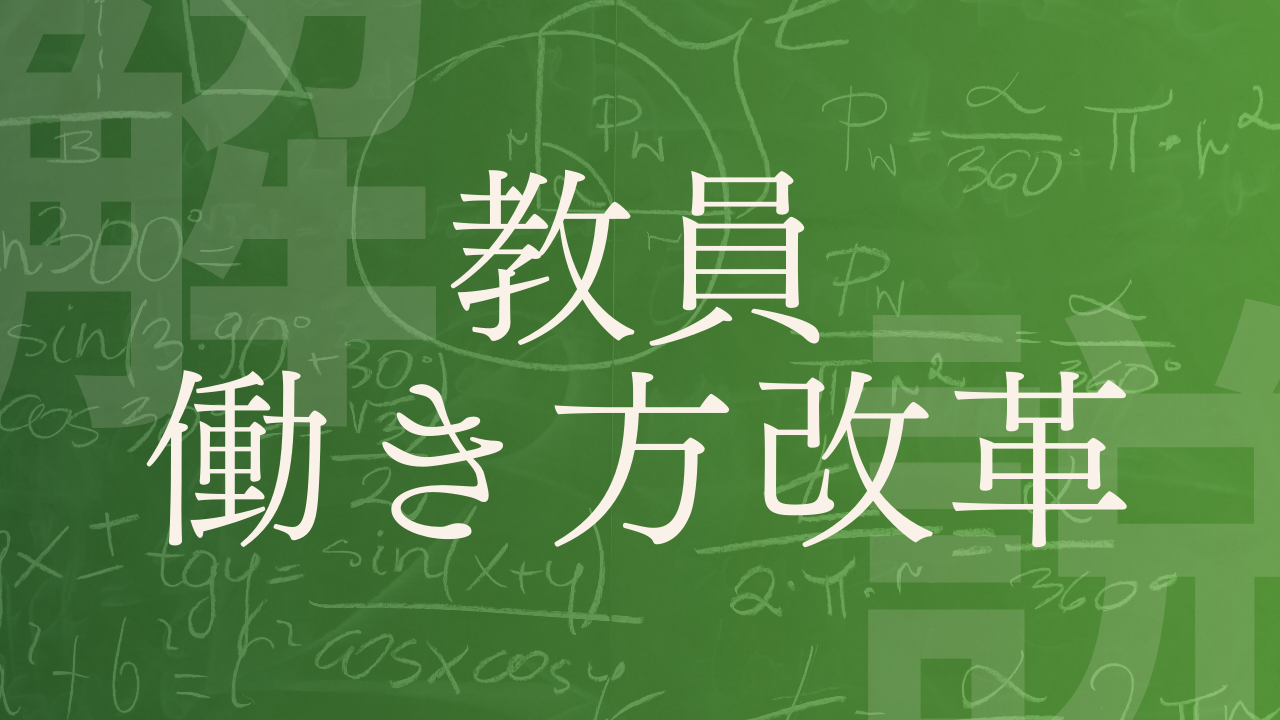【育休とは】何歳まで?男性も取れる?給付金や期間、手当についても解説

育児休業・育児休暇とはどんな制度なのか?
子どもが生まれるのはおめでたい出来事ですが、出産・育児はとても片手間にできることではありません。赤ちゃんには付きっきりでお世話が必要な一方で、働かなければ収入はありません。そこで役立つのがいわゆる「育休」ですが、そもそもどんな制度なのでしょうか?
育児休業制度とは?
育児休業とは、育児・介護休業法第2条に基づく制度であり、いわゆる「育休」と呼ばれるものです。
法律によって定められた「労働者の権利」なので、会社が特にルールを決めていない場合でも、労働者は性別に関係なく育児休業を取得する権利をもっています。簡単にいうと、子どもが生まれたばかりで働くことができない間、もともとの賃金のかわりに給付金がもらえるよう保障する仕組みであるといえます。
育児休業制度と育児目的休暇との違いは?
「育児休業」とは別に「育児目的休暇」と呼ばれるものも存在します。一体何が違うのでしょうか?育児休業、いわゆる育休は「公的な制度」なので、誰が、いつからいつまで取得できるのか、どのくらい給付金がもらえるのかというルールが法律で決まっています。一方で、育児目的休暇(育児休暇と呼ばれることも)とは、企業がそれらのルールを決められる独自の制度なので、どこの企業でも平等に利用できるわけではありません。
育児休業制度の内容(2022年改正の育児・介護休業法の内容)
日本では長年、女性に比べて男性の育児休業取得率が極端に低いことが問題視されてきました。厚生労働省によると、2022年度の女性の取得率が80.2%だったのに対し、男性の取得率は17.13%でした。男女でかなり違いがあることがわかりますね。
データ参照:NHK「育児休業の改正法が施行 育休パパを増やせ!」https://www.nhk.jp/p/ts/X67KZLM3P6/episode/te/917XRKYWMZ/
このような現状をふまえて、2022年4月、政府は育児・介護休業法の改正法を施行しました。2023年3月現在の主な育児休業制度は以下のようになっています。
① 「産後パパ育休」の創設
・子どもが生まれてから8週間以内に、父親は最長で4週間の休業を取得できる。
・2回に分割して取得することもできる。
② 「育児休業」のルール柔軟化
・取得可能期間:子どもが1歳になるまで(特別な事情があれば、最長で2歳まで)取得できる(改正前と同じ)
・分割取得:分割できない→2回まで分割できる
・1歳以降の延長:育休延長開始は子どもが1歳or1歳半になったときのみ
→自由なタイミングで育休を開始できる
③ 「パパ・ママ育休プラス」(改正前と同じ)
・両親がどちらも育児休業を取得する場合、子どもが1歳2か月になるまで育休期間をずらすことができる
(期間は最長で1年間のままだが、たとえば父親の育休開始を2か月遅らせると、母親が1年の育休を終えても、父親はもう2か月育休を続けることができる)
参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律|https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC000000007620230401503AC0000000063
育児休業給付金とは?
育児休業給付金とは、育児休業中にもらえる給付金のことをさします。また産後パパ育休を取得した場合、その期間中は出生時育児休業給付金が支給されます。育児目的休暇とは違い、これらは法律に基づく公的制度なので、給付金は雇用保険から支払われます。育休をとると会社に負担がかかるのでは、とためらう人もいるかもしれませんが、企業が直接負担するわけではないのですね。
育児休業給付金の対象者や条件、申請方法は?
給付金は雇用保険から支払われるので、対象者は雇用保険に加入している必要があります。雇用保険とは、雇用されている労働者の生活を保障するためのものなので、いわゆる自営業の人は残念ながら育休の対象とはなりません。また、給付金の対象となるには、育休後に職場復帰する予定であることが前提となっています。
育休の基本的なルールに則っていれば問題ありませんが、3回以上に分割取得すると給付金の対象外となるので、注意が必要です。
申請は、所定の申請書と賃金証明書をハローワークに提出するか、電子申請も利用できます。
育児休業・育児目的休暇運用における雇用者側に必要な配慮は?
以上が育休制度の概要ですが、実際に育休の取得を促進し、さらに実のある育休にするには、企業側の協力が欠かせません。
「男なのに育休?」パタハラに注意
育休をとった女性が職場で受けるハラスメントは「マタハラ」と呼ばれますが、同様に育休をとろうとする男性が受ける嫌がらせは「パタハラ」と呼ばれます。「奥さんが家にいるのになぜ?」だとか、「育休をとるなら出世はさせない」といった発言は、男性の育児参加に対する理解が低いことの表れです。これでは男性社員も進んで育休をとろう、という気には到底ならないでしょう。
育休制度について周知・理解の徹底を
そのために、まずは社員に育休制度について知ってもらうことが必要です。育休は労働者の権利であること、育休取得を理由とする減給や解雇は不当であることなど、制度に対する社員の理解を深め、性別を問わず育休をとりやすい雰囲気をつくることが重要になるでしょう。
「取るだけ育休」からの脱却
また、男性の育休取得率は少しずつ高まってきている一方で、2021年度の調査によると、女性の95%が6か月以上の育休をとっていたのに対し、男性は取得者のうち約半数が2週間未満の育休にとどまっていました。従業員1,000人以上の企業は男性の育休取得率の公表を義務付けられていることもあり、男性による育休の多くはポーズとしての「取るだけ育休」に過ぎないという批判もあります。雇用者側は、単なる数値上の成果としてだけの育休ではなく、意味のある育休をとるよう促進することも求められているといえるでしょう。
まとめ
「育休」という制度自体は知られていても、その中身は意外と複雑でわかりにくいものです。しかし、どんな育休制度が整備されているのか、育休を取得することが社会でどのように捉えられているのかは、私たちZ世代の出産・子育てにかかわる決定に大きく関わってくるといえるでしょう。
参考になるサイト
- あしたの人事|育児休業とは?育児休暇との違い、給付金の支給条件や期間、申請方法など解説|https://www.ashita-team.com/jinji-online/institutional/14701#%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91%E3%81%A8%E3%81%AF
- 厚生労働省「育児休業制度 特設サイト」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/index.html
- 厚生労働省「育児休業と育児目的休暇の違いについて」https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/content/contents/syuseiji2019-1.pdf
- NHK「育児休業の改正法が施行 育休パパを増やせ!」https://www.nhk.jp/p/ts/X67KZLM3P6/episode/te/917XRKYWMZ/
- 厚生労働省「知っておこう。育児休業制度」https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001194426.pdf
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律|https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC000000007620230401503AC0000000063
- 厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続き」https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001126859.pdf
- indeed「「パタニティハラスメント」とは 男性社員の育休取得の実態と課題」https://jp.indeed.com/%E6%B1%82%E4%BA%BA%E5%BA%83%E5%91%8A/c/info/what-is-paternity-harassment
- FNNプライムオンライン「『育休とるなら出世はさせない』パタハラは男性育休にも…改正法施行後の変化は?現状を聞いた」https://www.fnn.jp/articles/-/551073
- NHK「男性の育児休業取得率 過去最高の約17%も目標には大きな開き」https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230731/k10014148081000.html