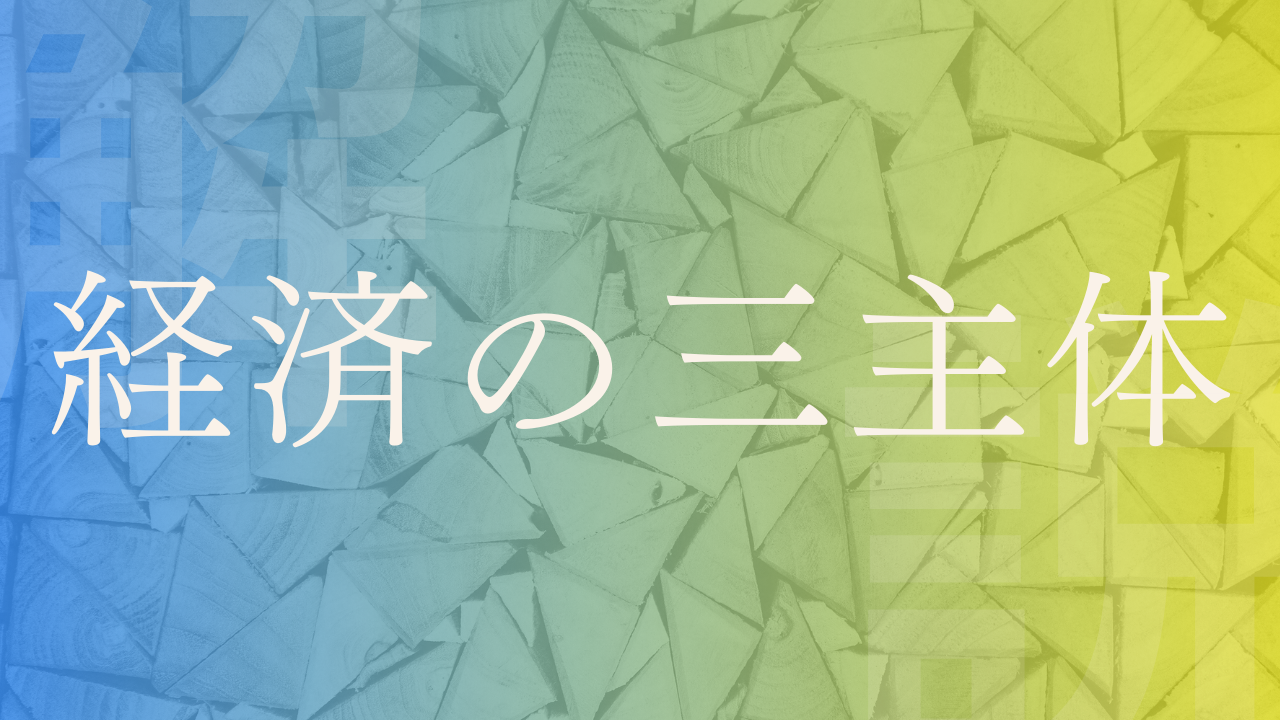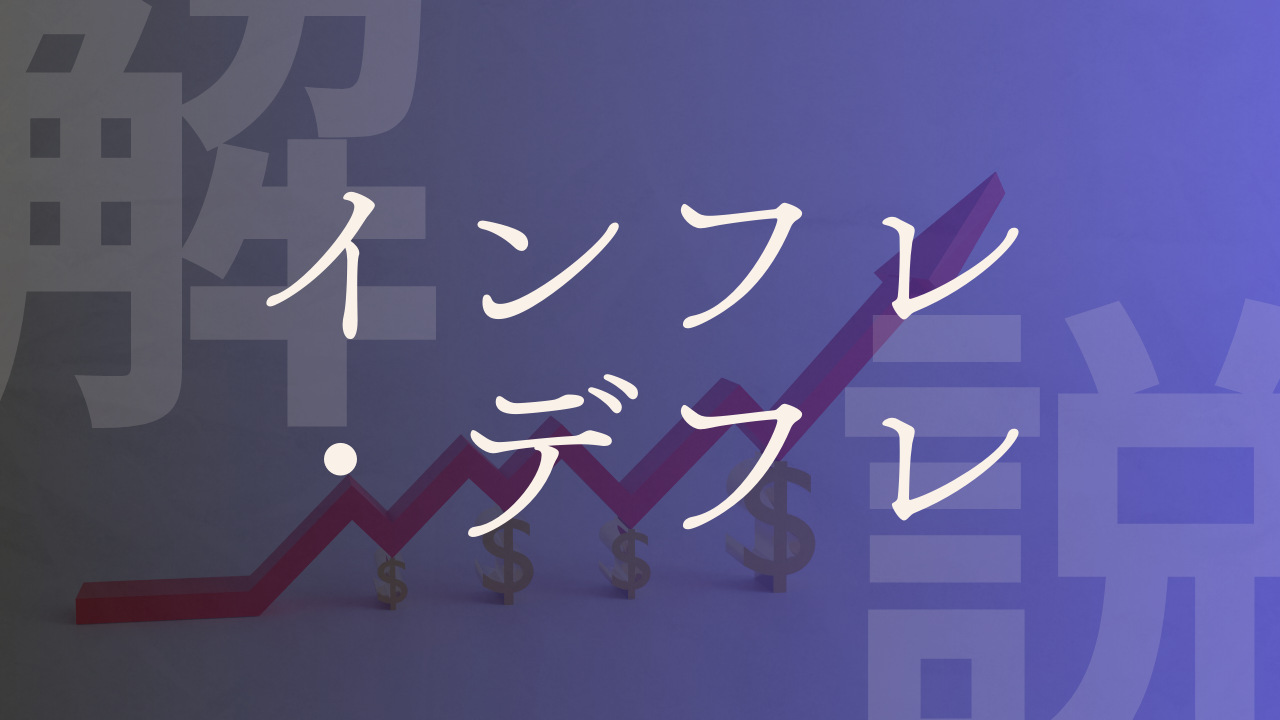【失われた30年】いつから?意味、原因や解決策をわかりやすく解説
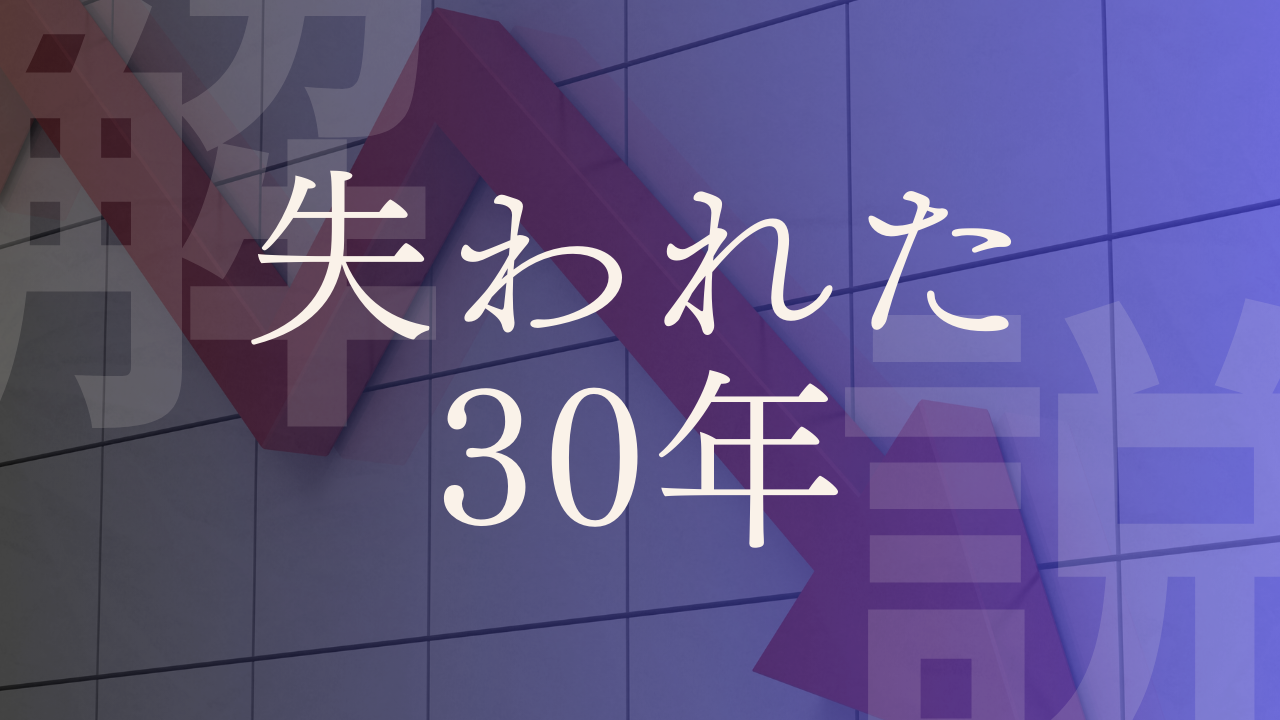
バブル崩壊から始まった失われた三十年とは、一体何?脱却の兆しはある?
日本経済を形容する場合に「失われた30年」という言葉がよく用いられます。
2024年3月には日経平均株価が史上最高値となる4万円を突破したことが話題となりました。株価の上昇などの今の経済状況を、「失われた30年」からの脱却の糸口が掴めつつあると見ることもできます。
一方で、「景気が回復している」「景気は上向きである」実感がなかなか得られない人も少なくありません。「失われた30年」の姿を見ていきましょう。
「失われた30年」はいつから始まった?
失われた30年とは、バブル崩壊以降の長期的な景気の停滞のことです。
バブル崩壊後、日本経済は短期間の間では景気が上向きとなることもありましたが、上がり下がりを繰り返し、全体としては景気の停滞が続きました。
1995年には、1ドルが80円を割り込む超円高の状態となります。円高となると輸出産業が打撃を受けるため景気が落ち込みました。
1997年には、山一證券が自主廃業、北海道拓殖銀行(拓銀)といった有名企業が次々と経営破綻に陥ります。
この背景にはいずれもバブル崩壊が関係しています。山一證券はバブル時代に契約した利回りを顧客に支払えず、法令違反となる損失の穴埋めを行い粉飾決算が明らかになり自主廃業に至りました。拓銀も、バブル時代にホテル事業など他分野への投資を行い、それが回収できず経営破綻に至ります。
2000年代に入ると世界的にITの需要が高まり、2000年代なかばには一時的にITバブルを引き起こします。しかし2008年9月に大手証券会社のリーマン・ブラザーズが経営破綻に陥るリーマンショックが起こり、世界的な不況に陥ります。
2001年9月11日に起きたアメリカ同時多発テロ事件や、2011年3月11日の東日本大震災など、国内外で起きた大きな出来事も景気後退に影響を及ぼしています。
バブル崩壊の原因や責任は?誰のせい?
そもそもバブル崩壊の原因や責任は何であると言えるでしょうか。
不動産等が実態以上に値上がりしている
バブルの時代は、お金の流れがお金そのものではなくモノに集中していました。土地や不動産、株価、高級車などです。これらが実際の価値以上に値上がりをしてしまったので、その金額が本来の価値へ戻ってしまうと、投資をしていた人は大きな損失を負うことになります。バブル崩壊の大きな原因はここにあると言えます。
低金利政策の継続
バブルで、投資がモノに集中した理由として、日本銀行が取り続けていた低金利政策があげられます。金利が高いならばお金を預けていれば、おのずと増えてゆきます。それがなかったために、より価値の上昇が見込めるモノへと投資が集中してしまったのです。金利を見直していれば、こうした一方的な動きは起こらなかったと言えます。バブルを引き起こしてしまった原因でもあり責任のひとつに日本銀行の低金利政策は関係していると言えます。
30年間回復しない原因
それでは30年間の長期間に渡り、経済が回復しない理由は何でしょうか。大きくあげられるのは負のスパイラルです。
大量のロスジェネを生み出したこと
バブル崩壊後、企業は採用する人数を絞り始めます。そうなると当然就職できない人たちが出てきます。その人たちはアルバイトや派遣社員などの非正規雇用の立場で働かなければいけません。当然賃金は低いままでスキルアップも望めません。お金がないので消費もできません。さらにお金がかかる結婚や出産にもハードルが立ちはだかります。
バブル崩壊後の1990年代前半から2000年代はじめに就職活動をした人たちは失われた世代であるロスジェネ世代と呼ばれています。2024年現在ならば30代後半から50代前半くらいの世代が該当します。一般的にこの世代は働き盛りであり社会の中心を担うべき存在ですが、ロスジェネ世代の中には思うように活躍ができていない人たちもいます。
社会が現状に慣れきっている
景気上昇は物価と賃金がともにあがっていくことで起こります。しかし日本社会は賃金も物価も上がらないままです。デフレ状態が長く続くと人々はその現状に慣れきってしまいます。日本銀行の前総裁である黒田東彦氏は2023年4月の退任時の会見で「賃金や物価が上がらないことを前提としたノルム(社会通念)が根強かった」と振り返っています。
【失われた30年】解決策について
失われた30年を回復させるために必要な策は何でしょうか。
デフレからの脱却
まず必要なものはデフレからの脱却であると言えます。デフレとは普段使っている日用品やサービスの対価が下がる現象です。なぜモノやサービスの対価が下がってゆくのかといえば、需要に対して供給量の方が上回っているためです。同じお金で買えるものが多くなるので貨幣の価値は上がります。
「お金の価値が上がるならばよいのではないか」と思うかもしれませんが、借金をしている人は負担が大きくなります。借金は個人ばかりでなく企業もしていますので、新しいイノベーションを生み出さなくなり、経済の落ち込みを生み出します。
さらにデフレは「安いからいいのではないか」と思うかもしれませんが、こちらも需要がない状態が続くため、長い目で見れば経済の落ち込みに繋がります
物価と賃金の上昇を目指す
景気回復のためには賃金と物価の上昇が必須です。現在は賃金は上がらず物価が上昇を続ける状態が続いています。もし賃金が上がったとしても物価は現状維持、あるいは今よりも下がって欲しいと望む場合では景気回復は望めません。生活者のマインドを変えていく必要もあると言えます。もちろん、物価も上がるが賃金も上がるベストな生活状態が作られる必要があります。
まとめ
失われた30年は、1990年代はじめのバブル崩壊後に日本経済が陥っている長期間の不景気状態を指します。賃金は上昇しないまま物価も上がらないデフレ状態が長引いたことが原因です。解決策として、デフレからの脱却や物価と賃金の上昇が挙げられます。
参考になるサイト
- 日経平均 読む・知る・学ぶ|1990年代:バブル景気が崩壊、公的資金投入へ|https://indexes.nikkei.co.jp/atoz/2016/06/1990s.html
- 日経平均 読む・知る・学ぶ|2000年代:911テロとリーマン・ショック|https://indexes.nikkei.co.jp/atoz/2016/06/2000s.html
- 楽天証券 トウシル|山一證券が自主廃業に伴い営業を終了【1998(平成10)年3月31日】|https://media.rakuten-sec.net/articles/-/40914
- 日経ビジネス|1980年代バブル、膨張と崩壊に3つの原因|https://business.nikkei.com/atcl/report/16/011900002/012200004
- 内閣府|デフレ脱却に向けた展望と課題|https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je06/06-00102.html
- JAIC|ロスジェネ世代とはどんな意味? ゆとり世代などとの違いも解説!|https://www.jaic-college.jp/useful/u-11629/