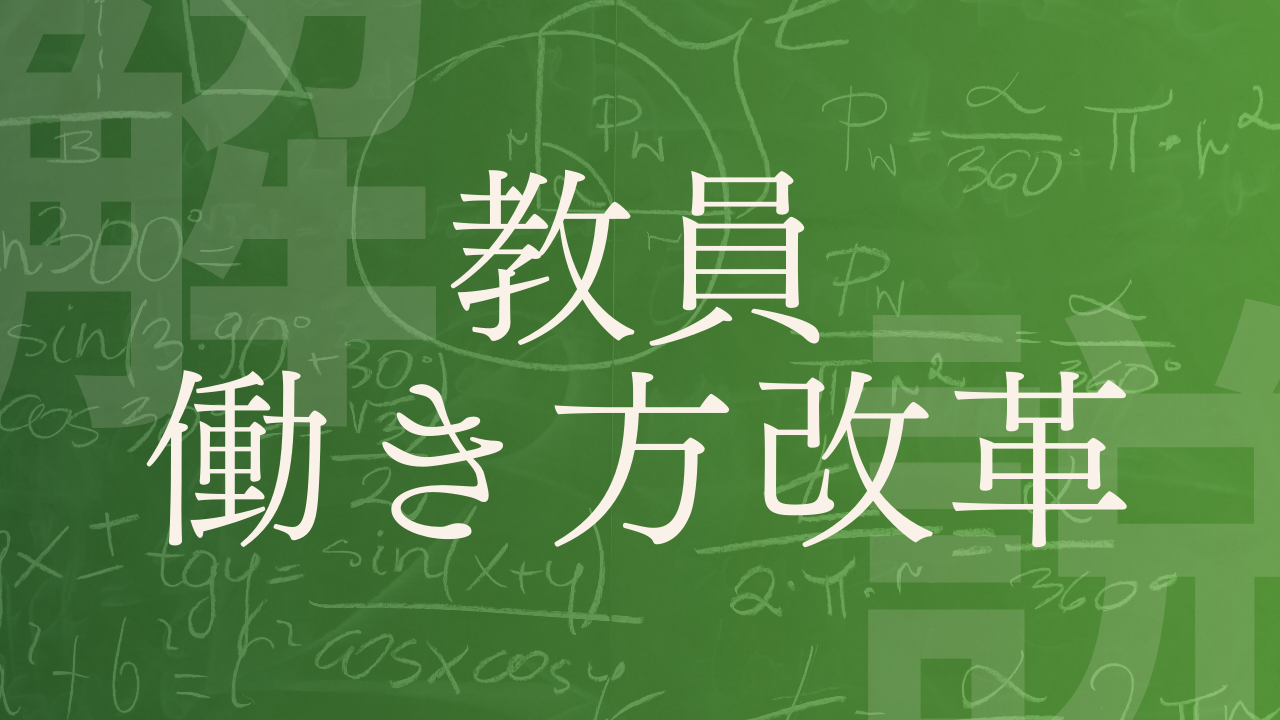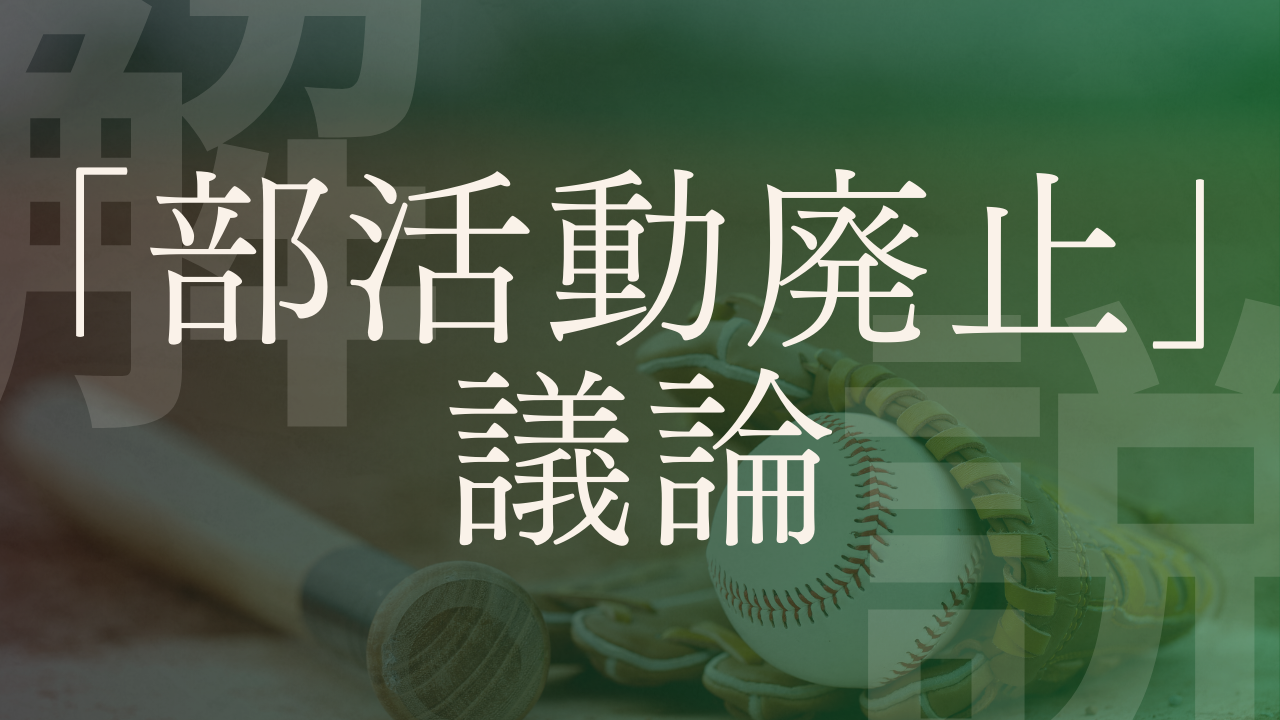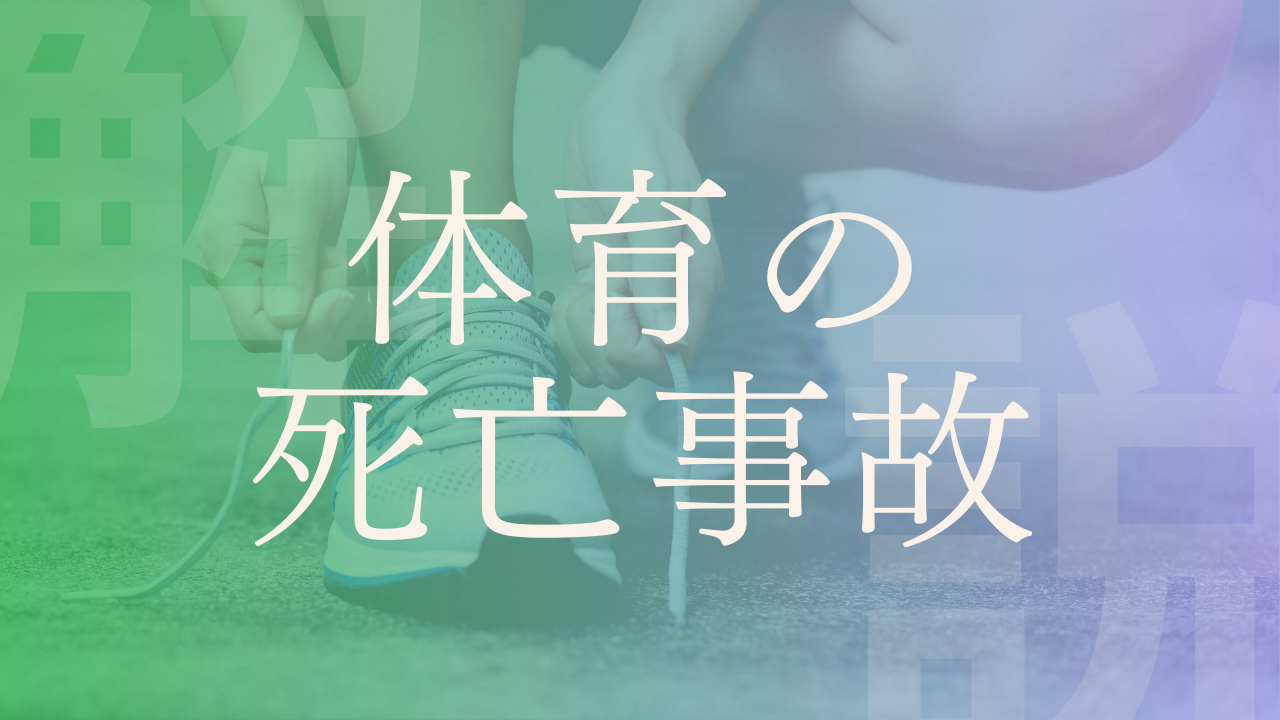【主権者教育】意味ない?目的・日本と海外の取り組み事例・課題など

【若者の低投票率】主権者教育とは?ねらいやデメリットを考える
主権者教育が注目されている背景には、2015年6月に公職選挙法が改正され、18歳選挙権の導入があります。若者の政治的リテラシーや政治参加意識を育む主権者教育とはいったい何なのか、現状はどうなっているのか、徹底解説します。
主権者教育とは?
まずは、話題になっている主権者教育とはどういったものなのか、そもそも主権とは何かを考えていきます。
国民主権の原則
日本国憲法では、国民主権の原則があります。これは、国のあり方を最終的には国民が決めることを指しています。
国のあり方を最終的に決める人の事を主権者と呼び、主権者としての意識やリテラシーを育む事を主権者教育と呼びます。
主権者教育とは?
文部科学省の「主権者教育の推進に関する検討チーム」によると、主権者教育を単に政治の仕組みを習得させるにとどまるのではなく、社会の中で自立し、他者と連携しながら課題解決を主体的に担う力を身につけさせることとしています。
すなわち、若者に投票に行かせることや低い投票率を上げることにとどまらず、政治や社会課題に対して幅広い合意形成をし、主権者自身が考え、意見を持ち、議論して決めていく教育だと言えます。
若者の低投票率と主権者教育の背景
近年、主権者教育が話題となる背景には若者の低投票率があります。
単に投票率をあげることに対しては、賛否両論ありますが、まずはデータを見てみましょう。
2022年の衆議院議員選挙のデータを見ると、各年代別の投票率は以下のようになります。
| 10代 | 43.21% |
| 20代 | 36.50% |
| 30代 | 47.12% |
| 40代 | 54.72% |
| 50代 | 63.34% |
| 60代 | 70.41% |
| 70歳以上 | 74.17% |
10代、20代、30代が50%を切っているのに対し、60代以上は70%以上の投票率があります。このデータからだけでも、高齢者よりも若者は投票に行かない割合が高いことが見て取れます。
主権者教育の課題・デメリットは?
主権者教育には、主権者として物事を決めていく能力を育むといった社会的意義がある一方で、課題も存在します。
入試との兼ね合い
選挙権を獲得する18歳は、多くの学生が大学入試を受けるタイミングでもあります。近年においては、主権者教育は入試との関係が低いものと受け止められているため、兼ね合いが難しいといった課題があります。どうしても、入試に直結する勉強を優先する傾向があります。
しかし、「公共」科目の導入など、入試科目に主権者教育に関連する内容を取り入れるなど、主権者教育と入試との関連性を持たせるなどの動きもあります。
政治的中立性の担保が難しい
政治教育・主権者教育を行っていく上で重要なことは政治的中立性を担保することです。実際に教育基本法第14条には、「法律に定める学校は、 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」と規定されています。
参考:教育基本法|https://www.mext.go.jp/bmenu/kihon/about/mext00003.html
政治的中立性を重視するあまり、実態のイメージがわかず主権者意識を持てないといった指摘もある一方で、主権者教育の名のもとに教員による政治的な誘導などの懸念もあります。
主権者教育の現状と実践例
主権者教育は、どこまで進んでいるのでしょうか?その現状と実践例をみていきます。
主権者教育の現状
現状の高校教育の中では、主権者教育に関する副教材(私たちが拓く日本の未来)の作成と活用、高校生の政治活動参加に関する通知の見直し、科目「公共」の導入への動きなどが進められています。
参考:国立国会図書館「主権者教育をめぐる状況」|https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo9624093po_0889.pdf?contentNo=1
主権者教育の取り組み例
主権者教育の取り組みには、模擬投票・模擬選挙の実施や、税務署や議員と連携した出前授業、模擬議会・若者議会などがあります。
参考:総務省「主権者教育の取組事例」https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/shukenshakyoiku/torikumijirei.html
海外での主権者教育の事例
では、ここからは海外の主権者教育の事例を見ていきましょう。
実際に候補者や政党に投票する模擬投票「学校選挙」|スウェーデンの事例
スウェーデンでは、過去50年間国政選挙の投票率が80%を下回ったことがなく、その要因の一つには主権者教育が挙げられます。
民主主義に対して手厚く教えるとともに、いじめや差別・薬物問題などの問題解決を実践的に考えるなど、生徒自身で判断することが尊重されています。
実際に、基礎学校中学年(日本でいう小学5,6年生ぐらい)の子どもが学校の課題として、各政党の主張や立場を調べています。また、各党の代表を招いた討論を行うなど、政治家と触れる機会も多いです。
学校選挙といって、模擬選挙に力を入れているのも特徴的です。学校単位で実際の選挙に合わせて候補者や政党を選ぶ形で行われます。
実際的知識を身につける「政治教育」|ドイツの事例
ドイツの主権者教育は、政治に関する実際的知識を学ぶ「政治教育」が一般的です。主権者教育を担う「連邦政治教育センター」が設立され、以下の3つの役割を果たしています。
①市民に対して政治とは何かを伝える
②市民に民主主義を促す
③市民に政治参加することや参加することへの興味を促す
連邦政治教育センターの理念には、「寛容性」と「多元主義」が定められており、多様な意見の中で決断していく能力を養うことを重視されています。
まとめ
主権者教育には、若者の低投票率といった背景の中、推進が進められる一方で、政治的中立性等の課題もあります。学校教育は、どうあるべきか今一度考え直すことが重要です。
参考文献
- 総務省「主権者教育の推進に関する有識者会議 とりまとめ」|https://www.soumu.go.jp/main_content/000474648.pdf
- 文部科学省「「主権者教育の推進に関する検討チーム」最終まとめ~主権者として求められる力を育むために~」|https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/1372381.htm
- 総務省「目で見る投票率」|https://www.soumu.go.jp/main_content/000696014.pdf
- 明光プラス「主権者教育とは?意味や目的とこれからの受験への関わりについて簡単に解説」|https://www.meikogijuku.jp/meiko-plus/other/20220215.html#
- 教育基本法|https://www.mext.go.jp/bmenu/kihon/about/mext00003.html
- 奈良県「主権者教育を行う上での留意点等」|https://www.pref.nara.jp/secure/292962/%E7%95%99%E6%84%8F%E7%82%B9%E7%AD%89.pdf
- 総務省「主権者教育の取組事例」|https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/shukenshakyoiku/torikumijirei.html
- 国立国会図書館「主権者教育をめぐる状況」|https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo9624093po_0889.pdf?contentNo=1
- SYNODOS「スウェーデンの主権者教育と政治参加」https://synodos.jp/opinion/international/22601/
- 18歳選挙権&主権者教育の専門家 西野偉彦「海外に学ぶ「主権者教育」とは~ドイツ~」|https://takehikonishino.net/germany1/