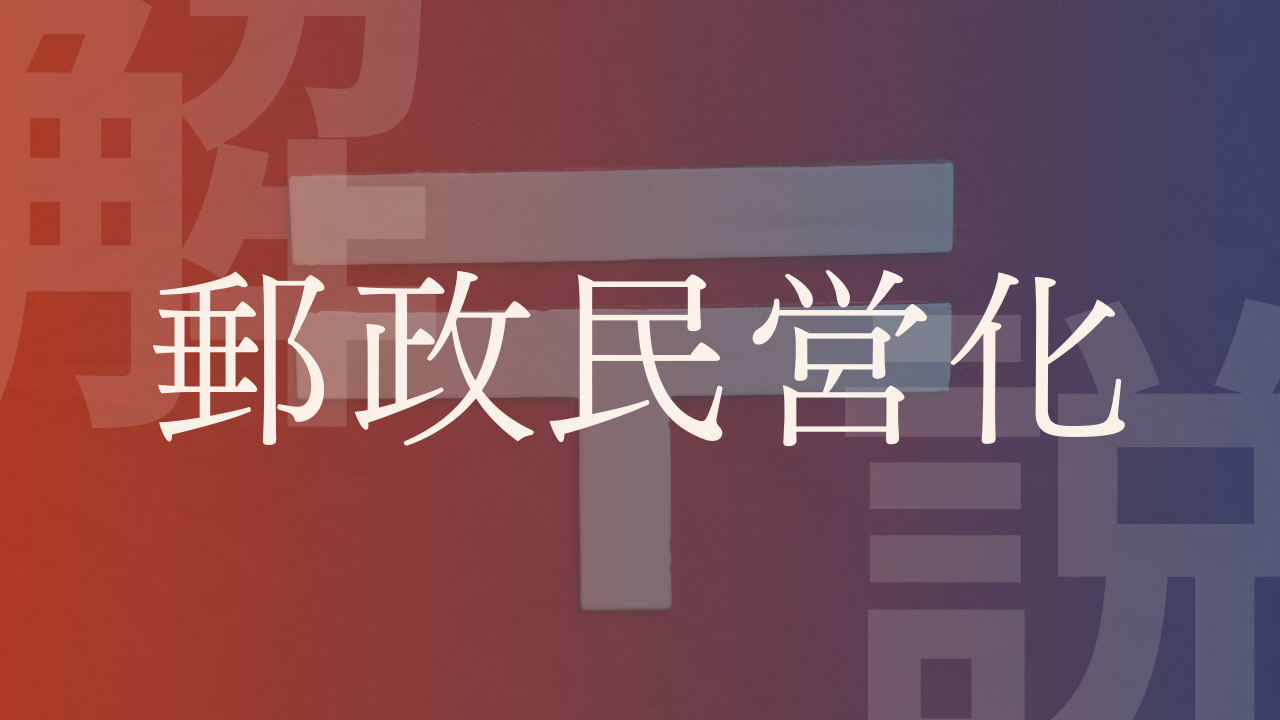【ライドシェア】解禁議論やメリット・デメリット、海外事例・問題点を解説!

ライドシェアとは?怖い?白タク?わかりやすく解説
この記事では、近年注目を集めているライドシェアサービスについて解説します。
ライドシェアの仕組みや特徴、メリット・デメリットを理解することで、新しいモビリティサービスの可能性が分かります。
ライドシェアとは?
ライドシェアとは、個人の自家用車をタクシーのように使って、他の人を有償で移動させるサービスのことです。近年、スマートフォンアプリの普及に伴い、ライドシェアサービスが世界各地で注目を集めています。
定義と仕組み
ライドシェアの仕組みは、ドライバーとなる個人がアプリに自身の車両情報を登録し、配車を希望する利用者にマッチングされます。
利用者はアプリ上で目的地を入力すると、近くの配車可能なドライバーが表示されます。事前に料金も確認できるため、利用者は安心して乗車できます。
白タクとの違い
現行制度の中で、営業許可を持たず、2種免許を持たない白のナンバープレートの車でタクシー業務をすることは、白タクと呼ばれてきました。
白タクは違法行為となっています。
ライドシェア解禁後も、誰でもタクシー業務が行えるようになるというわけではなく、法律の定める一定の条件を満たし登録されている事業者のみが事業を行えるようになります。
しかし、2種免許を持たないドライバーが参入するという意味では実質白タクと同じではないかという議論もあります。
ライドシェアの歴史
ライドシェアの概念自体は古くからありましたが、デジタルプラットフォームの普及によって新たな形で広まりました。2009年に米国のUberが創業し、2012年にはLyftが参入しました。その後ライドシェアサービスは世界各国に広まり、2023年現在では多くの国で事業が行われています。
主要なライドシェアサービス
代表的なライドシェアサービスとしては、Uber、Lyft、DiDi(中国)、Grab(東南アジア)、Ola(インド)などがあげられます。日本国内では2022年に政府が解禁に踏み切り、現在は主に地方部を中心に実証実験が行われています。
ライドシェアのメリット
ライドシェアサービスには多くのメリットがあり、経済面、環境面、利便性の面で従来のモビリティと比べて優れた特徴を持っています。
経済的メリット
ライドシェアは自家用車の活用により、新車の購入や人件費などの固定費用を抑えられます。そのため利用者への安価な料金設定が可能で、タクシーよりも割安な移動手段として注目されています。ドライバーにとっても、空き時間に収入を得られる点が魅力的です。
環境へのメリット
ライドシェアは自家用車の稼働率を上げることで、新車の購入抑制やより効率的な交通手段の実現に寄与します。さらに、電気自動車の活用によってCO2排出量の削減にもつながります。環境対策として、都市部での導入が期待されています。
利便性の向上
スマホアプリによる簡単な配車リクエストと決済、リアルタイムでの車両位置確認などにより、利用者の利便性が大幅に向上します。また、供給が需要に合わせて柔軟に変更できるため、従来の交通サービスよりも待ち時間が短縮できます。
ライドシェアのデメリット
一方で、ライドシェアサービスには様々な課題や懸念もあります。セキュリティ面での不安や規制の問題、雇用形態をめぐる議論など、解決すべき点が多くあります。
セキュリティ上の懸念
ライドシェアでは一般ドライバーが営業するため、利用者の安全性確保が最大の課題となっています。事故の責任範囲や未成年・女性の利用時のリスク管理など、さまざまなセキュリティ対策が求められます。
規制の問題
日本を含む多くの国で、ライドシェアサービスは既存のタクシー業界との規制の違いから、法的にグレーゾーンにあります。公平なルール作りのため、政府による新たな規制の整備が必要不可欠です。
従業員の処遇
主要ライドシェア企業のほとんどでは、ドライバーを個人事業主として雇用しています。そのため報酬や労働環境の改善を求める声があり、雇用形態の見直しに向けた議論が各国で行われています。
日本でのライドシェア議論と現状
日本国内でもライドシェアサービスの導入に向けた議論が進んでいます。現状の規制や課題、今後の展望について解説します。
日本における規制
日本では、従来の道路運送法の下で一般のドライバーによる有償の旅客運送が禁止されていました。しかし2022年6月に改正が行われ、ライドシェアの解禁に踏み切りました。有償運送が可能となる一方で、車両要件や運転者要件などが定められています。
ライドシェア導入をめぐる議論
大都市部でのライドシェア導入は地方より遅れています。タクシー業界からの反対運動や、交通渋滞への影響などが懸念されているためです。一方、地方部では過疎化対策としての導入に前向きな自治体が多数あります。
今後の展望
2023年現在は主に地方部での実証実験が行われていますが、今後はグレーゾーンを解消する法整備が進められる見込みです。円滑な導入に向けて、交通システム全体の最適化や補完的なインフラ整備なども必要とされています。
海外事例
世界各国では、ライドシェアサービスの普及状況や規制、課題が様々です。主要国の動向を確認しましょう。
アメリカでのライドシェア普及
ライドシェアの発祥の地であるアメリカでは、Uber、Lyftなどのサービスが大都市部を中心に急速に普及しています。一方で各州による規制の違いや、ドライバーの労働環境をめぐる訴訟が発生しています。
ヨーロッパでの取り組み
欧州では、Uber禁止の判断が出るなど国によって対応が分かれています。
一方でライドシェアの合法化に向けた動きもあり、ロンドンなどの大都市部では新たなサービスが次々と参入しています。
新興国での広がり
新興国市場でもライドシェアサービスは拡大の一途をたどっています。中国のDiDiやインドのOla、東南アジアのGrabなど、地場企業が積極的にサービスを展開しています。一方で、交通インフラの未整備や治安対策など、各国固有の課題も存在します。
まとめ
ライドシェアは新しいモビリティサービスとして、経済性や利便性、環境への配慮など様々なメリットがあります。一方で課題もあり、規制や安全性の議論が必要です。
海外の動向や国内の議論の状況を踏まえ、サービス改善やルール作りが重要となります。
参考になるサイト
- チューリッヒ保険|ライドシェアとは。日本の普及状況。カーシェアリングとの違い|https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-whatis-rideshare-takeup/
- 国土交通省|「移動難民」の問題について|https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001722468.pdf
- 内閣府ホームページ|ライドシェアドライバーに関する調査結果報告|https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_05local/240411/local02_02.pdf