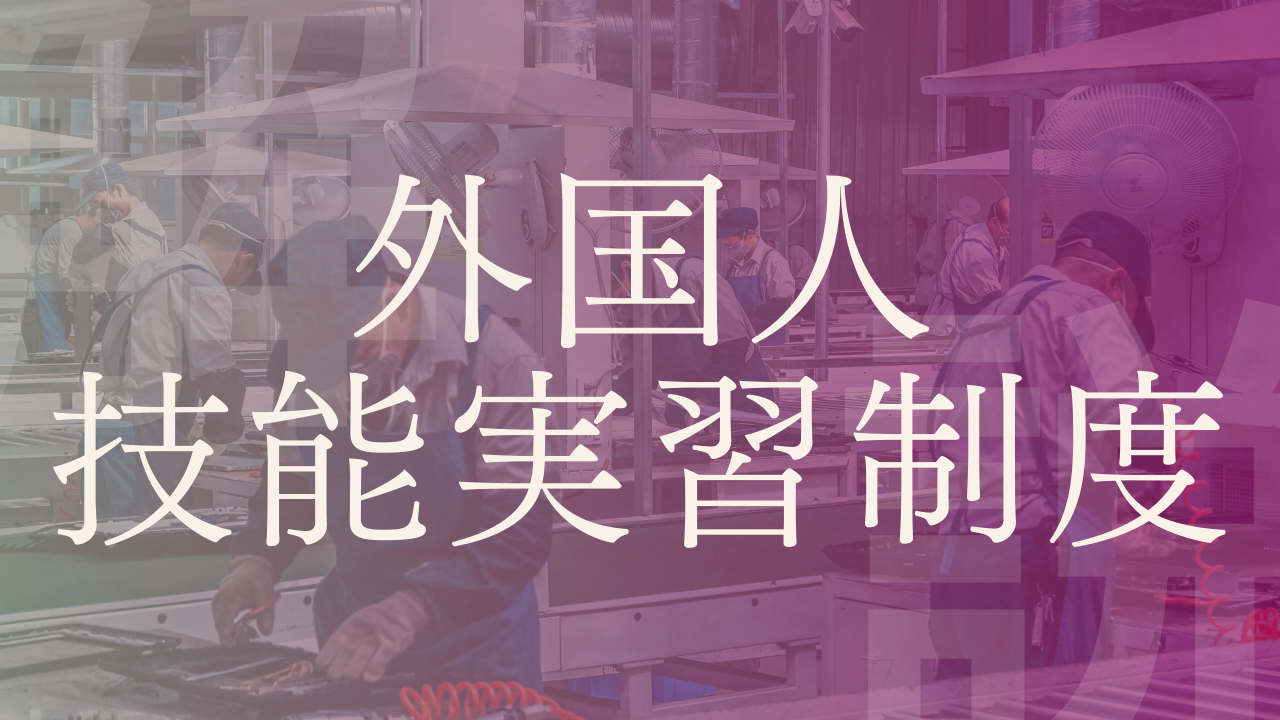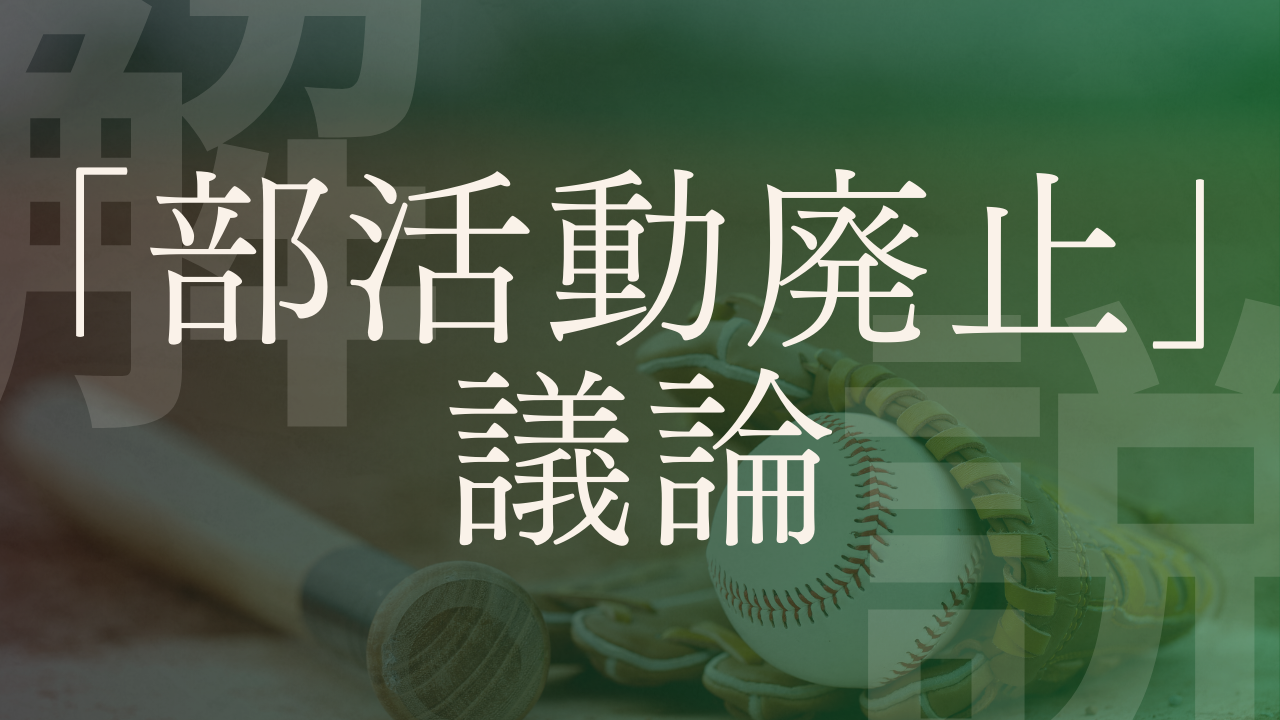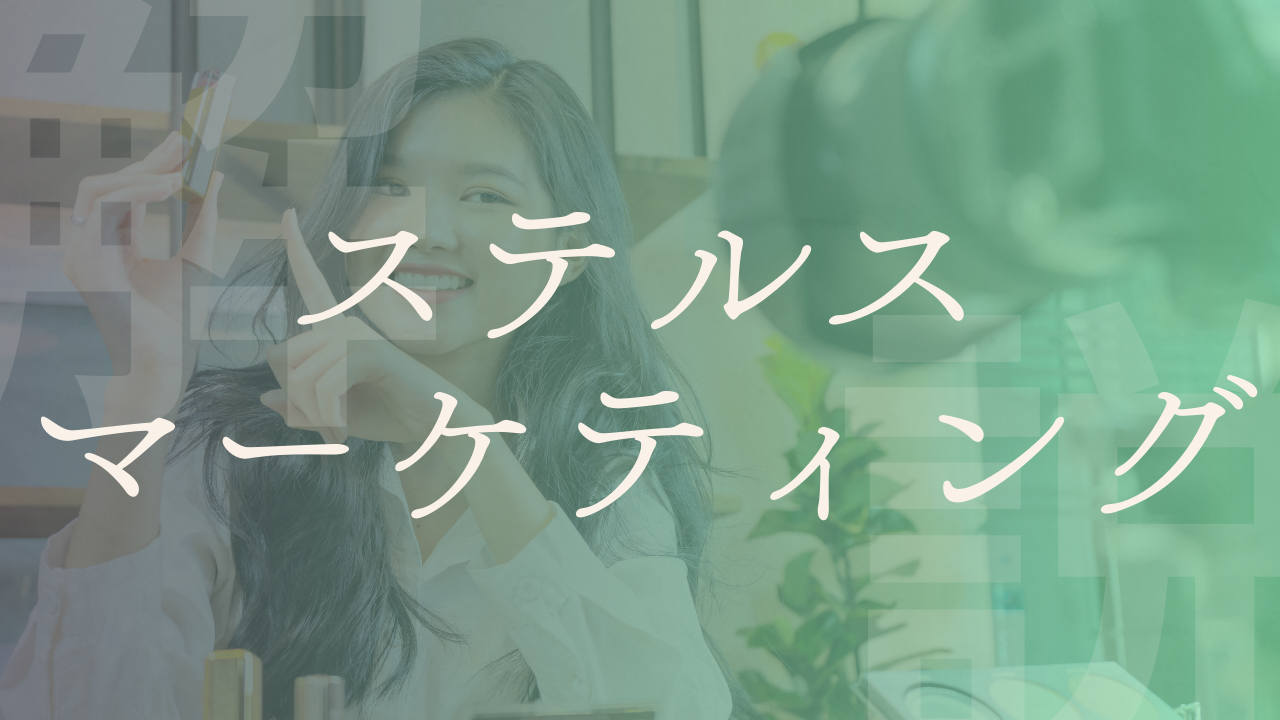【食品添加物とは?】目的用途や役割、メリットを解説!どんな危険性がある?

食品添加物とはどういうものかわかりやすく解説
食品添加物と聞くと何か体に悪いものといったイメージを抱きがちです。
しかし、食品添加物の使用に関しては厳しい基準が国によって定められています。さらに食品添加物は私たちの日常生活と密接な関連もあります。
食品添加物とは何かについて考えていきましょう。
食品添加物の目的
食品添加物とは何が該当するのでしょうか。
厚生労働省のサイトでは「保存料、甘味料、着色料、香料など」と定義されています。さらに「食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用される」とも記されています。添加物は食品に対して、腐らないように保存料を入れるといった目的がまずイメージされます。しかしそれ以外にも、味をつける、色をつけるといった目的でも使われており広い用途に仕様されていると言えます。
食品添加物の種類
先の厚生労働省のサイトによれば、日本で使用が認められている食品添加物は「指定添加物、既存添加物、天然香料、一般食品添加物」であると記されています。
指定添加物はカビの繁殖を防ぐソルビン酸や、ガムなどに含まれる人工甘味料のキシリトールがあります。既存添加物は、1995(平成7)年に食品衛生法改正を受けて添加物の定義が広まりましたが、それ以前から広く存在していたもので、黄赤青を出せるクチナシ色素や、赤ワインの渋みなどに使われるタンニンなどが該当します。天然香料はバニラ香料、カニ香料、一般食品添加物はウコンや寒天などよく知られた食品の名が並びます。
食品添加物は原則として食品に添加された場合は、すべて表示しなければならないと定められています。表示は物質名で記載され、保存料や甘味料はその用途を併記するように定められています。食品のパッケージを見れば、どういった食品添加物が含まれているかがわかるようになっています
安全性の確保
食品添加物は、食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って使用が認められています。そこで気になるのは食品添加物を摂取して健康に問題はないのかという点です。
食品添加物は国民一人あたりの摂取量を調査するなど安全の確保に務めています。実験動物などを用いてADI(1日接種許容量)が設定され、この基準を超えないように使用基準が設定されることで安全性が確保されています。
食品添加物がないと生活はどうなる?
食品添加物に関しては何となく「体に悪いのではないか」「長く摂取を続けていると有害なのではないか」といったイメージがあります。
味の素のウェブでは、食品添加物は食品の腐敗や食中毒を防ぐためのものです。さらに産地や地域に関係なく便利な食品添加物が大きな役割を果たしていると指摘されています。
もし食品添加物がなかった場合には、現在のようにスーパーやコンビニエンスストアなどで、食べたいものをいつでも買えるといった便利な生活は実現しません。食品の保存期間も短くなります。現在よりも不便な生活となってしまう可能性は高いと言えます。
さらに食品添加物には食品の嗜好性を向上させる目的もあります。食品に彩りを添えたり、色や風味を高める効果もあります。味や食感といった要素の実現にも食品添加物が必要です。
まとめ
食品添加物は保存料、甘味料、着色料など食品の加工・保存のために使われる成分を指します。法律で使用できる添加物が定められており、さらに食品安全委員会による評価、動物実験を経て人間が摂取しても問題ない量が定められています。
食品添加物には何となく体に悪いものといったイメージがありますが、食品の腐敗や食中毒を防ぐものであり、便利な食生活の実現に貢献しているものだと言えます。食品添加物に関しては何となくのイメージによるものではなく、正しい理解が必要です。
参考文献
- 厚生労働省|医療・健康添加物|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/index.html
- 厚生労働省|よくある質問(消費者向け)|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/qa_shohisya.html
- 味の素株式会社|ホントに知っていますか? 食品添加物のこと|https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/know/additives_01.html
- 三栄源エフ・エフ・アイ|食品添加物の基礎知識|https://www.saneigenffi.co.jp/whats/