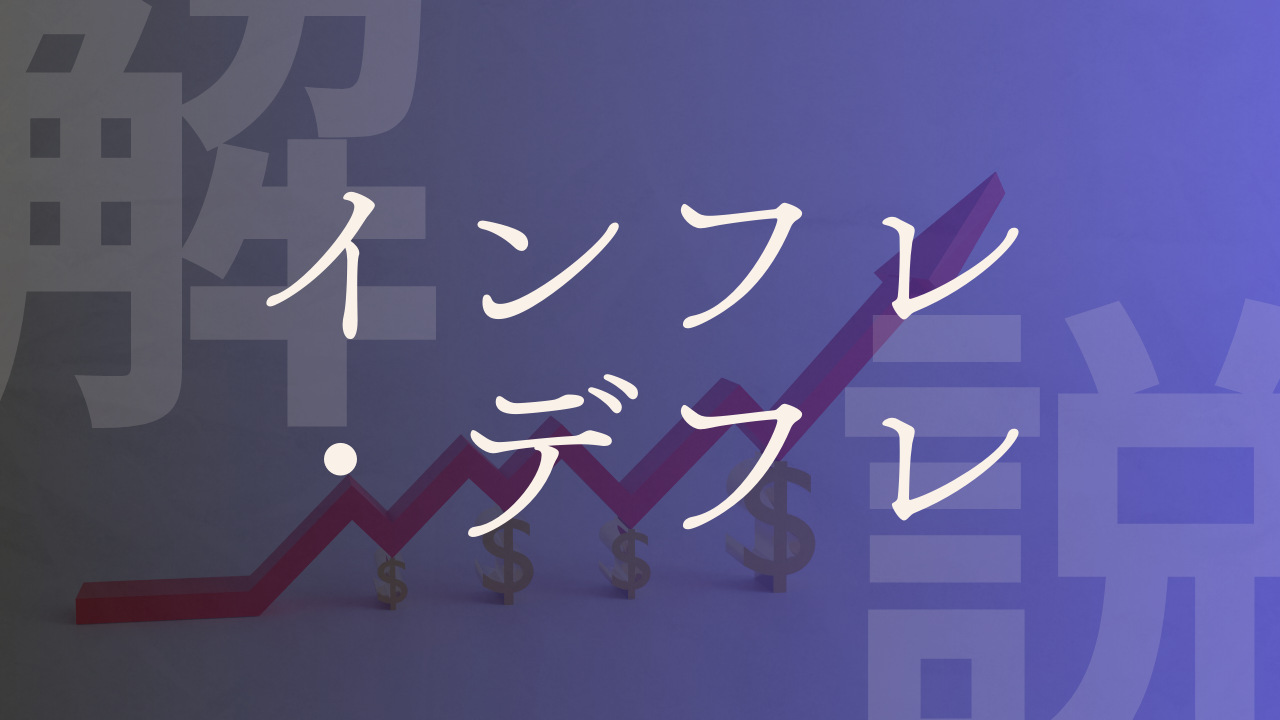【労働組合】法律・歴史・組織率は?ない会社はある?

【解説】労働組合の現代の役割はなに?労働三権などの権利と実態は?
日本の労働組合は労働組合法に基づき、厚生労働省が所管している組織です。組合加入率は2023年には16.3%であり、地方や会社レベルでの団体交渉が主に行われています。
この記事では日本の労働組合について理解を深めることで、労働組合の歴史、組織率の把握、企業の労働組合の役割、法律に関する知識を得ることができます。
労働組合とは?
労働組合は、労働者が団結して結成し、労働条件の改善や労働者の権利を守るために活動する組織です。労働組合は労働法に基づき組織され、労働者の代表として企業や政府との交渉を行う役割を果たします。
労働者の権利保護
日本国憲法第28条に基づき、労働者には「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」という労働三権が認められています。
- 団結権:労働者が労働組合を結成する権利。
- 団体交渉権:労働者が使用者と団体交渉を行う権利。
- 団体行動権:労働者が団体として行動する権利。
労働組合は労働者の権利を保護するために組織されるのです。
労働条件の交渉
労働組合は労働条件の交渉において重要な役割を果たします。具体的には団体交渉権を行使して、労働者の代表として、企業との労働条件の交渉を行います。
労働組合は労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関する交渉を行うのです。団結して労働条件に関する交渉を行うことで、労働条件の改善を企業に促すという重要な役割を担っているのです。
労働組合の歴史
労働組合は明治時代の労働運動をきっかけに誕生しました。戦後には日本労働組合総同盟や全日本産業別労働組合会議などの全国中央組織が結成され、労働組合運動が発展したのです。
労働組合の歴史を知ることで、労働組合の存在意義を理解することができます。
日本の労働組合の起源
日本では明治時代に近代化の波が起こりました。富国強兵・殖産興業の政策によって多数の賃金労働者が生まれ、労働運動が始まったのです。
1897年には職工義友会が結成され、日本の労働組合の最初の組織となりました。高野房太郎・城常太郎・沢田半之助らがサンフランシスコで得た経験を活かして設立しました。
職工義友会が労働講演会を開催し、労働組合の結成を労働者に呼びかけたのです。
戦後の労働組合
戦後の日本は連合国軍の占領下におかれました。1945年には労働組合法が制定されました。
敗戦後1年目の1946年には13,622の労働組合が結成され、3,936,815人がそこに加入していたといいます。1947年には労働基準法が制定。労働省が設置されました。
労働者は敗戦直後の自分たちの生活を守るため、労働運動による闘争に立ち上がったのです。その結果、労働組合は次々と結成されました。
労働組合の組織率は?ない会社はある?
組織率とは労働者に占める組織労働者の割合です。つまり、労働者のうち何割が労働組合に所属しているかという割合のことです。労働組合の組織率の現状と組織率の変化要因について見ていきます。
労働組合の現状
日本の労働組合の組織率は、2023年時点で16.3%から16.5%の間だと推定されています。これは過去最低の水準であり、労働組合に所属する組合員は減少しているのです。組合数は2021年時点で23,761。労働組合員数は1,000万人を下回り、推定組織率は低下しています。
大企業においては組織率が高い水準となっていますが、中小企業では組織率が低くなる傾向があります。このように労働組合が存在しない企業は多数あるのです。
組織率の変化要因
組織率の変化要因は3つあります。
産業構造の変化
近代の日本ではサービス産業に従事する労働者の割合が増えました。日本の産業構造が変化し、労働組合の組織率の低下に影響を与えています。
雇用構造の変化
女性労働者やパートタイム労働者の増加により、雇用構造が変化しました。雇用構造の変化が労働組合の組織率の低下に影響を与えています。
既存組合の活動
近代の産業構造、雇用構造の変化は既存の労働組合の活動に変化を与えました。労働者が求めるニーズは変化して、労働組合の運営や活動方針が変化していったのです。その結果、労働組合の組織率は低下していきました。
労働組合の現在の役割は?
現在の労働組合は労働条件の交渉、労働者の権利擁護といった基本的な活動に加え、社会的・政治的活動も行っています。労働組合の組織率は低下していますが、労働者の権利を守る役割を果たしていることには変わりはありません。
労働者の権利と福利厚生の向上
労働組合は3つの観点から労働者の権利と福利厚生の向上を目指して活動しています。
労働条件の交渉
労働組合は春闘と呼ばれる賃金アップの交渉や労働条件の改善交渉を通じて、労働者の権利と福利厚生の向上を図っています。
労働環境の改善
働く環境をより良くし、労働者が働きやすい環境を作るのも労働組合の役割です。安全対策の推進を企業に促すのも重要な活動です。
福利厚生制度の整備
時代に合わせた福利厚生制度の整備を進めるように企業に促すことも労働組合の役割です。
労使間の調整
労働組合は雇用者と労働者の間に立ち、互いの意見を擦り合わせ、より良い労働環境を作ることが重要な役割です。雇用者には事業の運営維持・規模拡大を目指したい、労働者にはより良い労働、生活環境を得たいという考えがあります。
その互いの意見を調整するために労働組合は組織されているのです。
労働組合の作り方
労働組合は4つの手順に沿って準備をすることで結成することができます。
自主的な団結
労働組合は労働者による自発的な団結ができます。
組合規約の作成
労働組合の活動方針や予算などを定める文書を作成します。
組合の目的と活動方針の明確化
作成した組合規約に基づいて、組合の目的と活動方針を明確にします。
結成大会の開催
組合の設立に向けて結成大会を開催します。
手続きの簡略化と活動方針の提供
労働組合を作る上で手続きの簡略化と明確な活動方針の提供が重要です。
手続きの簡略化
労働組合の設立を促進する上で、労働者が労働組合に加入しやすい環境を整備することが大切です。
活動方針の提供
活動方針をしっかりと労働者に伝えることで、労働者は労働組合に入るメリットを理解することができます。
労働組合に加入する意味とメリットの説明
労働組合は加入者を集める必要があります。そのためには労働組合に加入する意味とメリットを労働者に説明することが重要です。
労働組合に加入することで労働者は法的な保護が得られ、労働条件の交渉ができ、組織として活動することで企業と交渉する力を得ることができます。そして、企業と労働条件、環境面での交渉を行うことで、労働者はより良い労働をすることができ、モチベーションや離職防止につながります。
企業にとっても労働者にとっても労働組合はメリットがある組織なのです。
まとめ
日本の労働組合は労働組合法に基づき、厚生労働省が所管している組織です。労働組合は、労働者が団結して結成し、労働条件の改善や労働者の権利を守るために活動をします。
労働組合は明治時代の労働運動をきっかけに誕生しました。近年は社会構造の変化により組織率は低下しています。しかし、いつの時代でも労働組合は労働者の権利を守るために活動をしているという重要な役割を果たしています。
参考になるサイト
- 厚生労働省|労働組合|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/roudoukumiai/index.html
- 連合(日本労働組合総連合会)|日本労働組合総連合会(連合)ホームページ|https://www.jtuc-rengo.or.jp/
- 連合(日本労働組合総連合会|労働組合ができることって?|https://www.jtuc-rengo.or.jp/aboutrengo/toall/tradeunion.html
- jeju.or.jp|労働組合の役割 | 組合づくり・相談 – 電機連合|https://www.jeiu.or.jp/union/merit/
- 厚生労働省|日本の労働組合の成立ち|https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000zp5n-att/2r9852000001115x.pdf