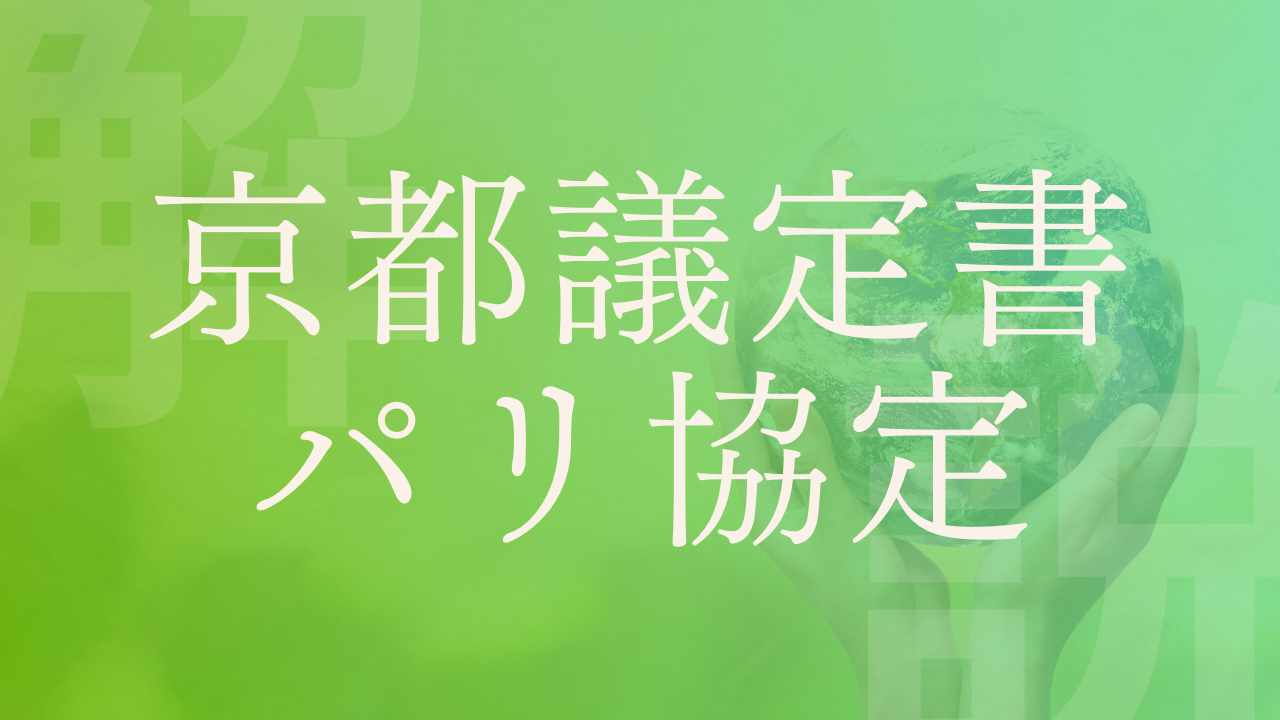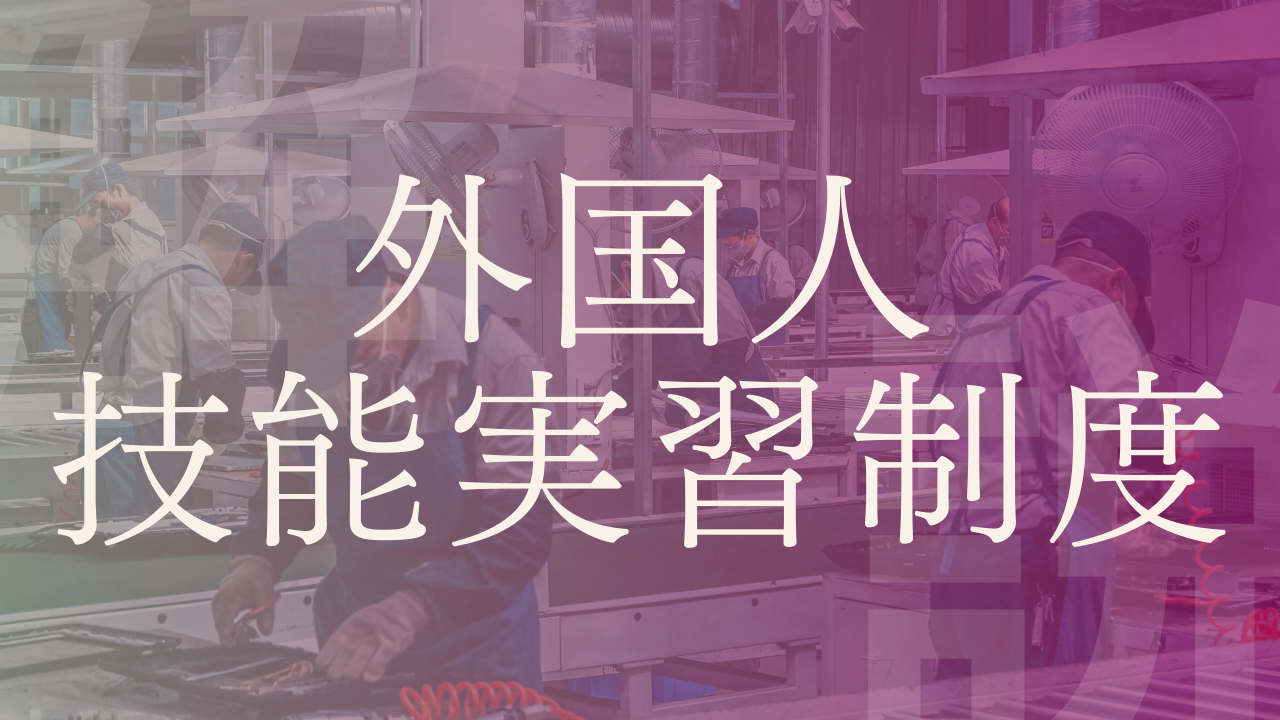【経済格差】南北問題・南南問題とは?日本や世界の支援や現状を解説

南北問題・南南問題を考える。解決策はあるのか?
みなさんは南北問題について聞いたことがありますか?この記事では、南北問題や南南問題について、どんな問題なのか、またなぜそうした問題が生じたのかについて、簡単に説明します。
南北問題とは?
南北問題とは、北と南の国々の間にある経済格差を示すものです。英語ではGlobal North and Global South や North-South Dvideといわれ、地球上の国をざっくり二つに分けると、先進国の多くが北半球に、発展途上国の多くが南半球に位置していることから、このように呼ばれるようになりました。
なぜ南北で経済格差が生まれたの?
1950年代頃までは、世界のほとんどの国が宗主国か植民地として植民地関係にありました。19世紀後半から20世紀前半にかけて、イギリス、フランス、ロシア、アメリカなどの国は強大な軍事力をもち、世界中で植民地を獲得することで国力を競い合っていたのです。植民地は、宗主国にとって資源・原料の供給地であり、また大きな市場でもありました。たとえば、植民地ではサトウキビ、ゴム、綿などの原料が大量に生産され、安く宗主国に買い取られます。宗主国は、そうして安く手に入れた原料で工業製品をつくり、できた製品を国内外で売ることで大きな利益を得ます。製品を売る上で、人口の多い植民地は宗主国にとって魅力的な市場でもあったのです。一方で、単価の安い原料ばかりつくらされる植民地にとっては、貿易で得られる利益が小さい上に、特定の作物・原料ばかり生産するモノカルチャー経済となってしまい、天候や国際情勢に左右されやすい不安定な経済社会となってしまいました。
南北問題はいつから話題に?
南北問題が取り上げられるようになったのは、1960年代のことです。第二次世界大戦後、民族実決(自分の社会は自分たちの民族で決める、という考え方)が広まると、1950年代から60年代にかけて、アジア・アフリカ各地の植民地が次々と独立しました。しかし、独立後も植民地時代の影響は強く残ります。モノカルチャー経済によって産業の多様性は失われ、元宗主国をはじめとする先進国に経済的に搾取される構造となってしまったのです。こうした南北の国家間にある経済利益の対立を受けて、1962年には国連貿易開発会議(UNCTAD)が創設され、途上国の発展に先進国が協力することが目指されました。
南北問題から南南問題に!?
しかし、1970年代後半以降、新たに南南問題が課題となります。かつては南北間での経済対立だけであったのが、NIES(新興工業経済地域)と呼ばれる東アジアの国や、ブラジル、メキシコ、中東の産油国など、かつては途上国としてみなされていた南の国々の一部が急速に発展したことにより、南部の国家間でも経済格差が生まれたのでした。
南南問題が起こった背景は?
1960年代、工業化に成功した韓国・台湾・香港・シンガポール急速に経済発展を遂げ、いずれもアジアの国だったことから「アジア小四竜」とも呼ばれました。また、同時期に自国の天然資源を管理する権利を求める資源ナショナリズムが高まりました。特に石油資源の豊富な中東では、旧宗主国が産油の権利を握ったままであることに対して不満が高まり、自国の権利を取り戻した中東諸国は瞬く間に経済力を伸ばしました。これによって、工業化と天然資源のどちらにも当てはまらない国々との間に、経済格差が広がっていったのです。
現在の状況は?
各国の経済力を示す代表的な指標としてGDP(国内総生産)がありますが、2024年現在の各国GDPを比べると、上位10か国が世界のGDPの約7割を占めています。上から順にアメリカ、中国、ドイツ、日本、インド、イギリス、フランス、ブラジル、イタリア、カナダとなっており、いわゆる先進国とNIESがトップを独占している状態です。また、GDP下位にはアフリカや中南米の国々が集中しており、南北問題・南南問題のいずれの格差も現在まで残ったままだといえます。
地域間の経済格差解消への取り組み
では、こうした経済格差解消のため、どのような取り組みが行われているのでしょうか。
国連による取り組み
世界各国が国際的な問題に対処するために集う国連では、南北問題・南南問題の解消に向けて、これまで様々な取り組みが行われてきました。たとえば、1960年代は「国連開発の10年」と位置づけられ、途上国全体の経済成長率を5%に目標設定し、先進国による途上国への援助増額を決定しました。この目標は達成されたものの、途上国での急速な人口増加によって一人当たりの成長率は低くなってしまい、むしろ格差は拡大してしまいました。このため、1990年代までに第4次計画まで実施されました。また、国連貿易開発会議(UNCTAD)では、途上国が貿易の機会を最大限活用できるように、世界銀行からの資金協力を促したり、これまでに1万件以上の開発プロジェクトを支援したりしています。
日本の取り組み
日本の発展途上国への支援は、ODA(政府開発援助)を中心に行われてきました。ODAには大きく分けて、無償・有償の資金協力と技術協力があります。無償協力は、医療や保険、水、教育の提供など、生きていくうえで最低限必要な支援が中心で、特に開発の送れている後発途上国が対象となっています。一方で、有償協力は途上国に対して低利子で長期的にお金を貸し出すもので、インフラの整備などに使われることが多くなっています。技術協力では専門技術や知識を持った人を派遣し、現地の人々がそれらを身に着け、将来的に活用できるようになることを目的としています。こうしたODAの具体例としては、子どもたちへの給食の提供、母子手帳の配布、上下水道の整備などが挙げられます。
経済格差解消のために私たちにできることは?
ここまで、世界の格差問題に関して政府や国際機関による取り組みを紹介してきましたが、私たちにもできることはあるのでしょうか。
ボランティアに参加する
たとえば、ボランティアとして実際に現地に行って支援活動に参加するという方法があります。日本ではJICAの運営する海外協力隊が有名ですね。未経験者でも参加できる一般案件と、経験者を求めるシニア案件とがあり、期間も短期では1か月のものから、長期では2年のものまであります。活動内容も、教育支援から医療、経済、環境問題に関わるものなど多岐にわたり、自分の興味や経験に合わせて選ぶことができます。
支援団体を援助する
現地で支援活動を行うNGO・NPOを援助することで、間接的に貢献するという方法もあります。お金を寄付したり、団体が必要とする物資を送ったりすることもできます。日本で有名な団体としては、国際NGOプラン・インターナショナルや、国際協力NGOワールド・ビジョン・ジャパンなどがあります。現地に行かなくても気軽にできる貢献の一つですね。
まとめ
南北問題・南南問題は、歴史的な植民地支配とその後の独立によって生じた、経済格差の問題です。1960年代に南北問題が国際的に注目され始め、1970年代後半には南南問題も浮上しました。こうした経済格差に対して、国連や日本などの先進国はさまざまな支援策を行ってきましたが、私たち個人も、ボランティアや支援団体への援助を通じて、格差解消に貢献することができます。ぜひみなさんも興味のある分野について、どんな団体・活動があるのか調べてみてください。
参考になるサイト
- Spaceship Earth|南北問題とは?歴史的な原因と現状を打開するための解決策・世界と日本の取り組み|https://spaceshipearth.jp/north-south-issue/
- Spaceship Earth|南南問題とは?南北問題との違いと原因・現状、解決策を簡単に解説|https://spaceshipearth.jp/south-south-problem/
- 世界史の窓|南北問題|https://www.y-history.net/appendix/wh1703-001.html
- World Population Review|GDP Ranked by Country 2024|https://worldpopulationreview.com/countries/by-gdp
- 国連広報センター|国際の10年|https://www.unic.or.jp/activities/international_observances/decades/
- 国連広報センター|経済開発|https://www.unic.or.jp/info/un/un_organization/60ways/economic_dev/
- 日本経済教育センター|4 日本のODAの仕組み|http://www.keikyo-center.or.jp/old/tool/pdf/oda_2.pdf
- JICA海外協力隊|https://www.jica.go.jp/volunteer/