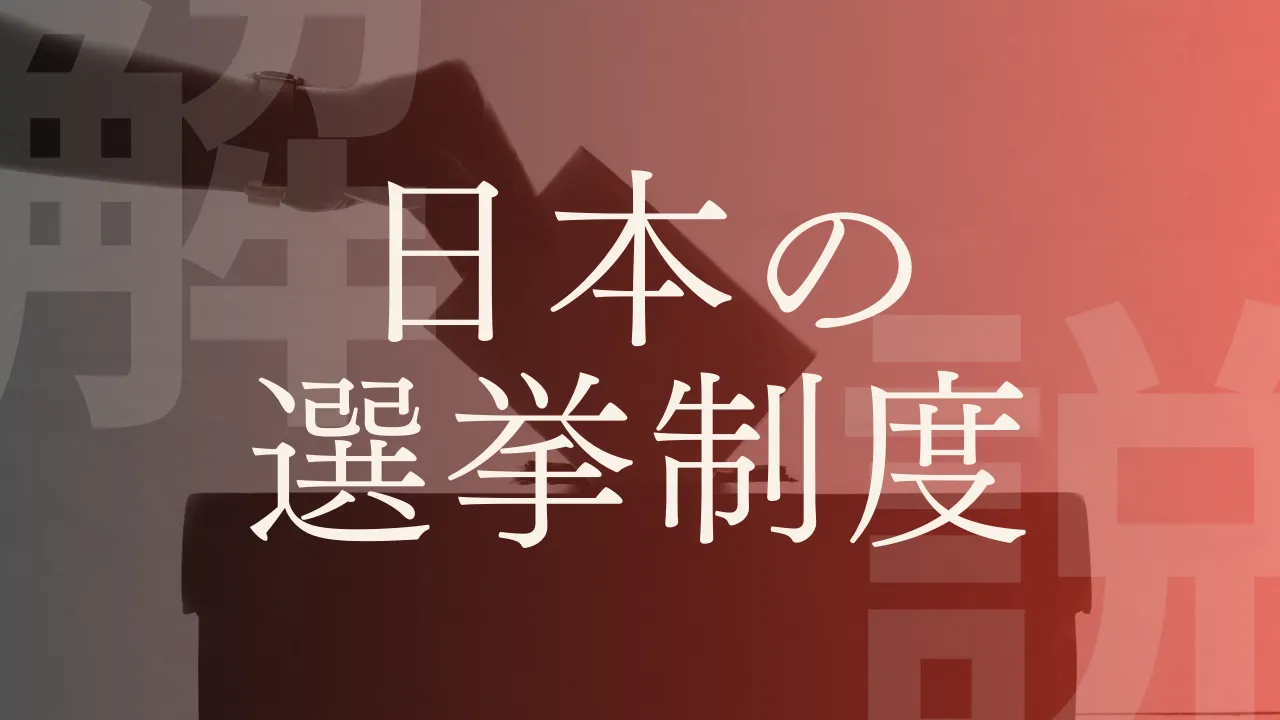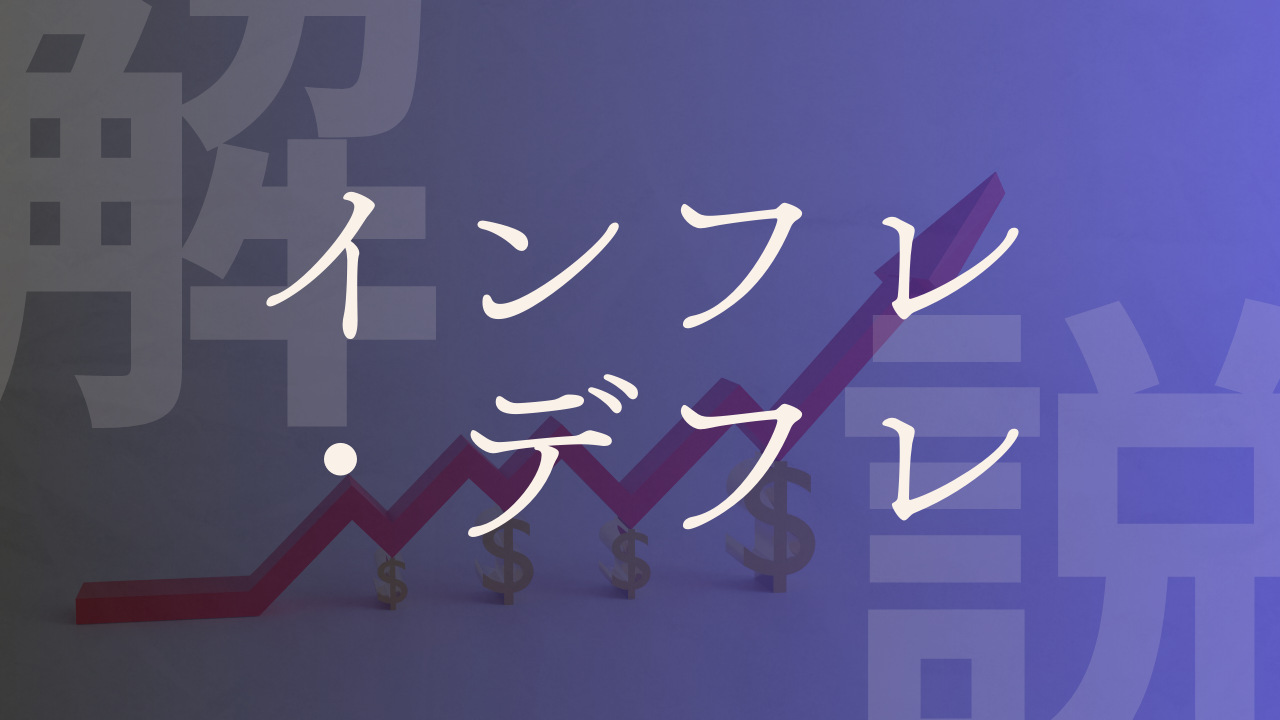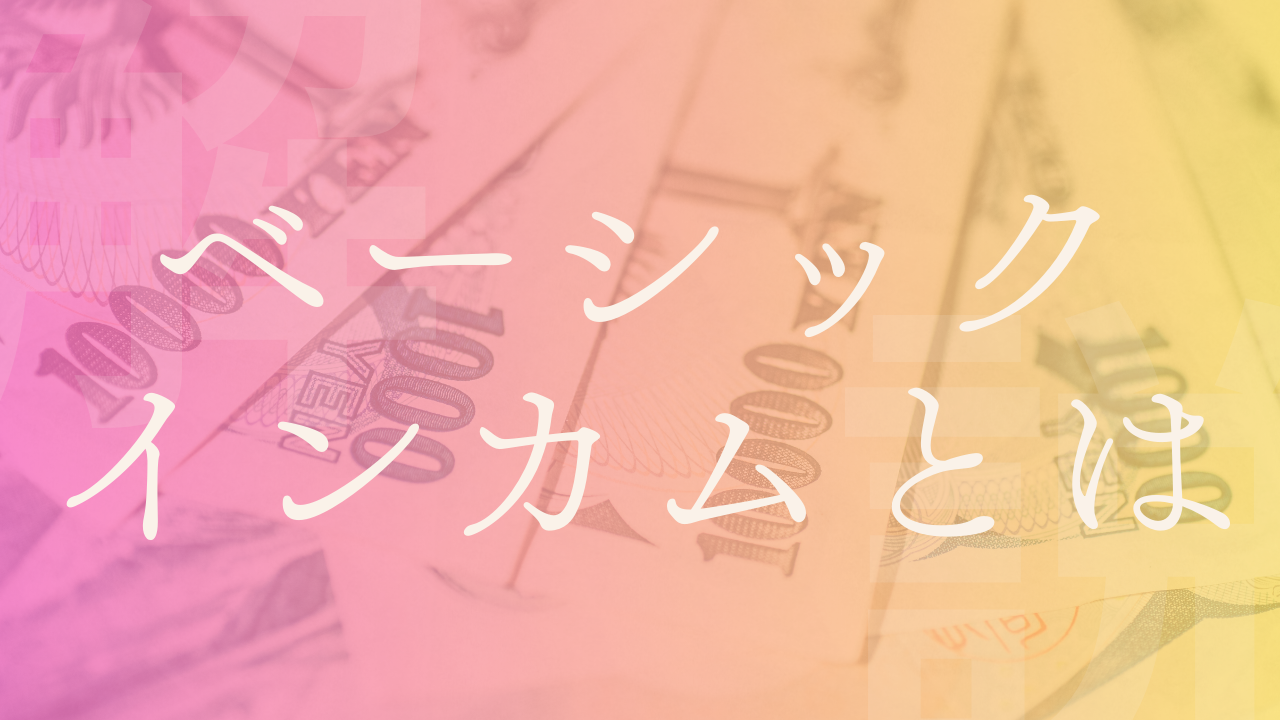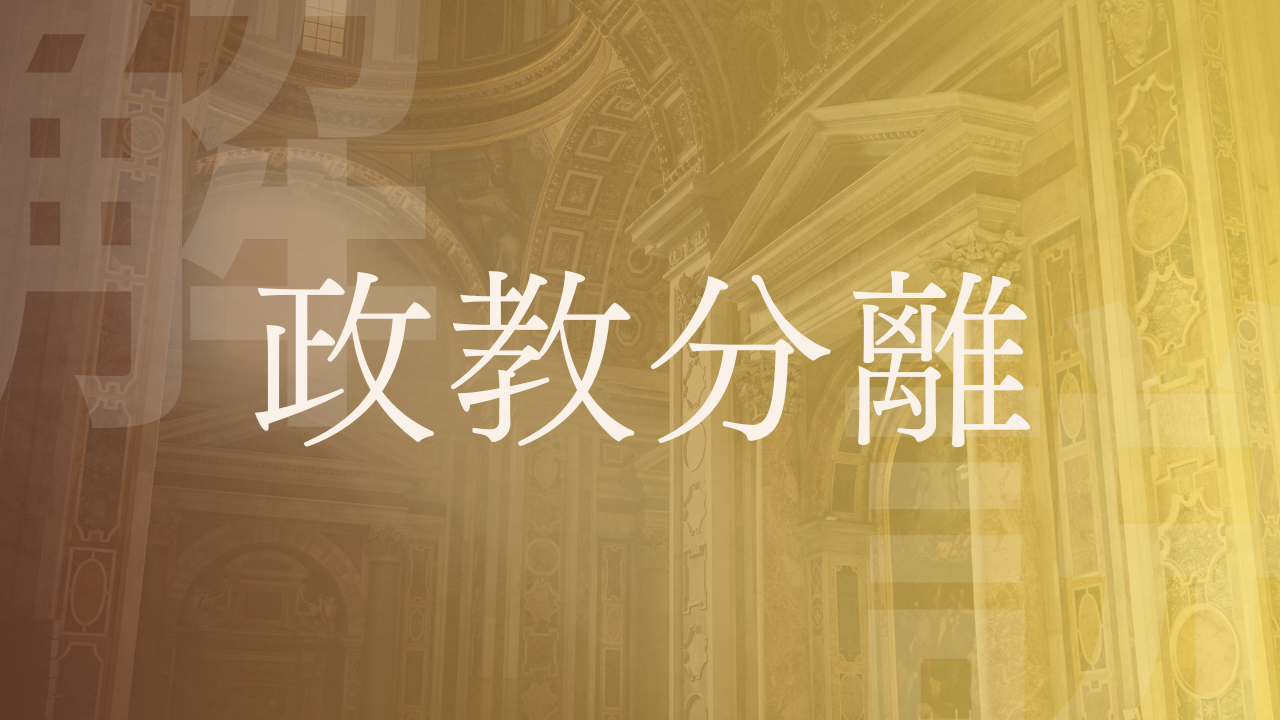【三権分立】意味・目的・日本での仕組み・歴史をわかりやすく解説!

国会・内閣・裁判所の関係は?
国の動きを三つに分け、それぞれが違う独立した違う期間が担当し、互いにバランスをとる制度である三権分立。
国の基本的な形を理解しておくことにより、みじかな社会課題がどこで起こっているのか、原因は何なのかを理解しやすくなります。
今回は三権分立をテーマにまとめていきます。
三権分立とは
国の動きは、法律というルールを作る立法権、作られたルールに基づいて政治を行う行政権、事件や揉め事をルールに基づいて解決する司法権の三権に分けられます。
日本ではそれぞれが独立した「国会」「内閣」「裁判所」といった機関によって担当されています。
それぞれの機関が相互に監視し合い、バランスを保つことにより、国家の暴走や権力が不適切に使われる事を防ぎ、国民の権利と自由を保障する国の形のことを三権分立といいます。
日本国憲法には、立法権を国会、行政権を内閣、司法権を裁判所が担当する事が書かれています。
- 第41条:国会は国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
- 第65条:行政権は、内閣に属する。
- 第76条1項:すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。(日本国憲法から抜粋)
三権分立の歴史
イギリスの哲学者であるジョン・ロックは著書「統治二論」のなかで立法権と行政権の分立を説きました。その後の、1748年にはフランスの哲学者であるシャルル・ド・モンテスキューが著書「法の精神」のなかで立法権・行政権・司法権の三権分立の思想を確立しました。
アメリカ独立戦争後の1787年に制定されたアメリカ合衆国憲法で、初めて三権分立の制度が規定されます。続く1789年には、フランスでも三権分立が憲法に規定されるようになりました。日本では、1890年に制定された大日本帝国憲法で不完全ながらも三権分立の制度が整備され、1947年の日本国憲法で三権分立が現在の形に規定されました。
歴史上、世界各地で独裁体制や政治の暴走が起こっており、それを防ぐべく、この考え方は世界的に広く受け入れられ、現在でも多くの国で採用されています。
国会(立法権)とは
先に述べた通り、法律の制定を行い、予算を決める担当をしているのが国会です。国会は衆議院・参議院に分けられ、国民から直接選挙で選ばれた国会議員で構成されます。また、国会議員が主権者である国民から選挙で選ばれるため、国権の最高機関とも位置付けられています。
国会は衆議院と参議院の二院制を採用しており、衆議院では任期4年(解散あり)、参議院では任期6年(解散なし、3年ごとに半数ずつ改選)となっております。
内閣(行政権)とは
国会で定められた法律・予算に従い実際に国の仕事を行うのが内閣です。国会で指名された内閣総理大臣をトップに内閣総理大臣から指名された国務大臣で構成されます。内閣の下には、学校でどの教科を何時間勉強するか決める文部科学省や国民の健康を支える仕組みを作る厚生労働省など、1府11省2庁があります。
裁判所(司法権)とは
立法権を持つ国会で決められた法律に従って、争いや揉め事を解決するのが裁判所です。事件が起きた時に法律や憲法に照らし合わせて、問題を解決します。裁判所は最高裁判所と下級裁判所で構成されます。下級裁判所には、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所があります。
最高裁判所長官は内閣に指名され、天皇が任命します。またその他の裁判官は内閣が任命します。最高裁判所の裁判官は任期はありませんが、衆議院議員選挙と同日に行われる国民審査でその職にふさわしいか審査されます。
国会と内閣の関係
内閣のトップである内閣総理大臣は、各院内の多数決で国会内から指名されます。また、国会は内閣不信任案決議をすることができ、内閣不信任決議が衆議院で可決された場合には、内閣総辞職もしくは衆議院の解散をしなけらばなりません。なお、実際には内閣不信任決議が可決された際には、衆議院の解散が行われることが多くなっています。一方で内閣は、衆議院の解散権の行使、国会の召集ができる権利を持っており、双方にバランスを保っています。
内閣と裁判所の関係
内閣は最高裁判所長官の指名、最高裁判所の裁判官の任命といった権利を持ちます。また、裁判所は内閣に対して、制定した命令や行政処分に対しての違憲性・違法性を審査する権限を持ちます。
裁判所と国会の関係
裁判所は、国会が制定する法律が憲法に違反していないかを審査する権限(違憲立法審査権)を持ちます。一方で、国会は裁判所に対し、ふさわしくない裁判官をやめさせることができる弾劾裁判を行うことができます。
まとめ
三権分立により、国家権力の集中を防ぎ、暴走を抑える仕組みになっています。三権分立の制度を理解することにより、身近な社会課題がどこで起きているのかを考える必要があると思います。これからも政経百科では、政治経済をわかりやすくお伝えしていくので、ぜひご覧ください。
参考になるサイト
- NHK for school|社会にドキリ 三権の役割|https://www2.nhk.or.jp/school/watch/outline/?das_id=D0005120505_00000
- スマート選挙ブログ|三権分立とは?仕組みや各機関の役割をわかりやすく解説|https://blog.smartsenkyo.com/3116
- 首相官邸きっず|三権分立って何?|https://www.kantei.go.jp/jp/kids/sanken_balance.html