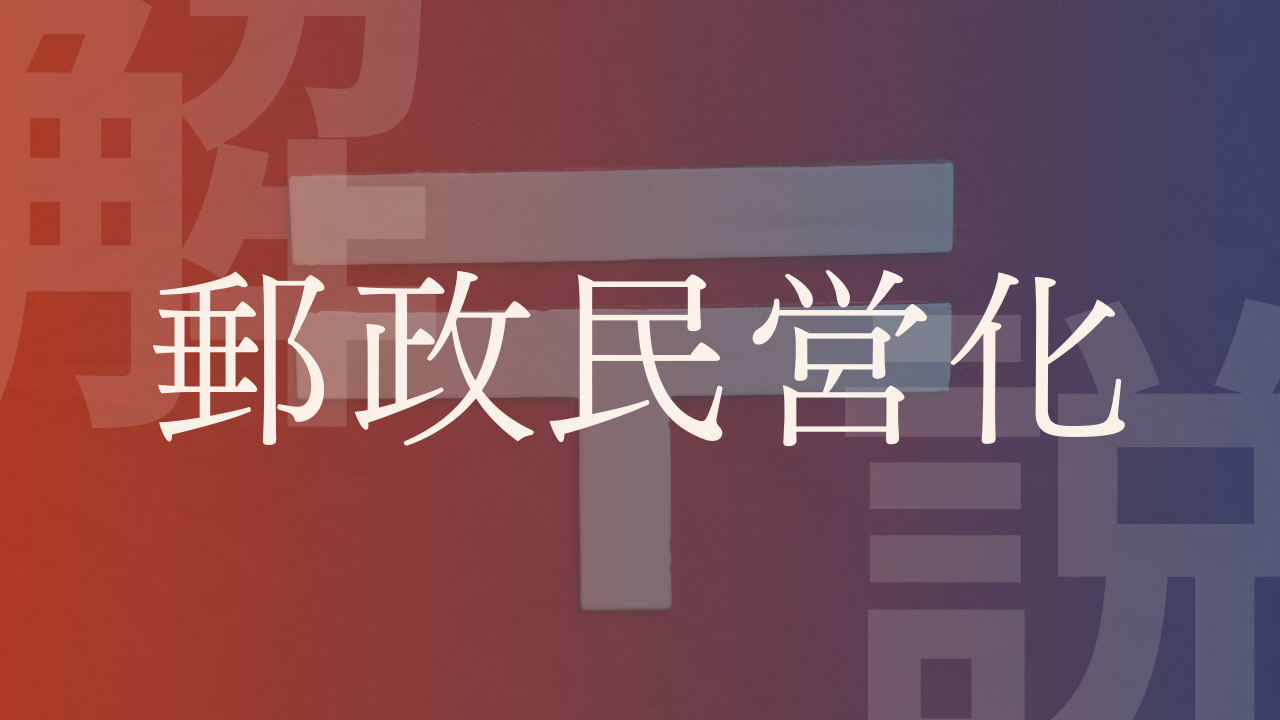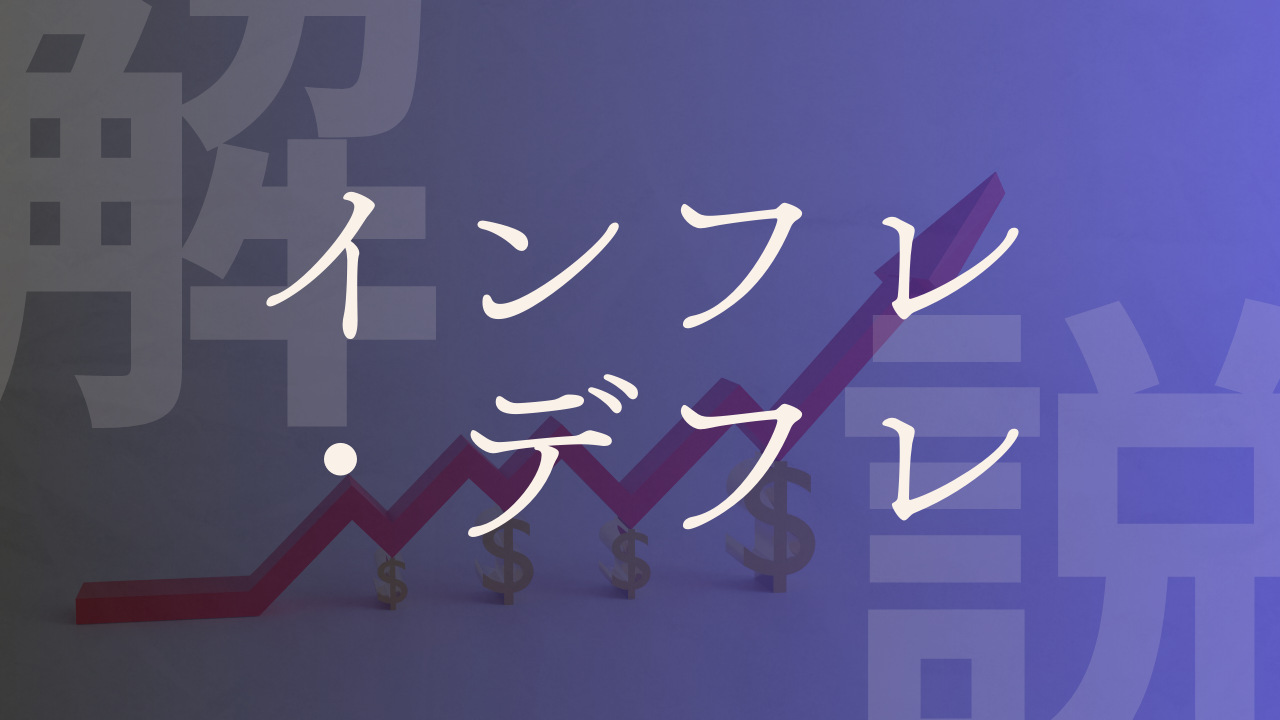【日本銀行】役割や一般銀行との違いをわかりやすく解説

【まとめ】日本銀行の役割・存在について
日本銀行は日銀の略称でよく知られています。経済系のニュースなどでも「日銀」のフレーズはよく耳にします。日本銀行は一般の銀行のように私たちが預貯金を預ける場所ではありません。その役割はよく知られていないと言えます。ここでは日銀の役割や一般銀行との違いについて解説します。
日本銀行とは?
そもそも日本銀行とはどのような銀行なのでしょうか?
日本銀行設立の背景
明治維新以降、日本は近代化を成し遂げるべく殖産興業(経済力を高め強い軍隊を持つことを目標に掲げる政策)を推進していました。そこには当然ながらお金が要ります。そこで政府は不換紙幣の発行を行います。不換紙幣とは、金や銀などと交換ができない紙幣を言います。反対に兌換(だかん)紙幣は金や銀と交換が可能なため、その貨幣価値が保証されます。大量の不換紙幣を発行したことで激しいインフレが起こります。
これを解消するために、1881年に大蔵卿(現在の財務大臣)に就任した松方正義が不換紙幣の整理と通貨安定を図るべく中央銀行の整備を提唱します。翌1882年に日本銀行が出来上がります。
「銀行の銀行」であり「政府の銀行」でもある
日本銀行の役割は安定した紙幣を発行する発券銀行としての役割があります。さらによく「銀行の銀行」であるとも言われます。一般銀行は、日本銀行に預金口座を持っています。金融機関はお互いにお金の貸し借りをしたり、日本銀行が金融政策の一環として行う国債の売買などにこの口座を利用しています。お金の取引を日本銀行が管理することにより経済の安定を図っているのです。
さらに日本銀行には「政府の銀行」としての役割もあります。全国各地の官公庁と取引を行っており、供託金、年金、公共事業などの支払いや、国税、社会保険料、交通違反の罰則金の支払いなども日本銀行が受け入れを行っています。これからのお金は金融機関を通じて日本銀行に払っていることになるため、私たちにも身近な存在だと言えます。
日本銀行の役割
それでは日本銀行の役割をさらに具体的に見てゆきましょう。
お札(日本銀行券)を発行すること
日本銀行はお金を発行しています。日本円のお札が該当します。お札は日本銀行券とも呼ばれます。硬貨は財務省が発行していますが日本銀行を通じて流通しています。ただ発行するばかりではなく、偽造券が出回らないように日々管理と監視を行っています。
損害現金の引き換えも日本銀行の役割です。例えば火事で燃えてしまった、大きな損傷をしてしまったという場合にも日本銀行に持ち込めば相当額のお金と交換してもらえます。両面が3分の2以上残っていれば全額、5分の2以上3分の2未満の場合は半額相当の新券と引き換えてもらえます。
物価の安定をはかること
日本銀行のもう一つの役割は物価の安定です。そのために産業調査も定期的に行っています。多種多様な企業を訪問し、生産や販売の動向や設備設計計画、価格動向への聞き取りや統計データの分析を行っています。
これにより「景気が悪くなり物価が下がりすぎないようにする」「景気が良くなった場合に物価が上がりすぎないようにする」ための調整を行います。
金融システムの安定をはかること
金融システムの安定も日本銀行の重要な仕事です。お金が安定するためにはスムーズなお金のやりとりができることが前提です。日本銀行では預金と貸出の動向を分析しているほか、金融機関と経営の健全性やリスク管理体制などについても金融機関と定期的な意見交換を行っております。場合によっては立ち入り調査を行う場合もあります。これらが行われることによって私たちが安心して金融機関を利用できるようになっているのです。
日本銀行と一般的な銀行の違いは?
それでは日本銀行と普段私たちが利用している一般銀行にはどういった違いがあるのでしょうか。
もっとも大きな違いはお札を発行する機関であるか否かです。海外では複数の銀行が紙幣を発行しているケースもありますが、日本で発券銀行としての機能を持っているのは日本銀行だけです。
さらに日本銀行は中央銀行としての立場からさまざまな金融政策を行っています。代表的なものは経済変動と動向に応じた、金利の調整です。景気が悪くなった場合、物が売れなくなるので物価が下がってゆきます。その場合日本銀行は一般銀行が持つお金の量を増やし、金利を下げます。そうすると、会社は一般銀行からお金を借りやすくなり、経済活動が盛んになり景気回復が期待されます。好景気の場合は、この逆で金利を上げ、お金の量を減らして物価上昇を抑えます。
日本銀行の総裁は?
日本銀行にはトップに総裁がいます。現在の総裁を務めているのは植田和男氏です。植田氏はどういった人物なのでしょうか。
研究者出身の総裁、任期は5年間
現在の日本銀行総裁を務めているのは植田和男氏です。植田氏は1951年生まれ。東京大学理学部を卒業後、経済学部に学士入学し卒業。その後、アメリカのマサチューセッツ工科大学の大学院を修了しています。その後、ブリティッシュ・コロンビア大学助教授、東京大学教授、共立女子大学教授などを歴任しました。1998年より日本銀行政策委員会審議委員を務め、2023年4月より日本銀行総裁を務めています。任期は5年間であり、2028年4月までの予定です。
政策はどういったもの?
それでは植田氏の政策はどういったものがあげられるでしょうか。2024年3月にはマイナス金利の解除など大きな金融政策の転換を行っています。
マイナス金利とは、銀行が日本銀行にお金を預けるにあたってマイナスの金利を設定してするものです。金融機関が日本銀行にお金を預けたままにしておくと、少しずつお金が目減りしてゆきます。こうすることで金融機関がお金を企業などへの貸出や投資に回すように促していたものです。植田氏はこれを「異次元緩和」と呼び「普通の緩和」へすると明言しました。この政策転換は長期的な経済の成長、景気回復を目標とするものです。
まとめ
日本銀行は中央銀行としての役割をもっています。
「銀行の銀行」としての役割のほか「政府の銀行」としての機能も果たしているのです。
日本銀行は、日本の社会、経済の仕組みの中でとても大切な役割をになっています。
参考文献
- ①:日本銀行「日本銀行について」https://www.boj.or.jp/about/education/oshiete/history/index.htm
- ②:日本銀行大阪支店「大阪支店のご案内」https://www3.boj.or.jp/osaka/about/about-bank.html
- ③:金融経済ナビ「日本銀行ってなにをしているの?」https://kinyu-navi.jp/walking/kouza6/index.html
- ④:SMBC日興証券「初めてでもわかりやすい用語集 マイナス金利政策」https://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/ma/J0694.html