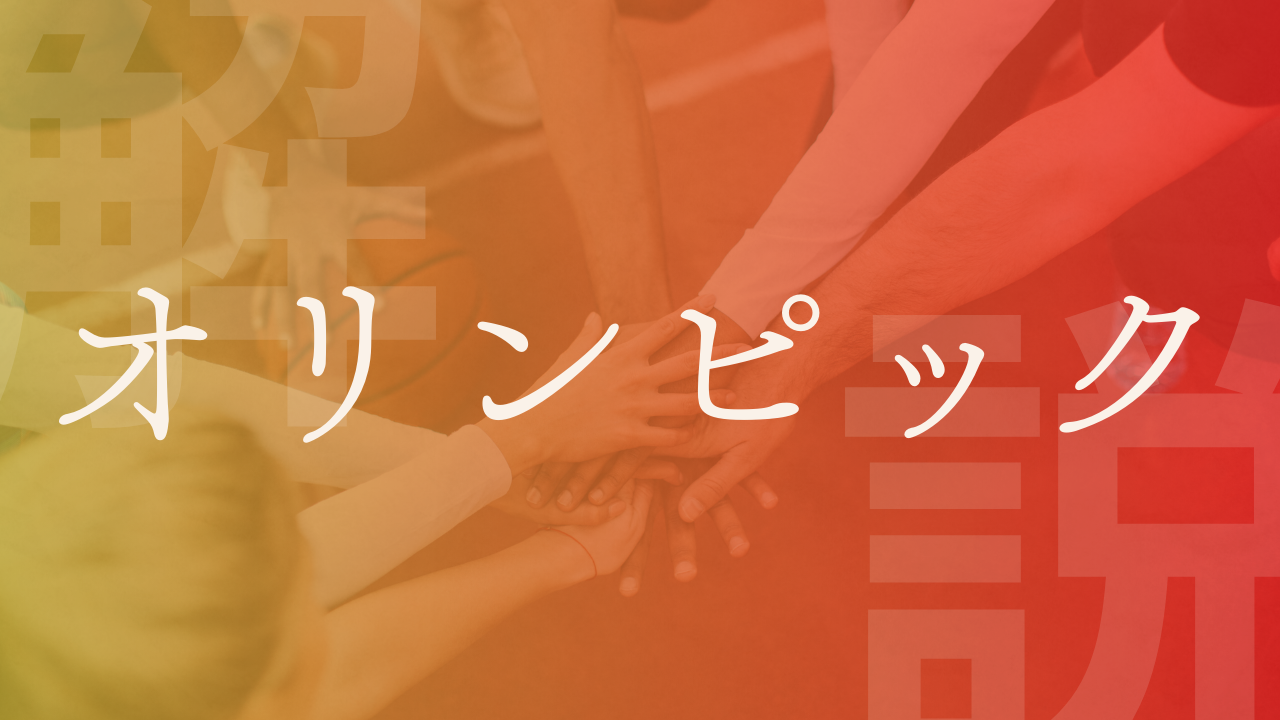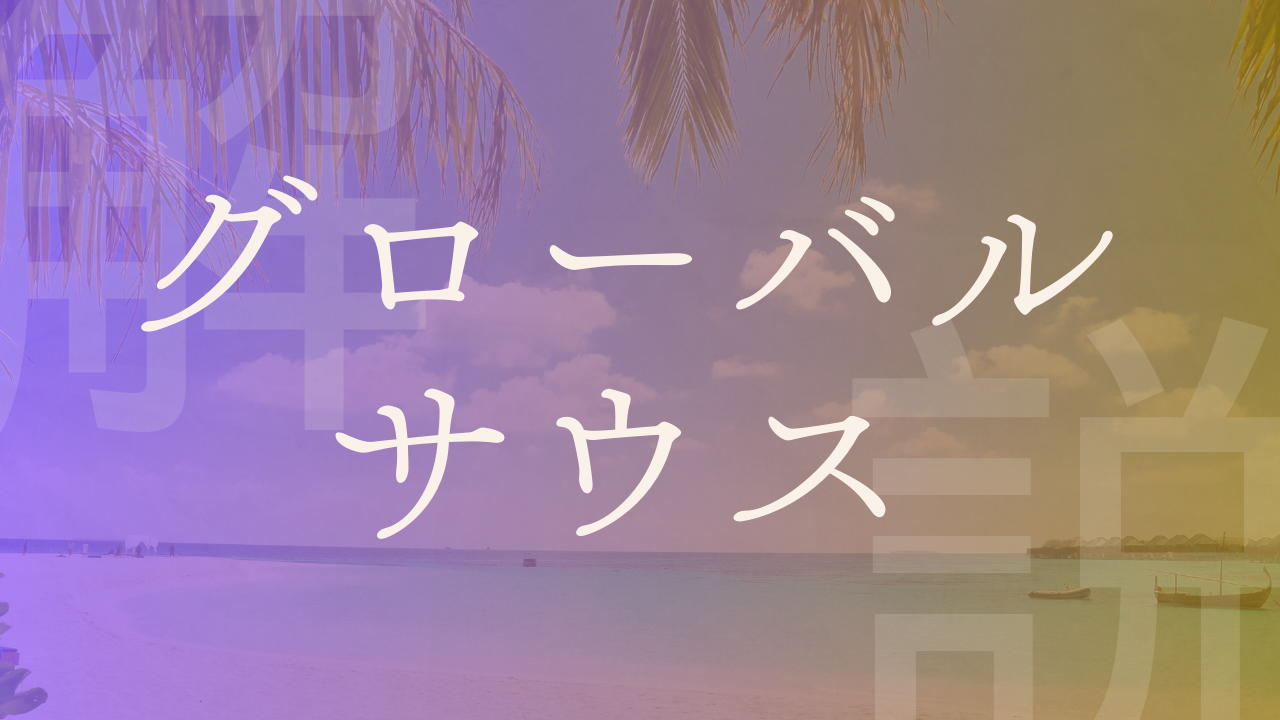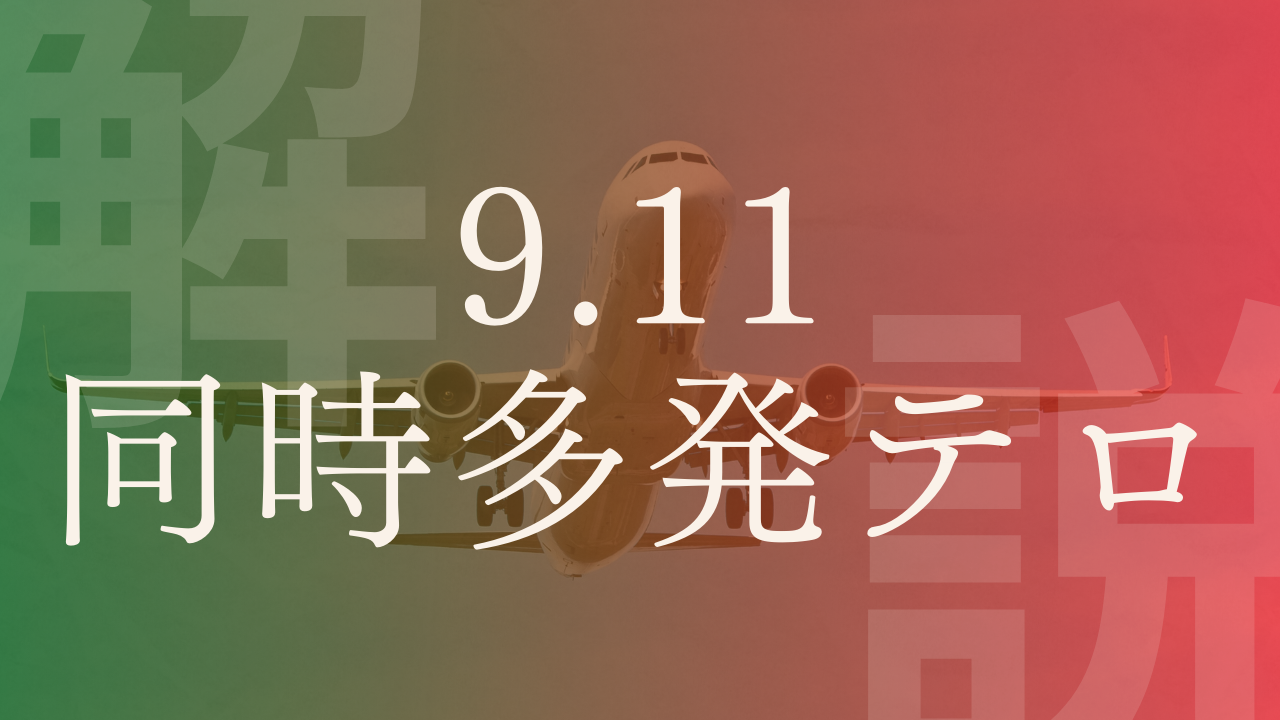【フェアトレード】どんなメリットがある?商品や取り組みの実例も紹介!

フェアトレード認証商品って一体何?
フェアトレードは公正取引とも呼ばれるものです。普段の私たちの消費活動にも深く関わっています。なにげなく手にした商品がフェアトレードと関わりを持っている場合も少なくありません。フェアトレードとは何かについて、あらためて考えてみましょう。
フェアトレードとは?
フェアトレードは公正、公平な取引を指します。これはどのようなものなのでしょうか。
実は多い外国製品
日本で手にする商品は多くの輸入品からできあがっています。たとえばチョコレートのお菓子は日本国内で生産されていたとしても、原料の一つとなるカカオは外国から輸入されたものです。カレー料理に使われているスパイスなども当てはまります。さらに食料品ばかりでなく、普段身につけている衣料品なども生産国が外国であることが少なくありません。これらの商品が、公正で公平な取引がなされているかがフェアトレードにとって重要となります。
先進国と発展途上国の関係
日本では発展途上国で作られた商品が安い価格で販売されています。発展途上国から輸入された原料も同様です。日本は先進国にあたりますが、多くの外国製品は発展途上国で作られています。その理由は人件費や生産コストが安いからです。
いくら人件費や生産コストが安いといっても、生産国の人々が正当な対価を受け取っているかについてフェアトレードは注目します。不当な長時間領導を強いられていないか。あるいは劣悪な環境で生産に従事させられていないかといったものです。さらに生産性の効率をあげるために農薬が必要以上に使われ環境が破壊される問題にも注目します。
理想的なものは生産者の労働環境が改善され、生活水準も一定程度保証されることです。さらに環境も保全されなければなりません。
フェアトレードがいわれるようになった時期、経緯
それではフェアトレードはいつごろから必要性が主張されるようになったのでしょうか。
第二次大戦後に始まった
フェアトレードの歴史は第二次大戦後に始まります。アメリカの国際協力のNGOでボランティアをしていた女性がプエルトリコの女性たちが作っていた手芸品を買い取ってバザーで販売したのがはじまりと言われています。そうした活動がヨーロッパへと広まってゆきました。貧しい生活を強いられている人たちの生活をなんとか改善してあげようとする慈善活動の意味合いがありました。これは小さな試みだったと言えます。
貿易のあり方を考え直す
フェアトレードの考えがさらに広く捉えられるようになったのは1960年代に入ってからです。発展途上国で安く作られた製品や原料が、先進国へ製品として輸出され高い値段で売られる貿易のあり方を考え直す動きが始まり、フェアトレードを専門とするショップが生まれるといった仕組み作りが始まりました。
このころのフェアトレードは「オルタナティブ・トレード」とも呼ばれていました。オルタナティブ(alternative)は英語で「代替、別の」といった意味合いがあります。
既存の貿易とは別のもう一つの流通のあり方を探ろうとしたのフェアトレードだと言えます。
フェアトレードの具体例
それではフェアトレードでは実際にどのような商品の取引が行われているのでしょうか。
スターバックスの取り組み
大手コーヒーチェーン店のスターバックスコーヒージャパン株式会社はNGO団体のトランスファジャパンとライセンス契約を結び、フェアトレードで生産されたコーヒー豆を販売しています。フェアトレード製品を買うことで、発展途上国のコーヒー生産者の収穫に対し最低購入価格を保証し、コーヒー生産者の経済的な安定を支援しています。
イオンの取り組み
スーパーマーケットなどを運営する大手物流グループのイオングループでは「持続可能なカカオの調達に向けた取り組み」を行っています。自社のオリジナルブランド製品においてカカオを扱う場合、「国際フェアトレード認証などイオンが認定する第三者認証を取得した原料を使用していること」「生活・報酬面の課題解決、環境保全活動、労働環境の改善、教育機会の拡大など生産者や労働者の方々が抱える社会課題の解決に向けたプロジェクトを、イオンが直接、支援し生産地の持続的な発展に寄与していること」のいずれかか両方の条件を満たす必要があると定めています。
フェアトレードの課題
フェアトレードは「良いこと」であるように見えますが、さまざまな課題があります。
中小の業者が参入しにくい
フェアトレードを企業が意識する場合、当然ながら原材料や生産のコストが上昇します。それは最終的に商品の価格の値上げなどに繋がるため、消費者が離れていく懸念があります。大量に商品を生産する、あるいは資産に余裕がある大手の事業者はフェアトレードに参入しやすいですが、その分中小の業者が参入しにくい問題が生じます。フェアトレードに取り組んでいない=悪い企業、というわけでは決してないのです。
基準があいまいである
フェアトレードの課題として、2024年時点では基準があいまいである点があげられます。世界共通の基準として国際フェアトレード基準が存在しますが、それを満たしていない場合でもフェアトレード商品として記載が可能になっています。こうした状態を改善するには、フェアトレードはそもそもどういうものなのか、どういう基があるのかをを消費者に周知していく必要があると言えます。
まとめ
フェアトレードは公正取引とも呼ばれています。発展途上国で生産された製品や原料が先進国で売られる場合、そこに正しい取引の過程があるか、生産者に対等な対価が支払われ、経済的安定が保証されているかに着目します。フェアトレードの商品は価格が上昇するため、中小企業が参入しにくい課題があります。基準もあいまいであるため、フェアトレードの存在そのものを周知してゆく必要があります。
参考文献
- ①:FAIRTRADE JAPAN|フェアトレードとは?|https://www.fairtrade-jp.org/about_fairtrade/
- ②:FAIRE TRADE FORUM JAPAN|フェアトレードのはじまり|https://fairtrade-forum-japan.org/fairtrade/fairtrade-history
- ③:スターバックス|全国のスターバックス コーヒー店における生産地貢献コーヒー「フェアトレード(公平貿易)コーヒー」の販売開始について|https://www.starbucks.co.jp/press_release/pr2002-253.php
- ④:AEON|持続可能なカカオの調達に向けた取り組み|https://www.aeon.info/sustainability/social/fair_trade/
- ⑤:MIRAI PORT|フェアトレードの目的と3つの問題点を解説|https://www.mirai-port.com/people/4239/