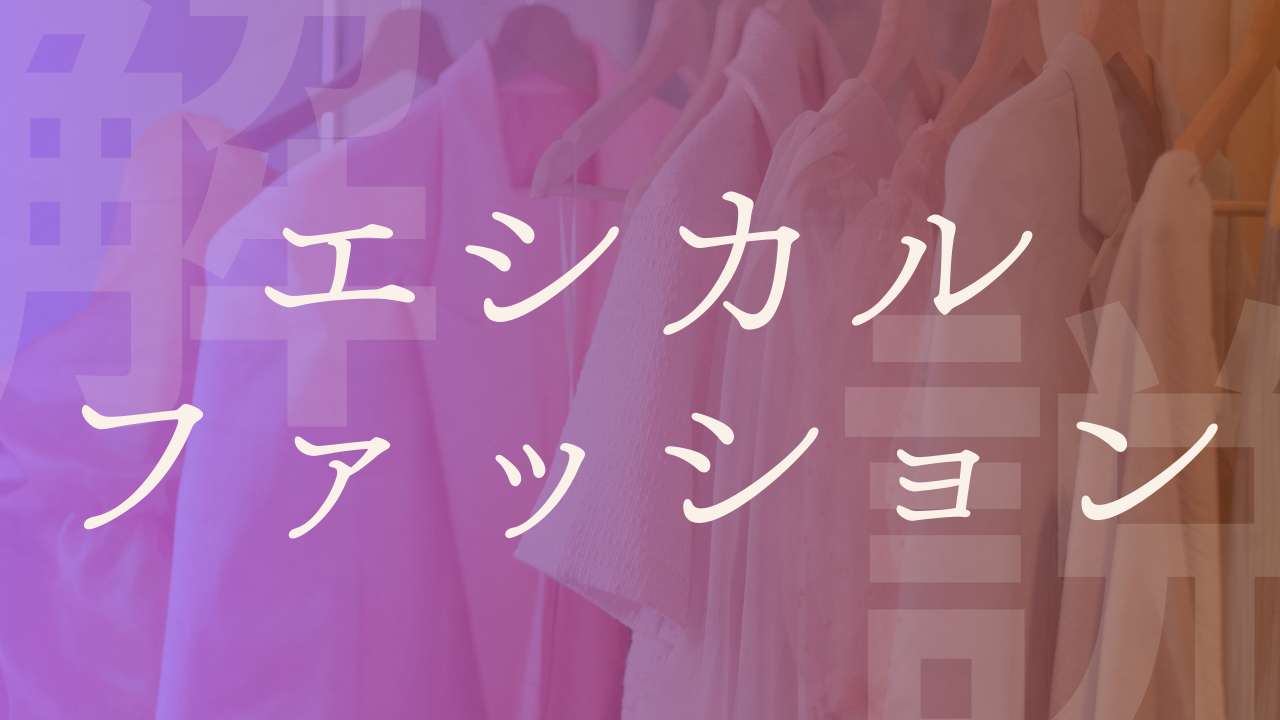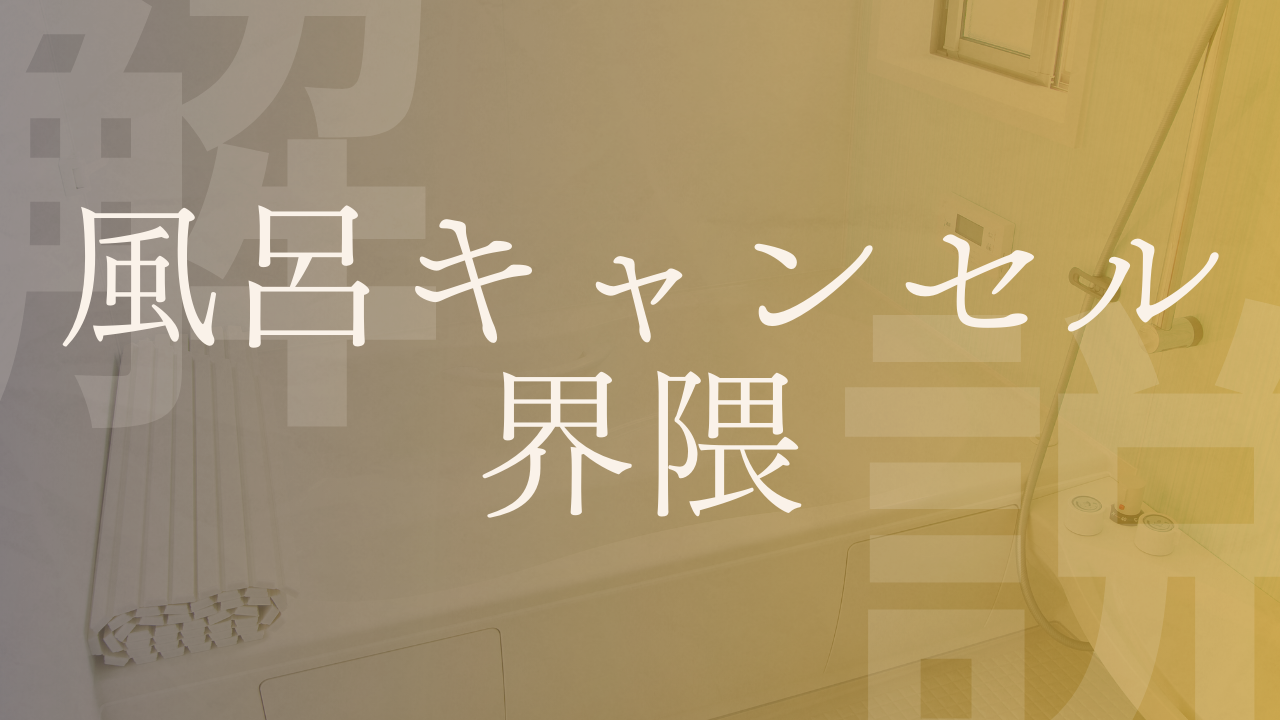【安楽死】定義や賛成・反対意見、尊厳死・医療拒否との違い、海外事例などを解説

安楽死とは。日本と諸外国の現状は?
2019年、京都市の難病ALSの患者が亡くなった事件で、関わった医師が安楽死を主張したことで、安楽死に対する関心が一気に高まりました。そもそも、安楽死とはどのような死を意味するのでしょうか?この記事では、安楽死の定義、日本と世界の安楽死の現状について、わかりやすく解説します。
安楽死とは?
安楽死とは、患者本人の安楽死を望む意思が明らかであることを前提として、耐え難い苦痛があり、治療を尽くしたとしても回復の見込みがなく、死期が迫っているとみなされる場合に、薬などを使って死期を早めることです。
国や地域によって定義や法制度に違いはありますが、一般的には、医師が致死薬を投与することが多いようです。医師から処方された薬を、患者自身が自分で服用する場合には、自殺幇助(ほうじょ=助けること)と呼ばれることもあります。
安楽死と尊厳死、医療拒否の違い
安楽死と似た概念として、尊厳死があります。また、医療拒否やDNRオーダーとは何が異なるのでしょうか。
安楽死と尊厳死の違い
安楽死が主に病気による苦痛を取り除くことを目的とするのに対し、尊厳死は延命治療を行わないことを指します。尊厳死では、生命維持を目的とした人工呼吸器や点滴、人工透析などの延命治療を行わない、または中止しますが、治療を一切受けないわけではなく、痛みや不快感を和らげる緩和ケアは行われます。一方で、安楽死と尊厳死のどちらも、他に治療法がなく、回復の見込みがない末期であること、本人の意思を尊重して行うことについては共通しています。
ただし、安楽死と尊厳死を明確に区別するのは日本特有で、多くの国では尊厳死も安楽死の一部として捉えられます。また、日本でいう安楽死と尊厳死を、それぞれ積極的安楽死と消極的安楽死として呼ぶこともあります。
安楽死と医療拒否の違い
医療拒否とは、そもそも治療を受けること自体を拒否することです。一方で、安楽死とは、あらゆる治療や可能性を試みた上で、現状の医療技術ではそれ以上手を尽くすことができない場合に、薬などで死を迎えることです。いわば、安楽死は最後の手段であり、最初から治療を拒否することを意味するわけではありません。
DNRオーダー
DNRオーダー(Do Not Resuscitation Order)とは、直訳すると蘇生拒否指示となり、心肺蘇生を拒否することをいいます。わかりやすく言うと、心臓を正常な動きに戻すための処置(心臓マッサージやAEDなど)を行わないということです。安楽死や尊厳死と同じで、すべての医療を拒否するわけではありません。しかし、末期患者の場合、心臓マッサージは身体への負担が大きいにもかかわらず、成功率が非常に低いので、あらかじめ患者から医師に、心臓が止まってしまったとしても心肺蘇生をしないように伝えておくというわけです。
世界の現状
ここ20年ほど、安楽死を法制化する国は拡大傾向にあります。世界ではどの程度まで安楽死が認められているのでしょうか。
外国人も安楽死できる国、スイス
スイスでは、医師が直接薬を投与する安楽死は認められていませんが、患者自身が処方された薬を自分で服用する安楽死(いわゆる自殺幇助)を行うことができます。スイスで安楽死を行うには、治る見込みのない病気であること、耐え難い苦痛があること、健全な判断能力があることなどが主な条件です。年間約1500人ほどが安楽死で亡くなっているといわれています。
安楽死といえば、ドキュメンタリーなどで日本人がスイスに渡航し、安楽死を実行する様子を見たことがある人もいるのではないでしょうか。実は、安楽死が合法である国はいくつかありますが、外国人でも安楽死ができる国は、今のところ世界でスイスだけなのです。そのため、自国で安楽死が法制化されていない人で、安楽死を強く望む場合は、あらかじめ申請など必要な手続きを済ませた上で、スイスへと渡り安楽死を行うケースがあるのです。
安楽死が急増している国、カナダ
カナダでは、2016年に安楽死が合法化されました。その後、安楽死はカナダ国内で急速に拡大し、施行からわずか5年で4万人以上の人々が安楽死を実施しました。2022年には、カナダ全土の死亡者のうち約3%もの人々が安楽死だったそうです。このように安楽死が急増した背景としては、患者が自ら薬を服用する以外に、医師による薬の投与による安楽死が認められているという制度的要因や、安楽死が個人の権利の一つとして考えられていること、貧しさからそれ以上の治療を受けられそうにない立場の人が安楽死を選択してしまうといった社会的要因などが指摘されています。
日本の現状
それでは、現在の日本では安楽死はどのような法的扱いとなっているのでしょうか。
現状、日本では安楽死(積極的安楽死、自殺幇助、尊厳死(消極的安楽死)を含む)のいずれも認められていません。日本の法律では、致死薬などによって安楽死した場合や、延命治療を中止したことで患者が死亡した場合、薬を投与したり、人工呼吸器を外したりした医師は嘱託(しょくたく)殺人、つまり殺人を助けた罪に問われることになります。
1990年代以降、いわゆる安楽死を実行したと思われる事件が増加し、その度に関わった医師の行為が安楽死として認められるべきか、殺人罪として罪を問われるべきかが議論されてきました。安楽死を求める意見が一定数ある一方で、反対も根強く、これまで日本で安楽死が法制化されたことはありません。
安楽死への賛成意見
ここからは、安楽死についての賛成・反対それぞれの意見をみてみましょう。
死を選ぶことは個人の権利である
まず賛成派で最もよく強調されるのは、安楽死が個人の権利の一つであることです。基本的人権として生きる権利が与えられているのと同じで、人は尊厳ある死を迎える権利がある、という考えに基づきます。治る見込みのない病気を抱えて、痛みに苦しみながら残りの人生を終えるよりは、自分らしい姿のままで人生を終えたい、と願う気持ちに共感する人は少なくないのかもしれません。
医療費の抑制になる
終末期医療は、高額な上に長期間になりやすいため、多額の医療費がかかります。患者やその家族に金銭的な負担がかかり続けること、また超高齢社会の日本では寝たきりの患者が非常に多いことから、医療費を抑えるためにも安楽死が有効だと考える人もいます。
安楽死への反対意見
では、安楽死への反対意見にはどのようなものがあるのでしょうか。
権利ではなく義務になってしまう恐れ
安楽死を合法化すると、死の権利がいきすぎて死の義務になってしまうのではないか、という懸念があります。たとえば、家族に迷惑をかけるべきでないという考えから、安楽死を選ぶことが美徳となったり、周囲から安楽死するようプレッシャーをかけられたりと、本人の意思を尊重するという本来の安楽死の在り方が保てなくなる恐れがあると考えられています。
医師の判断がばらつく恐れ
安楽死が法制化される場合、実施するための一定のルールや、安楽死が適切かどうかを判断するための基準は設定されると思われますが、医師も人間です。余命を基準にするとしても、その判断にはばらつきが生じる恐れがあります。通常の病気でも、病院によって処方される薬が違うこともあるように、安楽死が適切がどうかの判断も医師によって異なる可能性があり、本来死ぬべきでない人が安楽死を勧められてしまうのではないか、と危惧されています。
まとめ
この記事では、安楽死として認められるには、本人のはっきりとした意思や、回復の見込みのない病気であることなどの条件があること、日本では現状法制化されていないものの、安楽死に対して賛否両論の意見があることを解説してきました。さて、あなたは安楽死についてどう思うでしょうか?自分や家族、身近な人の死や生き方について考えるきっかけになれば幸いです。
参考になるサイト
- 朝日新聞DIGITAL|【用語解説】安楽死・自殺幇助・尊厳死の定義|https://www.asahi.com/articles/ASR4V3JSTR4KUHBI03L.html
- 公益財団法人 日本尊厳死協会|よくある質問|https://songenshi-kyokai.or.jp/qa
- 朝日新聞DIGITAL|日本も安楽死を法制化するのか? 識者が示す、その前に知るべきこと|https://www.asahi.com/articles/ASR4T4DNSR4KUHBI01P.html?iref=pc_rensai_short_1811_article_4
- 朝日新聞GLOBE+|「安楽死」か「殺人」か 日本での尊厳死の議論と法整備の動き、どこまで進んだ|https://globe.asahi.com/article/14998799
- 日本医事新報社|日本の法律上,安楽死や自殺幇助はどう罪になる?|https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=3882
- 東洋経済ONLINE|「安楽死を認めよ」と叫ぶ人に知ってほしい難題 議論はあっていいが一方向に偏るのは危うい|https://toyokeizai.net/articles/-/367007
- ハフポスト|安楽死制度に「賛成」「反対」という議論にゴールはあるのか:緩和ケア医 西智弘|https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5fe59c01c5b66809cb30e5dd
- NHK放送文化研究所|日本人は”いのち”をどうとらえているか ~「生命倫理に関する意識」調査から~|https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/20150401_6.html
- SWI swissinfo|年間1500人超が選択 スイスの安楽死|https://www.swissinfo.ch/jpn/business/%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%82%b9-%e5%ae%89%e6%a5%bd%e6%ad%bb-%e7%8f%be%e7%8a%b6/45931282
- PRESIDENT Online|「海外での安楽死」は200万円で十分可能|https://president.jp/articles/-/24274
- MSDマニュアル家庭版|DNR指示(蘇生処置拒否指示)|https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/01-%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%84%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98/%E6%B3%95%E7%9A%84%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%A8%E5%80%AB%E7%90%86%E7%9A%84%E5%95%8F%E9%A1%8C/%E6%8C%87%E7%A4%BA-%E8%98%87%E7%94%9F%E5%87%A6%E7%BD%AE%E6%8B%92%E5%90%A6%E6%8C%87%E7%A4%BA
- NHKニュース|ALS女性嘱託殺人 被告の医師に対し懲役18年の判決 京都地裁|https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240305/k10014379911000.html