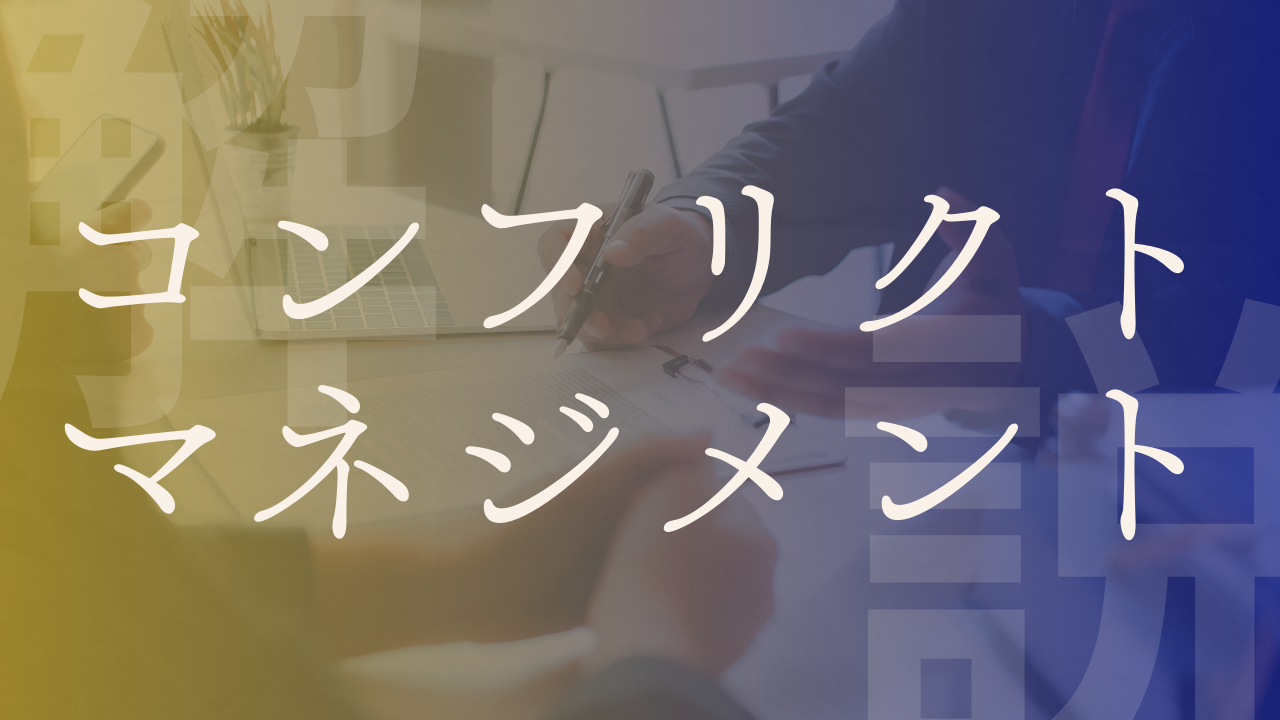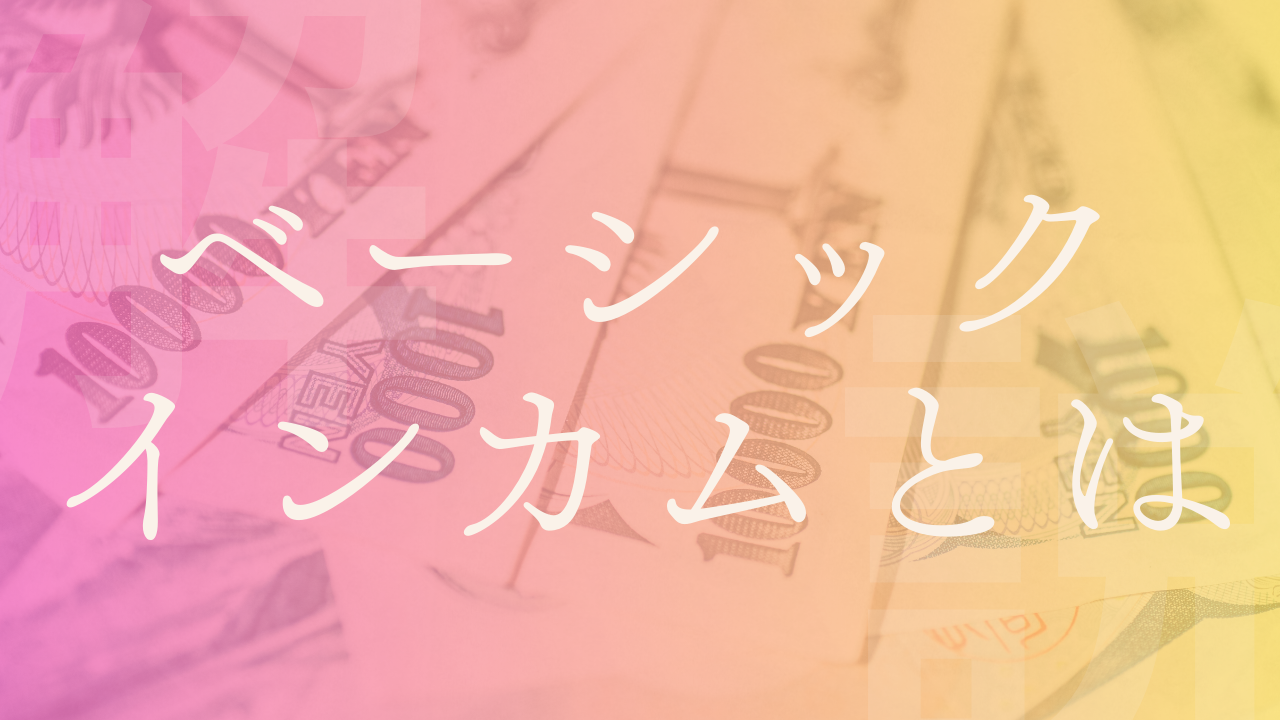【制約条件の理論】TOC理論をわかりやすく!ボトルネックの解消・コーチングについても解説!

TOC理論とは?考え方やメリットなどをわかりやすく!
みなさんは、制約条件の理論という言葉を見聞きしたことはあるでしょうか。おそらく、ないという方がほとんどでしょう。
これはビジネスのみならず、多くの組織において有用な手法なので、この記事を通して覚えておきましょう。
制約条件の理論とは?
生産管理・改善のための手法である制約条件の理論。企業・工場のような組織やそれ以外の組織においても非常に有用なこの手法について、今回は解説していきます。
制約条件の理論(以下、TOC理論)は、イスラエルの物理学者エリヤフ・ゴールドラット氏が考案した、生産管理・改善のための理論体系です。
どのような組織においても、生産を妨げる要因が存在します。TOC理論は、この生産を妨げる要因を「制約条件(ボトルネック)」と呼び、ボトルネックの改善を集中的に行うことで、組織全体の業績改善や生産性の向上を目指すという考え方です。
業績や組織全体の生産性は、一番の弱点であるボトルネックによって決まるため、そこに集中して改善策を講じれば、生産性は上がる、というのがTOC理論の基本的な考え方です。
ボトルネックとは?
では、そもそもボトルネックとは何なのでしょうか。
ボトルネックとは、業務やプロジェクトの行程のなかで、停滞や生産性の低下を招いている行程や人を指す言葉です。ボトルネックの存在は組織全体に悪影響を与えるため、早急に改善する必要があります。
直訳すると「瓶の首」で、これはどんなに大きな瓶でも首が細いと注げる量が制限されてしまうことに由来します。
ボトルネックを解消する制約条件の理論のステップ
ボトルネック解消のためには、いくつかの段階を踏む必要があります。
ボトルネックを発見する
最初に、改善すべきボトルネックを発見する必要があります。組織全体を俯瞰して、どこに生産を妨げる要素があるのか見つけ出すのです。
複雑に要素が絡み合い、原因の特定が困難な場合もあります。その場合は、服巣の要素を分類し、根気強く検証しなければなりません。
ボトルネックに対する方針を決める
ボトルネックの特定に成功したら、次にそれを改善する方法を考えます。資金や人材の投入や熟練者の移動、規約の改正など多岐にわたります。
実行
方針を決めたら、あとは実行するのみです。出来ることをやり切ったら、ボトルネックとなっている部分にさらなるリソースをつぎ込むのか、構成員の能力を強化するのか、その場に応じて最善策を講じる必要があります。
繰り返して生産性を向上
ボトルネックが解消されたら、再びボトルネックの探索に戻って、新たなボトルネックを探す必要があります。これを繰り返すことで、確実に問題点をつぶし、組織全体の生産性の向上を図ることが出来ます。
制約条件の理論のコーチングのやり方
ここでは、TOC理論を用いたコーチングの手法について解説していきます。
コーチングとは、相手が目標を達成できるように、気付きを与えたり自主的な行動を促したり、サポートしたりすることです。
一方的に指導をするのではなく、以下のステップを一緒に行うことが大切です。
問題を見極める
まず、現在のボトルネックを特定します。問題の原因を特定し、どこを改善すべきか決めるために必ず踏まなければならないステップです。
解決策を検討
見つけたボトルネックをどのように解決するかを考えます。特定のボトルネックを克服し、組織全体を最適化するための解決策を見つけるのです。どこにどの程度のリソースを投入するかも、この段階で決めます。
実行計画を立てる
ここでは、ボトルネック解消のための具体的な計画を立てます。必要なリソースの確保や利害関係者への連絡、リスク管理などはここで行います。
それぞれのステップごとの進捗の管理や必要に応じて計画内容の調整なども行います。
実行
計画が完成したら、後は実行するのみです。実行しても現状が変わらない場合は、さらなるリソースの投入など、追加の決断を行う必要があります。
TOC理論のメリット
ここからは、TOC理論のメリットについて解説していきます。
効率の向上
組織内における最大の問題を解決することで、組織活動の流れがスムーズになり、生産性が向上することが見込まれます。無駄を省くことにもつながり、効率的なシステムの構築が出来ます。
リソースの適切な運用
TOC理論では特定のボトルネックに照準を合わせて、それを中心にリソースを分配することを目指します。限られたリソースの中で、どこにどうリソースを使い、パフォーマンスを最大化するのかが大切です。
組織の最適化
個別の部局や個人のみならず、組織全体の最適化を図ることができます。局所的な改善にとどまらず、組織全体のパフォーマンスを向上させることにつなげることが可能になります。
人間関係の円滑化
また、人間関係を円滑化し、意思決定のプロセスをより合理化することも可能になります。人間特有の感情に関する問題を改善し、意思疎通の推進も可能になります。
まとめ
日ごろ、ビジネスなどの場で「ボトルネック」という単語を見聞きすることがあると思います。今回は、その単語の意味を解説とともに、解消する方法についてみていきました。
皆さんが所属する組織の中にも、問題があると思います。この理論は会社にとどまらず、様々な組織の中で、有効な手法になるかもしれません。
参考になるサイト
- ASPROVA|TOC理論(制約条件の理論)とは? 思考プロセスと問題解決手法を解説|https://products.sint.co.jp/asprova/blog/theory-of-constraints
- カオナビ|ボトルネックとは?【ビジネスでの意味を簡単に】原因と解消法|https://www.kaonavi.jp/dictionary/bottle-neck/
- リクルート|TOC理論とは|https://www.recruit-ms.co.jp/glossary/dtl/0000000159/