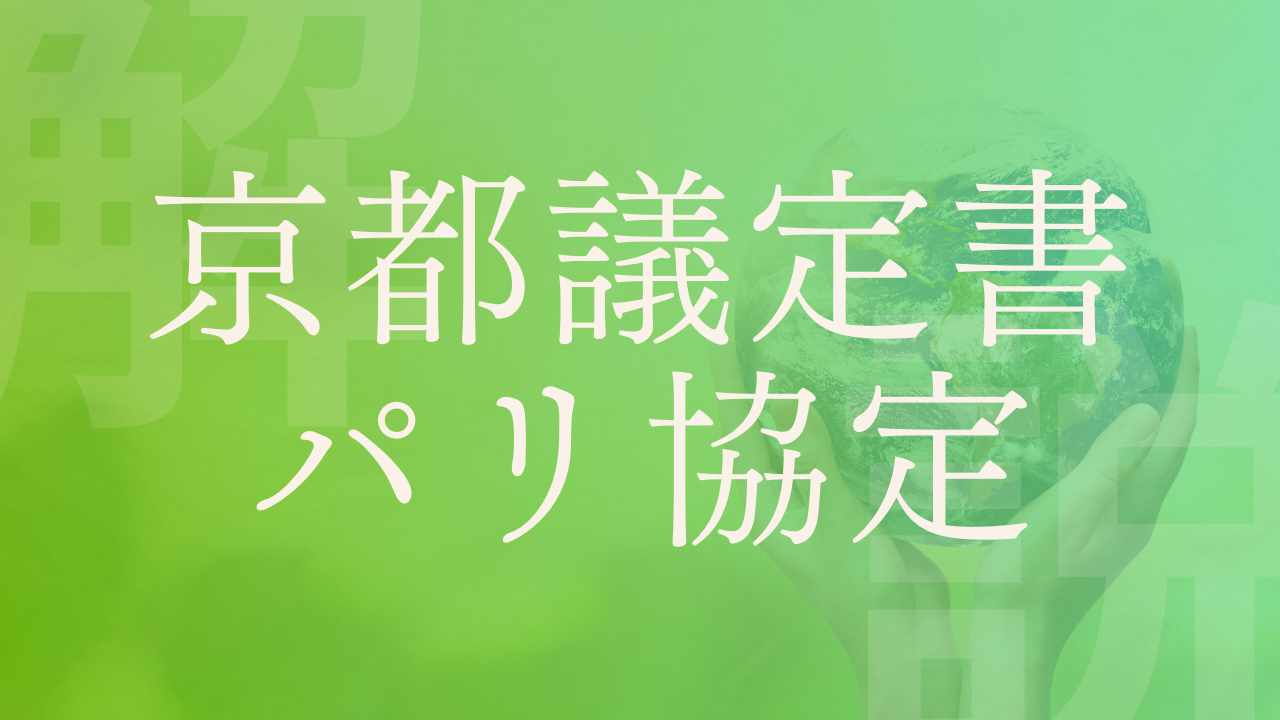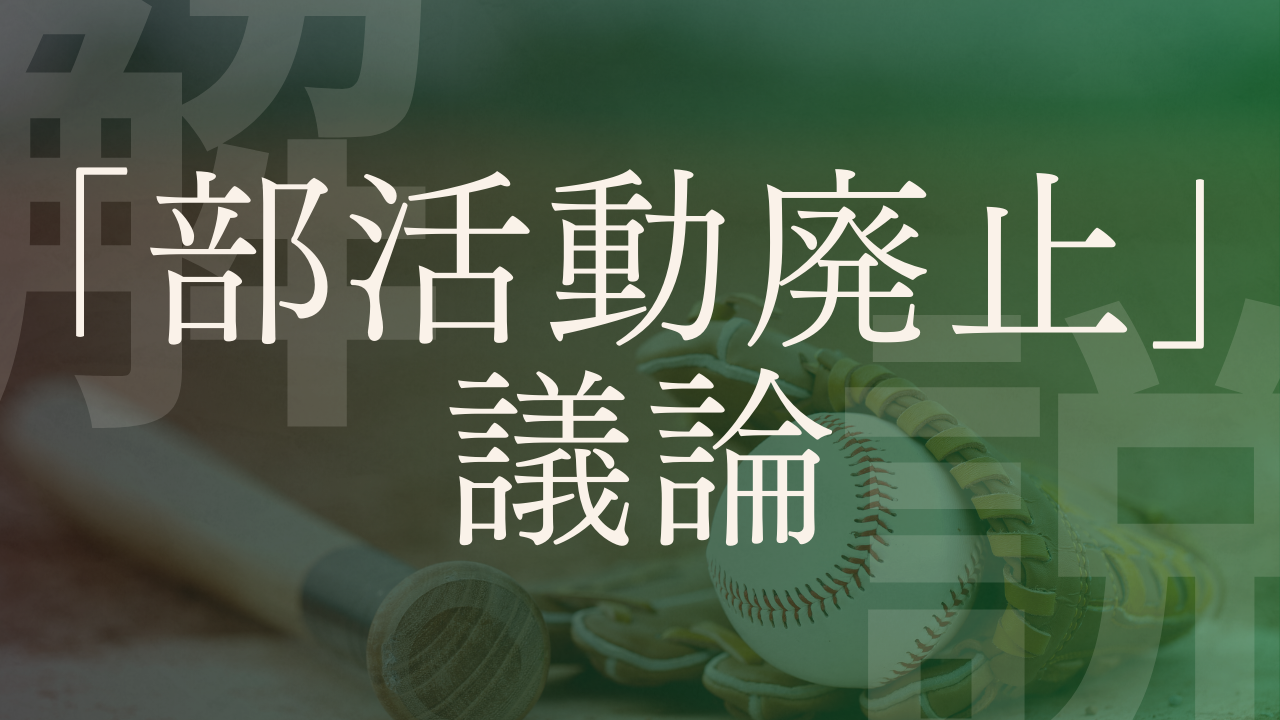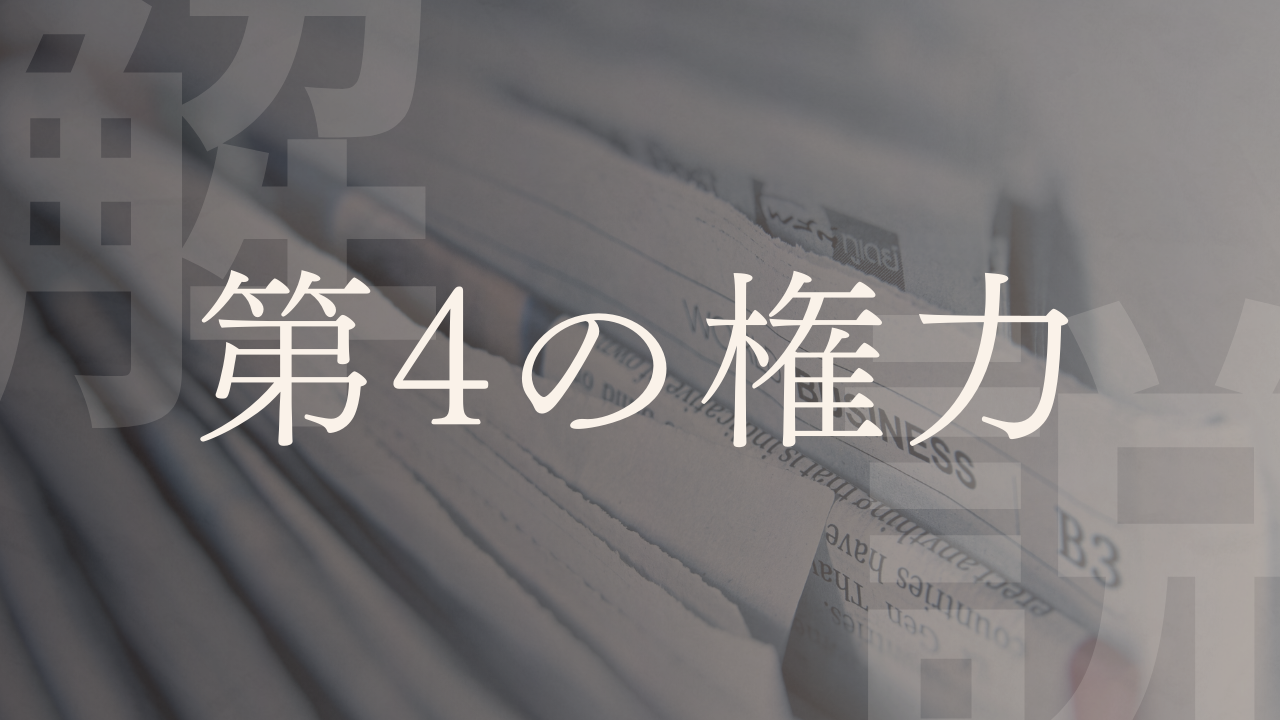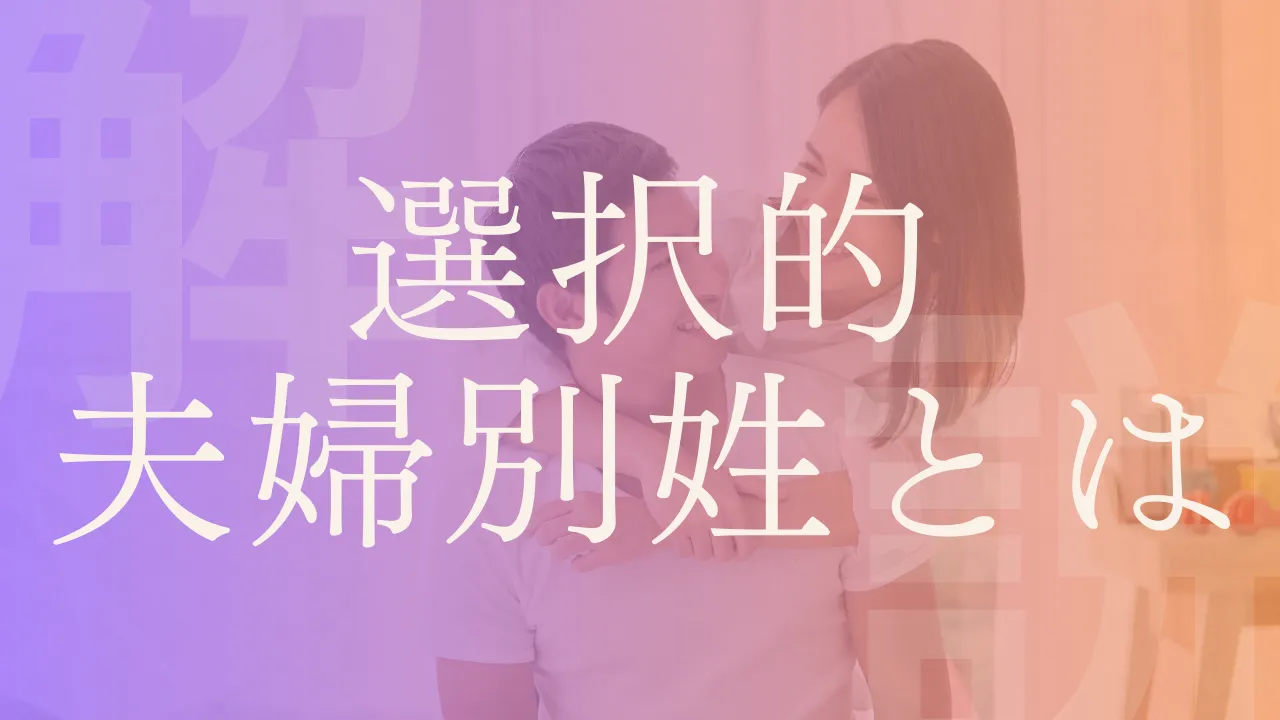【賞味期限と消費期限】意味・違い・決め方・など食品表示ルールを解説

賞味期限切れと消費期限切れの違いって何?
スーパーやコンビニ等で買い物をする際に目にする賞味期限や消費期限などの食品表示。
これらには一体どのようなルールがあるのでしょうか?
今回は、その決め方やそれぞれの違い、切れても食べられるのかなどを解説します。
賞味期限と消費期限の違い
賞味期限と消費期限の違いとして、もっとも大きなものとしては品質の劣化速度の違いです。品質の劣化の早いものは「消費期限」、比較的緩やかなものは「賞味期限」が製品に記載されます。
賞味期限とは?
賞味期限とはおいしさなどの品質が保たれる期間を言います。ここには味や食感なども該当すると言えます。賞味期限が表示される食品は較的傷みにくいものです。期限を超えたとしてもすぐに安全性に問題が発生するとは限らないものです。該当するものとしては、スナック菓子や缶詰製品などがあげられます。缶詰製品の中には食品ばかりでなく、缶入りのジュースなどの飲料も含まれます。
これらの商品は包装がなされていたり、缶詰のように密封されています。そのため外部からの影響を受けにくい構造になっています。さらに「直射日光を避ける」など表示された保存方法をしっかりと守っている場合は、賞味期限を超えて口にしてもすぐに安全性に問題が生ずるわけではありません。
消費期限とは?
それでは賞味期限に対して少期限は何を指すのかといえば、安全に食べられる期限です。急速に劣化する食品に表示されます。消費期限が表示されるものは弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、食品、生麺などに表示されています。ある程度、時間が経つと腐ってしまう、食べられなくなるイメージのあるもの全般と考えれば良いです。
表記についてのルールは
賞味期限と消費期限については表記についてのルールも定められています。どちらの期限表示についても「年月日」まで表示しますが、賞味期限については製造された日からの期限が3ヶ月を超えるものについては「年月」で表示しても良いことになっています。長期間保存が効く缶詰製品などの表示はそうなっている場合が多いです。
賞味期限と消費期限の決め方は?
それでは賞味期限と消費期限はそれぞれ、どのように決められているのでしょうか。基準となるのは消費者庁が示すガイドラインです。これを元に各食品企業が設定を行っています。消費者庁はウェブで「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を公開しています。ここには賞味期限と消費期限の双方に当てはまる指針が記されています。以下は特にその中でも特に賞味期限、消費期限に関わるトピックを取り上げます。
賞味期限の決め方
比較的保存が効く食品につけられる賞味期限について「食品期限表示の設定のためのガイドライン」では、1年を超えるなど長期間に渡り品質が保持される食品については長期間の試験(検査)は現実的ではないとし、一定の範囲を設定し、その結果を確認すれば合法的な根拠とできると記されています。
消費期限の決め方
痛みやすい食品につけられる消費期限について「食品期限表示の設定のためのガイドライン」では、理化学試験、微生物試験などにおいて数値化した客観的な項目を導き出す必要があると記されています。さらにそこに安全係数をかけて、客観的な指標である数値よりも短い期間を消費期限に設定することが基本であると定められています(これは賞味期限も同様です)。ある食品の消費期限を決める場合に、絶対に安全な客観的な日時よりも、さらに前の日時を設定する必要があると求められています。
賞味期限の1/3ルールとは?
賞味期限と消費期限の大きな違いは食品の劣化のスピードです。それでも賞味期限を気にする人は少なくありません。それが食品ロスを生み出す原因になっているとも言われています。
1/3ルール
食品ロスを生み出す原因となっているのが、スーパーや小売店に食品メーカーが品物を降ろす時に慣習として存在している1/3ルールです。
メーカーはお店に賞味期限が1/3となる前に卸さなければいけないとされています。賞味期限が6ヶ月の商品があったとします。この場合、2ヶ月を切った商品は下ろせなくなります。これらの商品はディスカウントストアなどに流れます。こうしたお店では賞味期限が近い商品が安く売られていることがありますが、これは1/3ルールに基づく慣習によるものです。それでも商品が捌けない場合は廃棄となります。
現在は一部のスーパーや小売店が1/3ルールを緩和する流れがあります。大手の中ではイトーヨーカドー、セブンイレブン、ミニストップ、ファミリーマート、ローソンなどが該当します。
てまえどりを推奨
食品ロスを防ぐためには、消費者が賞味期限が短いものを積極的に手に取るようにする行動である「てまえどり」も環境省ほかで推奨されています。私たち消費者側の心がけや意識改革も必要だと言えます。
まとめ
賞味期限と消費期限の違いは、食品が劣化するスピードによるものです。
弁当やパンなどの劣化が早いものには消費期限、スナック菓子やカップラーメンなど比較的長期間保存ができるものには賞味期限の表示が義務付けられています。
消費期限を過ぎたものは口にした場合、問題が起こる可能性が高いです。賞味期限は、期限を過ぎたものを口にしても大きな問題が起こりにくいものと区別することもできます。
参考になるサイト
- 東京都保険医療局「消費期限と賞味期限は、何が違うのでしょうか?【食品安全FAQ】https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/anzen/anzen/food_faq/hyoji/hyoji04.html
- 味の素株式会社「賞味期限と消費期限の違いは何? 決め方は?」https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/limit.html
- 消費者庁「食品の期限表示に関する情報」https://www.caa.go.jp/policies/policy/foodlabeling/foodsanitation/expiration_date/
- 消費者庁「食品期限表示の設定のためのガイドライン」https://www.caa.go.jp/policies/policy/foodlabeling/foodsanitation/expiration_date/pdf/syokuhin23.pdf
- なるほどSDGs「3分の1ルールとは?食品ロス問題の現状と、解決のためにできること」
https://naruhodosdgs.jp/one-third-foodloss/ - 環境省「「てまえどり」ダウンロードページ」
https://www.env.go.jp/recycle/food/post_95.html