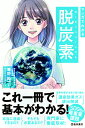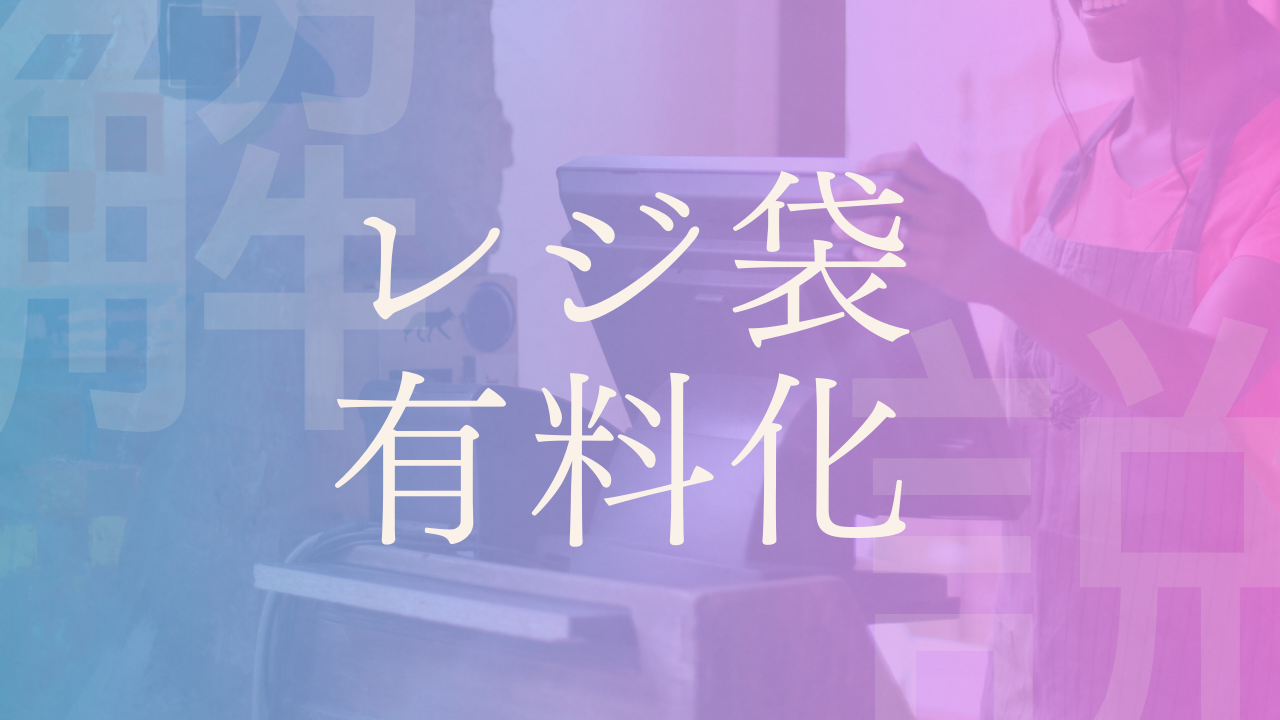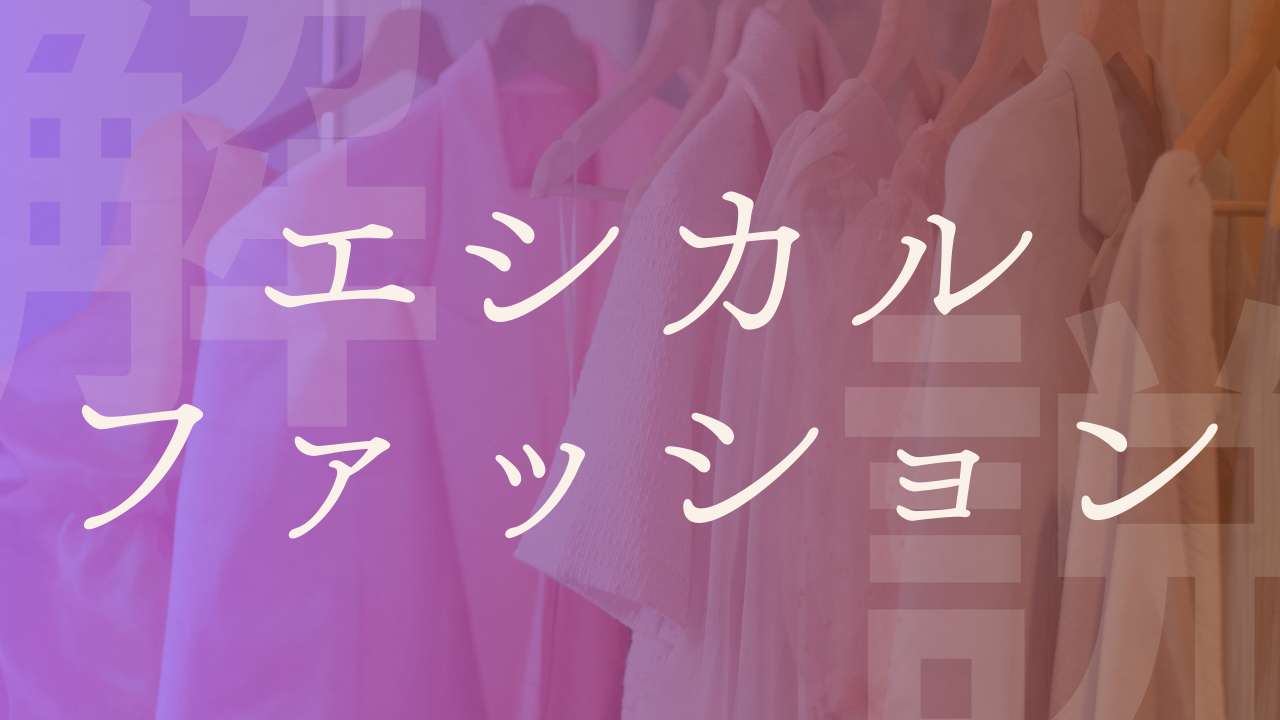【排出量を実質ゼロへ】よく聞く「カーボンニュートラル」って何?

カーボンニュートラル・脱炭素とは?
カーボンニュートラル(脱炭素)とは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを指します。つまり脱炭素社会とは、カーボンニュートラルを実現した社会です。
2020年10月、日本政府は2050年までに温室効果ガスの排出量を全体としてゼロにするカーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言しました。カーボンニュートラルの実現のためには、温室効果ガスの排出量の削減と吸収作用の保全の強化の両方に取り組む必要があります。
吸収と排出の仕組み
ここからは、二酸化炭素が循環する仕組みをみていきます。
二酸化炭素は、大きくわけて動植物による呼吸と人為的に燃料を燃やすことによって排出されます。(参考サイトを元に画像作成)
一方で、植物による光合成によって吸収されます。
大まかには、森林等の保全によって植物の光合成量を維持すると共に、人為的な燃料の使用による排出量を維持していくことがカーボンニュートラルへの取り組みと言えるでしょう。
引用元:https://www.bluedotgreen.co.jp/column/emissinncalculation-cfp/decarbonization/
参考:https://www.try-it.jp/chapters-10823/sections-10824/lessons-10847/point-2/
世界の取り組み
世界共通の目標として、2015年にパリ協定が採択されました。
その中では、「世界的な気温上昇を工業化以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること。(2℃目標)」「今世紀後半(21世紀)に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成すること。」などが合意されています。
この実現に向けて、世界が取り組みを進めており、2050年カーボンニュートラルといった目標を120以上の国と地域が掲げています。
なぜカーボンニュートラルを目指すのか
それでは、なぜ世界的にここまでカーボンニュートラルを目指しているのでしょうか。
世界の平均気温は、2020年時点で、工業化以前から既に1.1℃上昇しており、さらなる気温上昇が予測されています。(下記のグラフを参照)
近年の国内外で発生した気象災害は、気候変動と無関係ではありません。気候変動に伴い、猛暑や豪雨のリスクが高まっていることが予想されています。日本においても、農林水産業、水資源、自然生態系、自然災害、健康、産業・経済活動への影響が出るとされており、気候変動への対応が求められます。
カーボンバジェットとは?
カーボンニュートラル・脱炭素の緊急性を表す概念には、カーボンバジェットといった概念があります。簡単にいうと、これまで排出されてきた温室効果ガスの総量から、将来的に許容できる排出量を算出することです。
研究によると、世界平均気温の上昇と、過去の人間の活動によって排出された累積の二酸化炭素排出量に比例関係があることがわかっています。
気温上昇を1.5℃に抑えるためには、2020年以降に許容される残りの二酸化炭素排出量はわずか約330ギガトンであり、2020年時点の排出量のままでは、2030年までに超えてしまうとされています。
脱炭素社会の実現のために
気候変動への対応は、近年の主要7カ国首脳会議の最重要課題として議論されており、岸田総理の掲げる新しい資本主義のグランドデザインにおいても、「最大の課題」と記されるなど、乗り越えるべき最大の危機のひとつとされています。
化石燃料から風力や太陽光などの再生可能エネルギーへの転換や、エネルギー効率の向上と省エネルギーの取り組みによって、エネルギー需要の削減をすることが重要です。
また、産業部門においては需要管理やエネルギー効率化、循環型の物質フローなどの対策が、運輸部門においては電気自動車(EV)等のゼロ・エミッション車両(ZEV)への転換やバイオ燃料・水素・合成燃料の拡大といった対策が、求められています。
政策としても、必要な規制を整備するだけでなく、脱炭素社会に向けた取り組みを推進するための施策が必要となってきています。
課題
日本のエネルギー源の約8割(2020年現在)以上を占める燃料依存からの脱却をし、再生エネルギー導入拡大に向けた柔軟なシステムの整備や、輸送・物流に関しての二酸化炭素排出量における割合が高いことなど、課題も山積しています。
まとめ
今回は脱炭素社会についてまとめました。環境問題を考えることによって、現状の自分たちの暮らしの豊かさだけでなく、将来世代や自分たちの将来の暮らしの豊かさのために何ができるかを見直すきっかけになればと思います。
参考になるサイト
- 環境省によるポータルサイト:https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/about/
- JCLP:https://japan-clp.jp/archives/11006